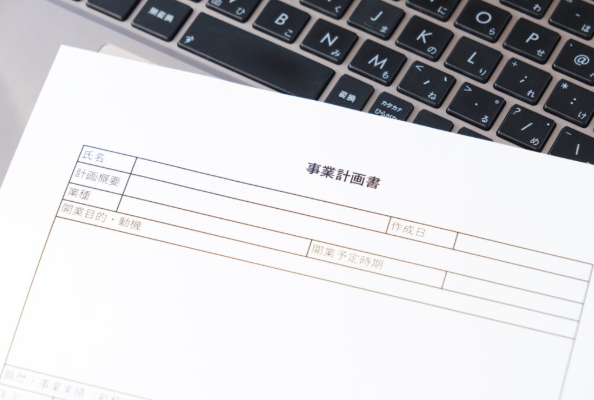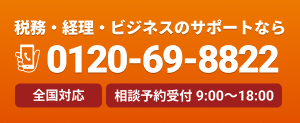メニュー
- 融資
事業資金の調達に利用できる銀行融資の種類や特徴は?選び方のポイントを解説

中小企業や個人事業主が事業を行うにあたって必要になるのが資金調達です。
金融機関などでは事業資金を確保するためのさまざまな融資を提供していますが、どこで借り入れるべきか悩んでしまう方もいるでしょう。
本記事では、事業資金の融資先と比較ポイントをご紹介します。
実は、金融機関や金融商品によって、金利や借入額、返済期間などに大きく違いがあるのです。
資金調達を成功させ、事業を軌道に乗せるためにも、ぜひこの記事を参考に、自社にとってメリットの大きい融資先を選んでいただけたら幸いです。
目次
事業資金とは

事業資金とは、事業を始める、もしくは運営していくために必要となる全ての資金のことです。
店の賃貸料や従業員の給料、工場の設備投資など、業種や事業規模によって必要な事業資金の項目や金額は大きく異なります。
また、事業資金は、用途に応じて以下の2種類に分けられます。
- 設備資金
- 運転資金
それぞれの違いを詳しく把握しておくと、外部から資金調達する際の準備に役立つので、詳しく見ていきましょう。
設備資金
設備資金は、事業に必要な設備を購入する際に一時的に必要となる資金を指します。
主な費用項目は以下のとおりです。
- 土地・建物、店舗、車両、機械の購入
- 知的財産権に係る費用
- 事務所や店舗内の設備や備品(パソコン・コピー機・事務用品など)
- 無形資産(ECサイト構築や自社ホームページ作成費用など)
- 店舗や事務所の改装費 など
基本的には貸借対照表の「固定資産」の欄に計上されるもので、事業の将来のために使う資金となります。
運転資金
運転資金は、事業を継続するために必要な資金です。
主な費用項目は以下のとおりです。
- 買掛金の支払い
- 商品の仕入れ代金
- 広告宣伝費
- 人件費
- 事業所や店舗の光熱費、家賃、通信費
- 外注費 など
このように、ランニングコストと呼ばれる、日々事業を行ううえで継続的に必要となる費用に対する資金が運転資金です。
融資を受けるときの設備資金と運転資金の違い

事業を営むのに必要な設備資金と運転資金についてご説明しましたが、金融機関などから資金を借り入れる際に、設備資金と運転資金では以下の違いがあります。
- 融資限度額
- 融資申し込みの簡易性
- 融資審査の難易度
- 返済期間
ここでは、運転資金と設備資金の借り入れの際の違いを説明していきます。
必要な資金額や利用する金融機関によっても異なりますが、融資を受ける際の参考にしてください。
融資限度額
融資限度額が比較的大きいのが設備資金です。
一般的に設備投資は一度にまとまった資金を要するため、融資限度額が大きく設定されています。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」と「新創業融資制度」で設備資金と運転資金の融資限度額を比較すると、以下のように設備資金の方が大きいことが分かります。
| 設備資金 |
運転資金 |
|
|
新規開業資金 |
7,200万円 |
4,800万円 |
|
新創業融資制度 |
3,000万円 |
1,500万円 |
このように、設備資金は多額の借り入れができる可能性があるため、生産能力の向上や効率化など大規模な設備投資ができるようになるのです。
融資申し込みの簡易性
運転資金の場合、銀行に提出した決算書をもとに金融機関側がおよその融資額を算出します。
一方、設備資金は金額が大きいため、設備投資の必要性や設備投資による収益性、資金の回収力などを見定める必要があり、さまざまな資料を用意する必要があるのです。
そのため、融資の申し込みに関しては運転資金の方が簡易的であると言えるでしょう。
融資審査の難易度
設備資金は運転資金よりも高額になりやすく、金融機関は企業の業績や財務状況によって借入枠を設けているなどの理由から、審査ハードルが高くなる傾向にあります。
しかし、必要な資料を提示し資金使途が明確に説明できれば審査に通る可能性が高まります。
一方、運転資金は設備資金よりも借入額が少なく、短期返済となるため審査基準が比較的ゆるく、融資を受けやすいです。
ただし、使途が不明確であり、運転資金以外で使われても簡単には判別できないことから、使途を明確に説明できなければ融資を受けられない可能性があります。
返済期間
運転資金と設備資金では融資の形態が異なるため、融資の返済期間も異なります。
事業を運営するための資金である運転資金は、返済期間が比較的短めに設定されており、一般的に運転資金の融資の返済期間は3〜7年です。
一方、高額になりやすい設備資金は返済期間も長めに設定でき、耐用年数が短い資産については長期返済にはできませんが、5〜10年程度、条件を満たせば最長20年の返済期間を設定することができます。
短期の返済期間が設定されるケースが多い運転資金を借り入れる際は、返済計画をしっかりと立てておくのが望ましいです。
融資先を選ぶ際の比較ポイント

事業者が融資先を選ぶ際には、以下の項目を比較しましょう。
- 金利
- 担保や保証人
- 返済期間
- 手数料などの諸費用
- 金融機関の信用度
それぞれ詳しく説明していきます。
融資先を選ぶポイント①金利
融資を受けた場合、借りた金額に対して、金融機関が設定した金利に基づいた利息を支払う必要がありますが、融資先によって金利が大きく異なります。
金利が高ければ、返済期間が長いほど支払額がどんどん増えるため、借入金を完済するまでの負担を最小限に抑えるためには、できる限り金利の低い金融機関や金融商品を選ぶのがおすすめです。
各金融機関が提供する融資の金利の目安は以下のとおりです。
- 日本政策金融公庫:年利1〜3%
- 銀行:年利2〜9%
- ノンバンク:6〜18%
ただし、金利が低い融資は審査基準が厳しくなる傾向にある点に注意しましょう。
融資先を選ぶポイント②担保や保証人
担保や保証人の有無も融資先を決める際のポイントです。
まとまった金額の融資を受けるときに、金融機関がリスクを管理するために担保や保証人を付ける必要があるケースが多く、担保や保証人付き融資は比較的低金利で、まとまった融資を受けられる可能性がある一方、担保や保証人の確保や手続きに時間があるなどのデメリットがあります。
無担保・無保証人の融資は創業時でも利用しやすいですが、担保付き融資に比べて金利が高く、融資額上限額が低めに設定される傾向にあるなど、それぞれにメリット・デメリットがあるため、どちらを選択するかが重要な決定となるでしょう。
無担保・無保証人で融資をしている金融機関としては、日本政策金融公庫が代表的です。
融資先を選ぶポイント③返済期間
事業向けの融資は、返済期間の長さも金融機関や商品で違いがあるため、事業の経営状況や返済計画に合わせて適している金融機関を見つけてください。
毎月の返済に余裕を持たせたいのであれば長期返済が可能な融資を選ぶのがおすすめです。
ただし、返済期間を長くすると利息分も増えるため、総支払額が高くなる可能性が高い点を覚えておき、毎月の返済額を少なくするか、総支払額を最小に抑えるかを考えましょう。
融資先を選ぶポイント④手数料などの諸費用
融資は金利以外に、手数料や保証料などの費用が発生する場合があり、資金繰りに大きく影響を及ぼす恐れもあるので慎重に検討してください。
たとえば、信用保証協会を通じた融資には借主の返済が滞った場合に、借主に代わって信用保証協会が金融機関に立て替え払いを行う保証付き融資などがありますが、保証料が発生するため、このような諸費用を踏まえたうえで融資を受けなければなりません。
手数料などの保証料が高いと、返済総額が増える点を把握しておきましょう。
融資先を選ぶポイント⑤金融機関の信用度
事業資金の融資を受ける場合、トラブルに巻き込まれないためにも金融機関との相性や信用度を確認することも重要です。
融資を行う金融機関の中には、「闇金業者」と呼ばれるような悪徳商法で融資する業者も存在しており、強引に契約を迫ったり、契約後に金利を大幅に上げたりする恐れがあります。
金融機関からの融資を断られてしまったときやすぐに資金調達をしたいときに、知名度の低い金融機関に融資を申し込む事業者もいますが、中にはこのように悪質な業者もいますので、業者の評判などをチェックして、少しでも怪しい点があれば利用を控えるようにしましょう。
事業融資を受けられる金融機関を紹介!

事業資金の主な借入先は以下のとおりです。
- 銀行のプロパー融資
- 信用金庫・信用組合の融資
- 信用保証協会の保証付き融資
- ノンバンク融資
- 地方自治体の融資制度
- 日本政策金融公庫の融資
それぞれの特徴を説明していきますので、先述した比較ポイントを参考にしながら、自社に合った融資先を検討しましょう。
銀行のプロパー融資
銀行のプロパー融資は、メガバンクや地方銀行などの金融機関から資金を調達する手段です。
プロパー融資は、銀行が独自の責任のもと資金を貸し付けるというもので、銀行と直接取引となるため、審査が厳しくなります。
全国の主要都市に支店を持つ大規模な銀行(メガバンク)は利息が比較的低く設定されていますが、大企業向けであり、創業したばかりの企業や事業規模が小さい企業には融資ハードルが高いです。
一方、各都道府県に本店を置き、各地方を中心に営業を展開している地方銀行は金利がメガバンクより高めに設定されている傾向にありますが、融資ハードルは低くなります。
信用金庫・信用組合の融資
信用金庫や信用組合は、地域社会の利益を優先しているため、規模の小さい企業や個人事業主でも比較的借り入れしやすいです。
ただし、地域が限定されている点や、地方銀行などと比べて金利が若干高めに設定されている点に注意しましょう。
また、信用金庫や信用組合の融資を受けるためには、出資をして会員になる必要があります。
信用保証協会の保証付き融資
信用保証協会は、信用保証協会法に基づいて、中小企業や小規模事業者の円滑な資金調達を支援することを目的に設立された公的機関です。
信用保証協会が保証人となり、借主が返済できなくなった場合に、借主に代わって信用保証協会が金融機関に立て替えて払う保証付き融資があります。
信用保証協会から保証をもらうためには、資金の返済が問題なくできる事業者であると認めてもらわなければならず、しっかりとした事業計画を立案・作成する必要があります。
ノンバンク融資

ノンバンクは預金や為替業務を行わず、貸付業務に特化した銀行以外の金融機関のことで、代表的なものに信販会社や消費者金融があります。
ノンバンク融資は審査が比較的緩く、短期間で行われる点や、担保や保証人がなくても利用できることから、急ぎで資金が必要な場合に利用されるケースが多いです。
ただし、他の金融機関の融資に比べて金利が高く設定されているため、長期的な借り入れには向いていません。
地方自治体の融資制度
地方自治体には独自に設けている融資制度もあります。
各自治体としては、中小企業の経営安定化や創業支援などの目的で行なっているため、通常の融資に比べて、中小企業が比較的低金利で融資を受けやすくなっているのです。
ただし、自治体ごとに融資条件や金利が異なるため、地方自治体からの融資を受ける際は、自社の地域の自治体の融資条件等を確認しましょう。
日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫は、民間金融機関を補完する目的で国が運営している金融機関で、新しく事業を始める場合や経営改善を図る中小企業、個人事業主への融資を積極的に行っています。
日本政策金融公庫の融資は国の政策に則った固定金利、長期の融資制度のため、安心して利用することができるでしょう。
ただし、融資実行までに1ヶ月程度かかるため、急な資金調達には向いていません。
事業に必要な資金を得るためにも融資先の特徴を知ろう

中小企業や小規模事業者、個人事業主向けの融資にはさまざまなものがありますが、それぞれの融資スピード感や金利、融資限度額、審査難易度などを把握し、自社の目的や経営状況に応じて最適な手段を選ぶことが重要です。
また、創業時の融資や低金利で借りられる融資の審査は特に厳しくなる傾向にあるため、あらかじめ綿密な事業計画や返済計画を立てたうえで申し込みをしましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は 国税OB・元税務署長 が所属し、 確定申告・相続・会社設立・融資サポート・労務手続きなど 幅広いサービスを提供する税理士法人です。
全国からの 税務・労務相談実績 年間1,000件以上
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から税務調査、相続、会社設立まで幅広く対応可能
- 融資や助成金、補助金の申請など資金調達サポートにも豊富な実績
- 顧問税理士が対応に困った案件も途中からサポートできます
30秒で完了かんたん融資診断