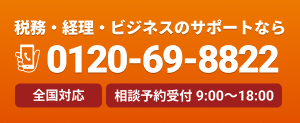メニュー
- 融資
運転資金の借入理由はどう説明すべき?スムーズに融資を受けるためのポイントも解説

事業の運転資金が不足しており、金融機関などからの借入を検討している方もいるでしょう。
しかし、運転資金の融資を受けるときは、しっかりと借入理由を説明しなければなりません。
なぜなら、借入目的は融資先にとって審査をするうえで重要な判断材料となり、説明を疎かにすると後々トラブルになる可能性が高いからです。
本記事では、運転資金の借入をする際に理由を説明することの重要性やスムーズに融資を受けるためのコツを解説します。
運転資金を借り入れようと検討している方はぜひこの記事を参考に、必要な資金を調達できるよう準備を進めましょう。
運転資金とは

運転資金とは、事業を運営するのに必要な資金を指します。
企業が事業運営を維持していくためにかかる、商品の仕入れや従業員への給料、広告費などさまざまな費用を運転資金と呼び、運転資金が足りなければこれらの必要な資金が支払えず、事業存続が困難になってしまうのです。
そのため、企業は適切な資金繰りを行い、常に運転資金を備えておくか、そうでなければ金融機関からお金を借りるなどして、運転資金を調達する必要があります。
設備資金との違い
運転資金と混同されやすいものに「設備資金」がありますが、運転資金と設備資金との違いは継続的に必要なお金かどうかにあります。
設備資金は、建物や機械、車といった設備や備品など、事業に必要となるものを購入するために一時的に必要となる資金を指しますが、一方、運転資金は日々の事業を続けていくために継続して発生する資金です。
具体的に、支払いには以下のような違いがあります。
|
運転資金で支払うもの |
設備資金で支払うもの |
| ・人件費
・店舗や事務所の家賃 ・商品の仕入 ・水道光熱費 など |
・店舗や事務所の敷金、保証金
・店舗の内装工事費 ・客用テーブル、椅子などの備品 ・業務で必要な車の購入費 など |
このように、運転資金とは設備資金では性質が異なるため、分けて考えておきましょう。
運転資金の計算方法
運転資金に余裕があれば、資金繰りをそこまで考慮する必要はありませんが、不足しそうな場合、なるべく早めに自社で必要な運転資金を把握し、資金調達を検討しなければなりません。
おおよその運転資金は、以下の計算式で求めることが可能です。
【運転資金=売掛債権 + 棚卸資産 – 買掛債務】
それぞれの項目を分かりやすく説明するとこのようになります。
- 売掛債権(まだ入金されていない代金)
- 棚卸資産(まだ売れていない商品)
- 買掛債務(これから支払う代金)
日本では、取引の際に商品と代金を同時に交換するケースは少なく、掛け取引が多く行われているため、入金と支払にタイムラグが生じ、その足りない資金を補うために運転資金が必要になるのです。
運転資金の調達方法

運転資金が必要になったときに、どこに相談すれば良いか迷う方も多いでしょう。
主な資金調達方法としては、以下が考えられます。
- 融資(金融機関から借りるお金)
- ビジネスローン(ノンバンクが提供している事業制ローン)
- 補助金・助成金(国や地方公共団体、民間団体などから支給されるお金)
運転資金を調達する方法として、はじめに思い浮かぶのが融資を受ける方法だと思いますが、銀行、信用金庫、政府系金融機関、制度融資など、融資をどこから受けるかによって違いがあります。
それぞれのメリット・デメリットをまとめました。
|
融資先 |
メリット |
デメリット |
|
銀行 |
・金利が比較的低い
・大きな金額の融資を受けられる ・長期返済が可能 |
・審査が厳しい
・融資限度額が企業の財務状況や経営状況によって変わる ・創業したばかりの企業は難しい |
|
信用金庫 |
・銀行と比較して融資が通りやすい | ・銀行よりも比較的金利が高い
・融資限度額が銀行よりも高い |
|
政府系金融機関 (日本政策金融公庫など) |
・小規模や中小企業向けの融資制度がある
・無担保・無保証人でも利用できる |
・融資を受けるために会員になる必要がある |
|
自治体の融資制度 (金融機関・自治体・信用保証協会の3者が連携する融資) |
・審査が通りやすい
・金利が低い ・長期借入に向いている |
・手続きに時間がかかる |
運転資金の借入ができないケース
先述した融資を行なっている機関に申し込んだとしても、以下のケースでは審査に通らない可能性が高いです。
- 根拠に基づいた金額を提示していない
- すでに多額の借入を行っている
- 税金や社会保険料に滞納がある
- 借入理由が明確でない
金融機関側としては、貸したお金を回収できるかが重要になってくるため、返済計画に無理がある、すでに多額の借入がある、税金を滞納している事業者の場合は信用に足りず、融資を断られる恐れがあります。
また、後ほど詳しく解説しますが、何に対して、どのような理由で、いくらお金が必要なのかを明確に説明できなければ借入は難しいと言えます。
運転資金の借入には明確な理由が必要

運転資金を借り入れる際には明確な理由を提示することが重要であり、資金使途によって、融資の種類はもちろん、返済期間や金利も変わってくるのです。
運転資金と一口に言っても、以下のように様々な種類があります。
- 経常運転資金(会社を運営するうえで常に必要な資金)
- 増加運転資金(売上増加に伴って必要になる資金)
- 減少運転資金(売上の減少に伴って必要になる資金)
- 季節運転資金(一時的な需要増加に伴って必要になる資金)
- 設備未払金決済運転資金(設備資金として購入した費用が半年以上支払えなかった場合に充てる資金)
そのため、単に「運転資金が必要」と伝えるだけでは融資審査には通りません。
ですから、融資を申し込む際は、資金を何に使うかを明確にして納得してもらえるよう説明しなければならないのです。
別の目的で使用すると資金使途違反になる
資金使途違反というものがありますが、これは、融資を受ける際に金融機関へ事業者が説明した資金使途通りに資金を使わずに、別の目的で流用することを指します。
銀行融資の場合、申し込み時の見積書や請求書の通りに支払いが行われているか、領収書の提出などにより資金使途違反になっていないかを確認します。
そのため、申し込み通りに資金が使われていなければ、資金使途違反が金融機関にバレてしまうのです。
資金使途違反とみなされた場合のリスク
資金使途違反が判明した場合、借入金の全額一括返済を求められたり、その金融機関からの取引を今後いっさい受けられなくなったりする可能性があります。
また、信用保証協会の保証付き融資の場合には、保証協会内ブラックリスト入りしてしまい、その後別の金融機関で保証付き融資を申し込んだとしても、審査に落ちてしまう恐れがあるのです。
金融機関側としては、申請された資金使途以外の使い方をされたときに、想定通り資金を回収できない可能性が高まるため、資金使途違反に対して厳しいペナルティを課しています。
運転資金を借り入れる具体的な理由

運転資金の借入理由は事業者によって異なりますが、主なケースでは以下が挙げられます。
- つなぎの資金
- 開業・事業拡大のための資金
- 季節性の資金
- 借入を一本化するための資金
先述した通り、運転資金の借入の目的は融資審査において重要な判断材料となり、資金使途違反となると資金の全額返還や今後融資を受けられないなどのリスクがあるため、自社で明確にしておくことが重要です。
運転資金を借り入れる主な理由について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
つなぎの資金
資金繰りが苦しくなり、つなぎとして融資を受ける必要があるケースがあります。
掛け取引をしている会社は多くありますが、この場合、売上と入金にタイムラグが生じてしまうのです。
掛け取引は売上があれば後々にお金は入ってきますが、入金前に支払わなければならない費用が多く発生すると、手元資金がなくなり、売上が順調に伸びるほど資金繰りが苦しくなります。
そのため、つなぎとして運転資金が必要になりますが、売掛債権が順調に回収できれば、借入金も問題なく返済可能です。
開業・事業拡大のための資金
起業や開業時、もしくは会社の事業拡大の際にはまとまった資金が必要になります。
例えば、起業するにあたって店舗や事務所を借りる場合、賃料のほか、水道光熱費やオフィス用品、家具などの備品がかかるだけでなく、売上に対する入金があるまでの間に支払わなければならない人件費や仕入代金などの運転資金が発生するため、その不足分を補うために資金調達しなければならなくなるのです。
また、今よりも売上を伸ばしたいときや事業を拡大したいときに、店舗の増設や優秀な社員の雇用などで運転資金が必要になるケースもあります。
季節性の資金
売上に季節変動がある事業者は多いです。
たとえば、冬に賞与や年末商戦に使うために支出が増えるなど、毎年決まった時期に運転資金が必要になる場合があります。
このようなケースでは、運転資金の借入した後、その返済を売上ピークの回収に合わせるのが一般的で、短期借入であることから、金融機関としても融資がしやすいです。
借入を一本化するための資金
様々な期間から運転資金の融資を受けていると、返済が複数口になります。
この場合、運転資金をひとまとめに借り換える事業者もいます。
支払いを一本化することで、返済スケジュールが管理しやすくなるほか、借入額が大きくなるため低金利で借りられる可能性があるなどのメリットがあるのです。
事業融資の借り換えを行う際には借り換え元と借り換え先どちらにも手数料を支払う必要があるため、運転資金が必要になります。
スムーズに融資を受けるためのコツ
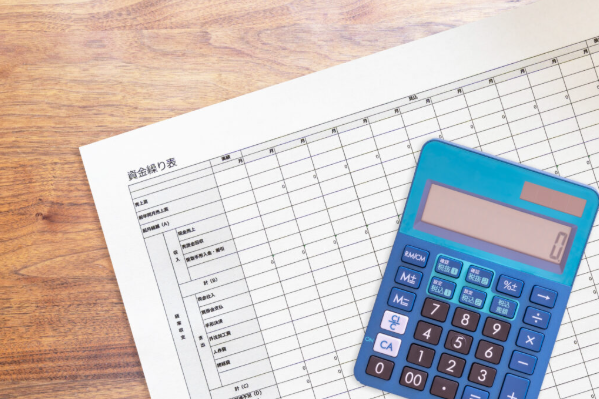
運転資金の調達を成功させるためには、ご紹介したような借入理由を明確に説明することが重要ですが、スムーズに融資を受けるためにも以下のポイントを押さえておくとより安心です。
- 前向きな理由を伝える
- 資金繰り表を添付する
- 自己資金をできるだけ多く準備する
- 実現可能な事業計画書を作成する
それぞれ詳しく説明していきます。
前向きな理由を伝える
資金使途の理由を説明する際は、前向きな内容にするのが望ましいです。
例えば、「不況のため利益が下がり、資金繰りが厳しくなった」「他の返済のために充てる原資がない」などの理由では金融機関が資金を回収できるかどうか不透明で、不信感を抱いてしまいます。
そのため、使途違反になってはいけないのが大前提ですが、金融機関が融資を前向きに検討できる理由を述べ、融資担当者を安心させましょう。
資金繰り表を添付する
融資先に資金使途を説明する際は、資金繰り表を必ず添えるようにしましょう。
融資の申し込みに資金繰り表の添付要件がない場合もありますが、運転資金の調達の場合には、返済資金をどのように捻出するのかを融資先に示すことが大切なのです。
資金繰り表を添付して資金がしっかりとまわる計画を証明すれば、審査に通る可能性が高まります。
自己資金をできるだけ多く準備する
融資の際、金融機関側は貸し倒れのリスクを抱えるため、返済できる見込みがないと判断されると融資を断られる恐れがあります。
そのため、運転資金で融資を受ける際は、自己資金をできるだけ多く用意し、金融機関が抱える不安を解消することが有効です。
経営状況や融資を受ける金額によっても異なりますが、調達したい金額の2割程度自己資金でまかなえると良いでしょう。
融資金額が少ないほど、審査通過の確率が高まります。
実現可能な事業計画書を作成する
実現可能な範囲の詳細な事業計画書の作成も融資を受けるコツです。
事業計画書の内容が魅力的であったとしても、それが実行できなければ利益を得られず、融資側が資金を回収できないからです。
そのため、融資担当者を納得させるために、事業計画書の内容は、具体的な内容かつ実行可能で、融資担当者にとって理解しやすいものであることを意識して作成しましょう。
運転資金の融資を受ける目的を明確にしよう
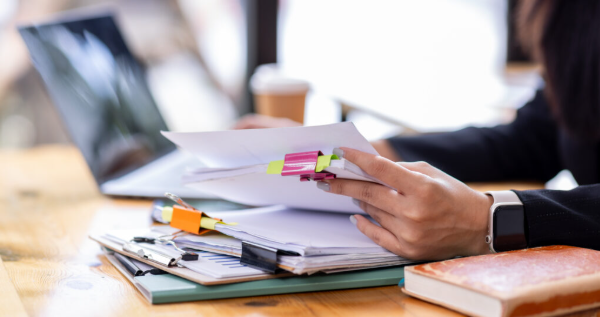
事業を営むうえで運転資金は欠かせないもので、自社に資金が不足する場合は融資などの資金調達方法を検討しなければなりません。
その際、借入をする理由をしっかり説明することは、金融機関の審査において非常に重要な情報となるため、申し込み前に自社でどのような目的で融資が必要なのか明確にしておきましょう。
また、審査に通過し融資を受けられたとしても、資金使途とは違う目的で資金を流用しないよう注意してください。
この記事を参考に、十分な運転資金を用意して、事業を順調に展開していただけたら幸いです。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は 国税OB・元税務署長 が所属し、 確定申告・相続・会社設立・融資サポート・労務手続きなど 幅広いサービスを提供する税理士法人です。
全国からの 税務・労務相談実績 年間1,000件以上
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から税務調査、相続、会社設立まで幅広く対応可能
- 融資や助成金、補助金の申請など資金調達サポートにも豊富な実績
- 顧問税理士が対応に困った案件も途中からサポートできます
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断