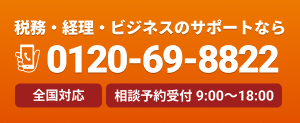メニュー
- 融資
建設業で資金調達する方法とは?資金繰りを改善する方法についても解説

建設業において、円滑な資金調達は事業の成功を左右する重要な要素です。
資金に余裕があれば、新規プロジェクトへの投資や事業規模の拡大が容易になり、企業の成長スピードを加速させることができます。
必要なタイミングで十分な資金を確保できなければ、新規案件の受注や進行が困難になり、事業運営に大きな影響を及ぼしてしまうのも事実です。
本記事では、建設業で資金調達する方法について紹介します。
他にも「建設業で資金調達をする際のポイント」や「建設業で資金繰りを改善する方法」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、建設業で資金調達を成功させてみてください。
建設業で資金調達する方法

建設業で資金調達する方法については、以下の5つが挙げられます。
- 資金調達方法①:日本政策金融公庫
- 資金調達方法②:金融機関のプロパー融資
- 資金調達方法③:信用保証協会付き融資
- 資金調達方法④:ファクタリングサービス
- 資金調達方法⑤:手形割引
それぞれの方法について解説していきます。
資金調達方法①:日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、民間の金融機関が提供する融資を補完し、事業者の活動を支援する目的で、2008年に設立された政府系の金融機関です。
「株式会社日本政策金融公庫法」に基づいて運営されており、特に資金調達が難しい事業者を支援する役割を担っています。
その代表的な制度の一つに新創業融資制度があり、創業間もない事業者やまだ確定申告を2期完了していない事業者向けの融資制度です。
特に、事業実績が十分でない建設業者などにとって、通常の融資審査は厳しいものですが、この制度を利用することで資金調達のハードルを下げることができます。
しかし、新創業融資制度を利用する際には、提出書類の種類が多く、審査に一定の時間がかかる点には注意が必要です。
資金調達方法②:金融機関のプロパー融資
プロパー融資とは、金融機関が独自の基準で審査を行い、直接事業者に貸し付ける融資のことを指します。
通常、信用保証協会の保証が付いた融資では、もし事業者が倒産などで返済不能になった場合、金融機関は信用保証協会に代位弁済を請求し、融資資金の回収を図ることができます。
一方、プロパー融資ではこの保証がないため、万が一事業者が返済できなくなると、金融機関は融資資金を回収できないリスクを負うことになります。
このリスクを軽減するため、金融機関は慎重に審査を行い、事業者が確実に返済できるかどうかを事業内容や財務状況を基に判断します。
審査の結果によっては、担保や保証を求める場合もありますが、必ずしも経営者保証を必要とするわけではないので注意が必要です。
また、信用保証協会付きの融資とは異なり、保証料が不要であり、融資の上限額にも特に制限がない点がプロパー融資の特徴です。
資金調達方法③:信用保証協会付き融資
信用保証協会とは、事業者が銀行などの金融機関から融資を受ける際に、保証人として支援する公的な機関です。
信用保証協会が関与する融資制度では、万が一、事業者が返済できなくなった場合、信用保証協会が事業者に代わって金融機関へ弁済を行います。
しかし、事業者はこの保証を受けるために、信用保証協会へ一定の保証料を支払う必要があります。
信用保証協会の保証を受けるためには、以下の3つの条件を満たしていることが求められます。
- 企業規模(資本金や従業員数)
- 業種(対象となる事業内容)
- 所在地や事業歴(事業を行っている地域や業歴)
例えば、建設業においては、資本金3億円以下、従業員数300人以下の企業が対象となります。
また、建設業は信用保証協会の対象業種に含まれますが、事前に適切な許認可を取得していることが求められます。
さらに、事業者が信用保証協会の保証を受けるには、原則としてその協会の管轄する地域内で事業を営んでいることが必要です。
加えて、一部の保証制度では、一定の業歴が求められることもあります。
資金調達方法④:ファクタリングサービス
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社へ譲渡することで、支払期日を待たずに現金を手にできる資金調達手法です。
特に、受注から入金までの期間が長くなりがちな建設業などの業界では、ファクタリングを活用することで資金繰りの改善ができることで、資金が滞るリスクを軽減し、事業運営の安定化につながります。
さらに、売掛先が万が一支払い不能に陥った場合でも、利用企業が代わりに返金する義務がない点が挙げられ、ファクタリング会社が売掛金の未回収リスクを引き受けるためです。
そのため、単なる資金調達手段にとどまらず、未回収リスクを回避する方法としても利用されています。
資金調達方法⑤:手形割引
手形割引とは、支払期日が到来する前の手形を、銀行や専門の業者に売却し、現金化する仕組みのことです。
特に建設業界では、依然として手形による取引が一般的に行われており、その結果、入金までの期間が長くなりやすく、資金繰りに悩むケースが多く見られます。
しかし、支払期日前の手形であっても、銀行や手形割引業者に売却することで、早めに現金を手にすることが可能です。
しかし、手形割引は実質的に融資とみなされるため、銀行で利用する場合は、手形を発行した企業だけでなく、割引を申し込む側の信用状況も審査の対象となるので、審査に通らず利用できないこともあります。
万が一、銀行の審査に通らなかった場合でも、手形割引業者が引き受けてくれることがあります。
しかし、その場合は高額な割引手数料が発生することもあるため、慎重に業者を選ぶ必要があります。
建設業で資金調達をする際のポイント

建設業で資金調達をする際のポイントについては、以下の4つが挙げられます。
- 自己資金を準備する
- 金融機関との良好な関係を築く
- 建設業許可の取得をして信用を高める
- 事業計画や返済計画をしっかりと立てているか
それぞれのポイントについて解説していきます。
自己資金を準備する
金融機関から融資を受ける際には、自己資金の額が重要なポイントとなります。
特に創業融資を申請する場合、必要な資金のうち約30%を自己資金として準備するケースが一般的です。
また、創業時だけでなく、事業開始後に運転資金の融資を受ける場合にも、自己資金が十分にあると審査の通過率が高まります。
さらに、融資の審査に通ったとしても、実際に資金が手元に入るまでには一定の時間がかかるので、現在の資金状況に余裕があったとしても、将来的な資金繰りが厳しくなる可能性がある場合は、早めに融資を申し込んでおくのが賢明と言えます。
金融機関との良好な関係を築く
金融機関複数の金融機関とつながりを持つことが重要になります。
実際に、資金調達の場面では、「A銀行では融資を断られたが、B信用金庫なら対応してもらえた」といったケースも珍しくありません。
そのため、資金調達の選択肢を広げておくことが経営の安定につながります。
具体的な方法としては、日頃から預金や融資の取引を継続的に行い、金融機関との信頼関係を築くことが大切です。
また、積立預金を活用したり、従業員向けのクレジットカード発行に協力したりと、金融機関からの依頼にできる範囲で応じることも関係強化につながります。
さらに、金融機関が主催するイベントや商談会へ積極的に参加することで、自社に対する金融機関の評価が高まり、融資などの相談がしやすくなります。
建設業許可の取得をして信用を高める
建設業で円滑に資金調達を行うには、建設業許可の取得などを通じて企業の信頼性を高めることが重要です。
建設業許可をはじめとする各種認証は、企業が一定の業務水準や安全基準を満たしていることの証明となり、金融機関からの融資審査において有利に働く可能性があります。
さらに、こうした許可や認証を取得することで、企業はより多くのプロジェクトに参加する資格を得られ、結果として事業の成長や取引の機会を拡大することができます。
事業計画や返済計画をしっかりと立てているか
融資を受ける際に提出する事業計画書は、審査を通過するための重要な資料になるので、事業計画や返済計画をしっかりと立てているかが重要なポイントになります。
過去の経歴や実績、自店舗の強み、競合店との差別化ポイント、そして将来の展望などを具体的に示し、「事業の成長が見込め、返済能力がある」と判断されなければ、融資の承認は得られません。
事業計画書には、事業に関連する経験や経歴を厳選して記載するようにしましょう。
これまでの準備や実績も、事業の継続性を評価する重要な要素となります。
また、将来の売上や経費の見通しについては、過去のデータを根拠に現実的な数値を示すことで、計画の妥当性を証明できます。
このように、融資担当者が納得できるよう、説得力のある事業計画書を作成することが成功のカギと言えます。
建設業で資金繰りが難しいと言われる理由
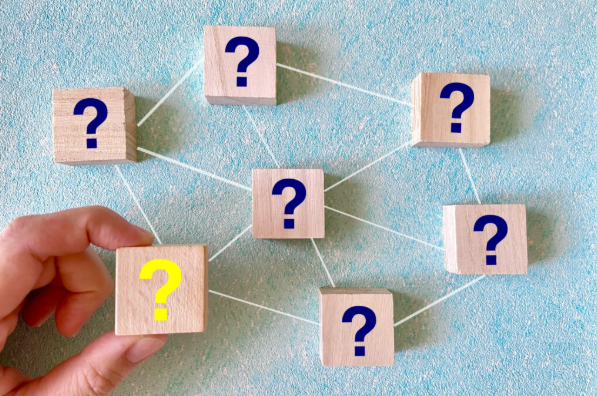
建設業で資金繰りが難しいと言われる理由については、以下の4つが挙げられます。
- 先出の出費が多い
- 入金されるまでの期間が長い
- 手形取引が多い業種
- 融資審査に通りづらい
それぞれの理由について解説していきます。
先出の出費が多い
建設業における資金繰りが難しい理由の一つとして、先行して多額の費用を投入しなければならない点が挙げられます。
建設プロジェクトでは、工事が本格的に始まる前の段階で、資材の購入や重機の準備、労働力の確保などに多くの資金を投じる必要があります。
そのため、十分な資金が確保できていないと、工事の進行が遅れたり、最悪の場合には中断せざるを得なくなるリスクがあります。
このような事態を避けるためにも、事前に綿密な資金計画を立て、適切なキャッシュ・フローを維持することが重要です。
入金されるまでの期間が長い
建設業では、工事の受注から作業の完了、入金までの期間が他の業界と比べて長くなりやすいので、資金繰りの難しさが生じやすい業種の一つといえます。
通常、工事が完了するまでは報酬を受け取ることができませんが、その間にも資材の購入費や職人の給与、下請け業者への支払いなど、さまざまな経費が発生します。
これらの費用は、工事が始まる段階から継続的に必要となるため、資金のやりくりが求められます。
また、工期の延長や追加工事の発生など、予測しにくい要因によってさらに支出が増えることもあります。
その場合、企業側が自己資金で立て替えなければならず、資金繰りの負担が一層大きくなる可能性があります。
手形取引が多い業種
建設業において資金繰りが難しくなる要因の一つとして、手形取引が多く行われている点が挙げられます。
手形取引とは、特定の期日に一定の金額を支払うことを約束する証書を利用した決済方法です。
この取引方式では、実際に現金が手元に入るまでに時間がかかることがあり、すぐに資金を確保できないケースも少なくありません。
建設会社は、工事の初期段階で多額の資材費や人件費を支払う必要がありますが、受注先からの支払いは工事の進行状況に応じて遅れることが一般的です。
そのため、会社の手元資金が不足しやすくなり、円滑な事業運営を妨げる要因となります。
融資審査に通りづらい
金融機関では、建設業界を「構造的に不況に陥りやすい業種」と見なす傾向があり、そのため融資の審査が厳しくなることが多いです。
銀行側の視点では、建設業は「資金の流れが安定しにくい」「突発的な要因で資金不足に陥るリスクが高い」といったイメージが強いため、慎重な対応を取ることが一般的です。
しかし、資金繰りが厳しいからこそ、融資を必要とする企業が多いのも事実です。
金融機関が一切相手にしないわけではなく、会社の財務状況や受注の安定性などが評価されれば、融資を受けられる可能性は十分にあります。
建設業で資金繰りを改善する方法

建設業で資金繰りを改善する方法については、以下の4つが挙げられます。
- 原因を調査する
- 資金繰り表を作成する
- 赤字案件は受注しない
- 入金と支払いのタイミングのズレを少なくする
それぞれの方法について解説していきます。
原因を調査する
資金繰りを改善するには、まず現在の厳しい状況が生じている原因を明確にすることが重要です。
具体的には、人件費や固定費を含め、削減可能なコストがないか細かく確認するようにしましょう。
主な要因として、以下が挙げられます。
- 赤字経営や売上の大幅な変動
- 借入金の返済負担の増加
- 過剰な在庫
また、売掛金の回収までに時間がかかる場合、資金繰りが悪化しやすくなります。
特に、工期が長くなりがちな建設業では、この影響を受けるケースが多いため、注意が必要です。
資金繰り表を作成する
建設業で資金繰りを改善する方法として、会計ソフトなどを活用して日々の入出金を記録し、状況を可視化するのが重要です。
実際に、適切な管理を怠ると、支払いと入金のズレによって資金不足に陥るリスクが高まります。
また、契約している税理士に相談したり、商工会議所のサポートを受けたりするのも有効な方法と言えます。
まずは、自社に合った方法で資金繰り表を作成する習慣を身につけることが大切です。
赤字案件は受注しない
企業の健全な経営を考えると、利益を確保できない案件を引き受けることは避けることが重要です。
恩義や慣習にとらわれるのではなく、しっかりと収益を見込める工事の受注へとシフトしていきましょう。
特に建設業界では、業績の低迷や競争の激化により、利益率の低い案件を次々と受注し、結果として資金繰りが厳しくなるケースが多く見られます。
「目先の現金収入が欲しい」といった短期的な視点ではなく、「最終的にどれだけの利益が確保できるのか?」という経営的な判断を常に持つことが重要です。
もちろん、長年の付き合いや過去に助けてもらった恩義を考慮しなければならない場面もあります。
しかし、将来にわたって健全な事業運営を続けるためにも、明らかに赤字となる案件には慎重に対応し、無理な受注は控えるようにしましょう。
入金と支払いのタイミングのズレを少なくする
入金と支払いのタイミングのズレを少なくするために、前金の交渉を検討しましょう。
特に大規模な工事では、材料費や人件費などの工事原価を事前に受け取ることで、資金の流れをスムーズにできます。
そのため、発注者と交渉し、工事の進捗に応じた段階的な支払いを提案するのも有効です。
このように、資金繰りを安定させるためには、入金と支払いのタイミングのズレを最小限に抑えるような交渉が重要です。
自社に合った資金調達方法で資金繰りを改善しよう!

今回は、建設業で資金調達する方法を紹介しました。
建設業界では、材料費や外注費などの支払いが先行しやすく、売上の入金までに時間がかかるケースが多いため、資金繰りに苦労するケースが多くみられます。
そのため、業界特有の資金面の課題を解決できる資金調達の手段を選ぶことが、資金繰りを円滑にするための重要なポイントとなります。
今回の記事を参考にして、自社に合った資金調達方法で資金繰りを改善しましょう。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は 国税OB・元税務署長 が所属し、 確定申告・相続・会社設立・融資サポート・労務手続きなど 幅広いサービスを提供する税理士法人です。
全国からの 税務・労務相談実績 年間1,000件以上
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から税務調査、相続、会社設立まで幅広く対応可能
- 融資や助成金、補助金の申請など資金調達サポートにも豊富な実績
- 顧問税理士が対応に困った案件も途中からサポートできます
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断