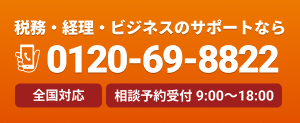メニュー
- 融資
飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるポイントとは?融資を受ける流れも解説

飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるポイントを把握しておくことで、融資の審査が通りやすくなります。
万が一、審査に通らなかった場合、再挑戦までに半年から1年ほどの期間を空ける必要があるため、慎重に準備することが重要です。
本記事では、飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるポイントについて紹介します。
他にも「飲食店が日本政策金融公庫から融資を受ける流れ」や「飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるメリット・デメリット」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるポイントについて理解を深めてみてください。
飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるポイント

飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるポイントについては、以下の5つが挙げられます。
- 自己資金を用意する
- 事業計画書を作り込む
- 明確な資金計画を立てる
- 信用情報に傷を付けない
- 面談の準備を入念にする
それぞれのポイントについて解説していきます。
ポイント①:自己資金を用意する
日本政策金融公庫の融資審査を通過しやすくするには、希望する融資額に応じた自己資金を準備することが重要です。
以前の制度では融資申込額の1/10以上の自己資金があることが要件でしたが、現在はその要件は撤廃されています。
しかし、要件がなくなったからといって自己資金がなくても良い訳ではありません。従来と変わらず、少なくとも希望融資額の10~30%程度の自己資金があることが理想です。
ポイント②:事業計画書を作り込む
飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるポイントとして、事業計画書を作り込むことが挙げられます。
実際に、融資を申し込む際には、事業計画書の提出が求められ、決められたフォーマットに沿って詳細に記入し、数字や内容に整合性が取れていないと審査に影響を及ぼす可能性があります。
そのため、事業計画書の作成に慣れていない方にとっては、ハードルが高いと感じてしまう可能性が高いです。
また、経営者の経歴やこれまでの事業経験は、返済能力を判断するうえで非常に重要な要素となるので、できる限り詳しく記載し、自身の強みや実績を明確に伝えることが大切です。
ポイント③:明確な資金計画を立てる
日本政策金融公庫の融資審査に通るためには、資金の使い道を明確にし、納得のいく資金計画を作成することが重要です。
用途がはっきりしないと、資金の必要性が十分に伝わらず、審査が通らなかったり、希望額より少ない金額しか借りられなかったりする可能性があります。
そのため、融資の目的や資金の使い道を具体的に示し、見積書や資金繰り表などを用いて根拠を示すことが求められます。
さらに、事業開始後の売上や仕入れ、運営コストなど、資金の流れを明確にすることも重要です。
審査では、事業が継続できるかどうか、また借入金をしっかり返済できるかが判断されるため、論理的で説得力のある資金計画を立てることが成功のカギと言えます。
ポイント④:信用情報に傷を付けない
融資の審査を受ける際には、信用情報に傷を付けないためにも、普段から支払いの遅延や滞納を避けることが重要です。
特に日本政策金融公庫の審査では、申込者の信用情報が細かくチェックされるため、信用に傷がついていると融資の承認が難しくなります。
スムーズに融資を受けるためには、税金の未納や公共料金、ローン、クレジットカードの支払い遅れがないように注意しましょう。
もし過去に支払いの遅延や滞納があった場合、自分の信用情報を確認することが可能です。信用情報を管理する機関には、CICやJICC、KSCといった団体があり、各機関に情報開示を請求することで、自身の信用状況を把握できます。
ポイント⑤:面談に向けて準備を入念にする
飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるポイントの一つとして、面談に向けて準備を入念にすることが挙げられます。
実際に、事業計画書の作成は専門家に依頼することも可能ですが、審査の際の面談には本人が対応する必要があります。
たとえ専門家が完璧に仕上げた計画書であっても、面談で本人がしっかり説明できなければ評価にはつながりません。
そのため、面談当日を想定し、どのような質問にも対応できるように十分な準備をしておくことが重要です。
飲食店が日本政策金融公庫から融資を受ける流れ

飲食店が日本政策金融公庫から融資を受ける流れについては、以下の5つが挙げられます。
- 借入申込書の提出
- 申請書類の準備
- 担当者と面談
- 融資の決定通知が届く
- 指定口座に入金
それぞれの項目について解説していきます。
借入申込書の提出
日本政策金融公庫から融資を受けたい場合は、最寄りの支店へ借入申込書を提出し、正式に申し込みを行いましょう。
借入申込書には、申込者の個人情報に加え、希望する融資額や返済計画など、借入条件に関する詳細を記入します。この申込書は、日本政策金融公庫の公式ウェブサイトからダウンロードして印刷するか、最寄りの支店に訪問して用紙を受け取ることが可能です。
また、日本政策金融公庫ではインターネットからの申し込みにも対応しており、24時間365日いつでも手続きが可能です。
申請書類の準備
日本政策金融公庫の融資を利用するには、申請に必要な書類を揃える必要があります。
必要な書類は、申込者の状況や融資の目的によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
具体的に、申請に必要な書類については、以下のとおりです。
- 創業計画書
- 身分証明書
- 確定申告書
- 決算書
- 登記謄本(法人のみ)
- 許認可証のコピー
また、設備資金の融資を希望する際は、購入予定の設備の見積書が必要になります。
さらに、飲食業など特定の業種では、許認可証の提出が必要になるケースもあります。
担当者と面談
日本政策金融公庫から融資を受ける際には、担当者との面談が必要です。
借入申込書を提出した後、公庫の担当者から電話で連絡が入るため、その際に面談の日程を調整します。
面談では提出した書類の内容に基づいて質問が行われるため、書類に記載した内容をしっかり理解し、口頭でも説明できるように準備しておくことが大切です。
また、面談時の服装や態度も評価の対象になることがあるため、清潔感のある服装で臨むことをおすすめします。
融資の決定通知が届く
日本政策金融公庫の審査に通った場合、融資の決定通知が届きます。
この書類には借用証書が同封されており、融資契約を正式に結ぶために必要となります。
借用証書には、貸主の氏名や入金先の口座情報などを記入し、指定の手続きを済ませたうえで、日本政策金融公庫の担当者へ返送する必要があります。
万が一、記入内容に誤りや不足があると、再提出を求められることがあるため、慎重に記入することをおすすめします。
また、日本政策金融公庫の審査結果は、通過した場合だけでなく否決された場合も通知されるので、融資を申し込んだ方は、担当者からの連絡を待ちましょう。
指定口座に入金
日本政策金融公庫の審査に通った方は、契約手続きが完了すると、借入金が指定した口座に振り込まれます。
入金された際には、借用証書に記載された金額と一致しているかを必ず確認しましょう。
もし振込額に誤差がある場合は、速やかに日本政策金融公庫の担当者へ連絡し、必要な対応について相談することが重要です。
なお、資金の振込時期は、借用証書が日本政策金融公庫に到着してから通常3営業日以内となることが多いです。
万が一、3営業日を過ぎても入金が確認できない場合は、借用証書の記入ミスなどが原因の可能性もあるため、担当者に問い合わせて状況を確認するようにしましょう。
飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるメリット

飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるメリットについては、以下の5つが挙げられます。
- 低金利で融資が受けられる
- 返済期間が長い
- 融資実行まで比較的早い
- 無担保・無保証で融資を受けられる
- 他の金融機関から融資が受けやすくなる
それぞれのメリットについて解説していきます。
低金利で融資が受けられる
日本政策金融公庫では、融資の種類や担保の有無によって年利0.30%〜2.85%と、比較的低めの金利が設定されています。
一般的に、金利が低いとされる銀行融資でも、その利率はおおよそ2%程度となることが多いです。
これに対し、日本政策金融公庫の融資は、銀行と同程度またはそれ以下の金利で利用できる上、審査のハードルも比較的低めであるため、多くの人にとって有利な選択肢となると言えます。
返済期間が長い
日本政策金融公庫の融資には、返済期間を長めに設定できるというメリットがあります。
返済期間を延ばすことで、毎月の返済額を抑え、無理のない返済計画を立てやすくなります。
具体的には、運転資金の返済期間は最長7年、設備資金の場合は最長20年と定められています。
しかし、設備資金については、実際には10年程度での完済を求められるケースが多くみられます。
それでも、7年から10年の返済期間があれば、まとまった金額の融資を受けた場合でも、計画的に返済を進めることができます。
融資実行まで比較的早い
日本政策金融公庫の融資は、信用保証協会を介さずに手続きを進められるため、一般的な民間金融機関を利用する場合と比べて、早く融資を受けられる可能性があります。
実際に、資金の確保に時間がかかりすぎると、事業が安定する前に資金繰りが厳しくなり、経営に支障をきたす可能性があります。
また、融資までの期間が短ければ、経営者自身が手続きを進めるために費やす時間も減り、本業に集中しやすくなります。
このように、日本政策金融公庫は融資実行まで比較的スピーディーに融資を受けられる点は大きなメリットと言えます。
無担保・無保証で融資を受けられる
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を利用すれば、基本的に担保や保証人なしで融資を受けることが可能です。
また、「中小企業経営力強化資金」では、最大2,000万円まで無担保・無保証での資金調達ができます。
このように、日本政策金融公庫の融資制度は、特に創業期の経営者にとって資金を借りやすい点が大きな魅力と言えます。
他の金融機関から融資が受けやすくなる
日本政策金融公庫から融資を受けることで、他の民間の金融機関からの融資が受けやすくなるメリットが挙げられます。
具体的に、日本政策金融公庫からの融資実績があると、銀行や信用金庫などの金融機関もその企業や事業主に対して前向きな姿勢を示しやすくなります。
さらに、日本政策金融公庫からの融資資金を預けている金融機関であれば、より積極的に融資を検討してもらえる可能性が高まります。
日本政策金融公庫が融資を実行したということは、その企業が信頼でき、将来性があると判断された証拠とみなされることが理由として挙げられます。
実際に、日本政策金融公庫の融資を受けた後に、銀行や信用金庫から追加の融資を受けるケースも多く見られます。
飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるデメリット
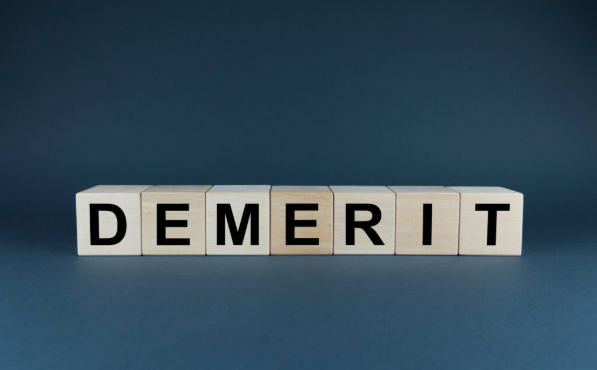
飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるデメリットについては、以下の3つが挙げられます。
- ある程度の自己資金が必要になる
- 提出書類が多い
- 融資の乗り換えは禁止されている
それぞれのデメリットについて解説していきます。
ある程度の自己資金が必要になる
日本政策金融公庫から融資を受ける際には、一定の自己資金が求められます。
2014年の制度改正により、創業融資では希望する融資額の10%程度の自己資金があれば申請可能となりましたが、実際の審査では自己資金が1割しかない場合、承認を得るのは難しく、3割ほどの自己資金を用意しておくことが望ましいのが現状です。
実際に、全額を融資に頼って開業するのは現実的ではありません。
もし自己資金が不足している場合は、家族や知人から資金援助を受けたり、説得力のある事業計画を作成するなど日本政策金融公庫の審査を通過できるような準備が必要になります。
提出書類が多い
日本政策金融公庫の融資を受ける際には、多くの書類を提出しなければならない点がデメリットの一つと言えます。
事業計画書は必須であるのはもちろん、資金繰り計画書や自己資金を証明する書類、賃貸借契約書、履歴事項全部証明書の原本など多岐にわたる書類の提出が求められます。
そのため、経営者は資金調達を進めるにあたり、書類を準備するために相当な時間を費やす必要があります。
融資の乗り換えは禁止されている
日本政策金融公庫の融資を使って民間金融機関からの借入を返済することは認められていません。
過去に多くの企業が公庫の融資を活用して民間の融資を借り換えた結果、民間金融機関の経営が圧迫されたという背景が挙げられます。
しかし、新たな事業資金としての創業融資や、中小企業向けの通常の融資を申し込むケースであれば、問題なく申請することが可能です。
飲食店の開業なら日本政策金融公庫の融資を受けよう!

今回は、飲食店が日本政策金融公庫から融資を受けるポイントを紹介しました。
民間の銀行などでは融資の審査が厳しく、資金を確保するのが難しい場合でも、日本政策金融公庫なら融資を受けられる可能性があるので、資金調達を検討している方は申し込みを視野に入れてみるのをおすすめします。
しかし、日本政策金融公庫の審査は特別に簡単ではなく、一定の基準をクリアする必要があるので、融資を受けるポイントをしっかりと把握することが重要です。
今回の記事を参考にして、日本政策金融公庫の融資を検討してみてください。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は 国税OB・元税務署長 が所属し、 確定申告・相続・会社設立・融資サポート・労務手続きなど 幅広いサービスを提供する税理士法人です。
全国からの 税務・労務相談実績 年間1,000件以上
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から税務調査、相続、会社設立まで幅広く対応可能
- 融資や助成金、補助金の申請など資金調達サポートにも豊富な実績
- 顧問税理士が対応に困った案件も途中からサポートできます
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断