メニュー
会社設立
鳶職が会社を設立するのに費用や資格は?独立するメリット・注意点も解説

読了目安時間:約 7分
建設業の一種である鳶職が独立する際には、どのような準備が必要になるのでしょうか。
鳶職人が独立する場合、個人事業主として事業を始める方法と法人化のどちらかが選べますが、それぞれの特徴や費用などを把握して必要な準備を進めていくことで、スムーズな独立が可能となります。
本記事では、鳶職が独立するメリットや注意点、会社設立に必要な費用や資格について解説します。
キャリアアップのために独立を考えている方はこの記事を参考に、必要な知識を身につけましょう。
目次
そもそも鳶職とは?

建築現場や高所作業現場で働く職業を一般的に「鳶職」と呼びます。
鳶職を雇う建設会社などに就職する際は、資格や経験を求められるケースは少なく、採用後は見習いとしてスタートし、知識や技術を徐々に身につけて一人前の鳶職人となります。
その過程においてはスキルアップのために、さまざまな資格の取得が求められることになるでしょう。
鳶職にはさまざまな種類がある
鳶職と一口に言っても、作業内容などによって以下のようにさまざまな種類があります。
- 町鳶:基礎工事や足場の設置、外構、解体などを行う
- 足場鳶:建設現場で足場の組立てや解体を専門に行う
- 鉄骨鳶:鉄骨を組立て建物の骨組みを作る
- 重量鳶:重量物の運搬や設置、すえつけなどを行う
- 橋梁鳶:橋や高架、ダムなどの鉄骨を扱う
- 機械鳶:リフトや杭打ち機などの機械類を扱う
このように、同じ「鳶職」というくくりでも専門分野があります。
鳶職として独立するなら個人事業主か法人化どちらにすべき?
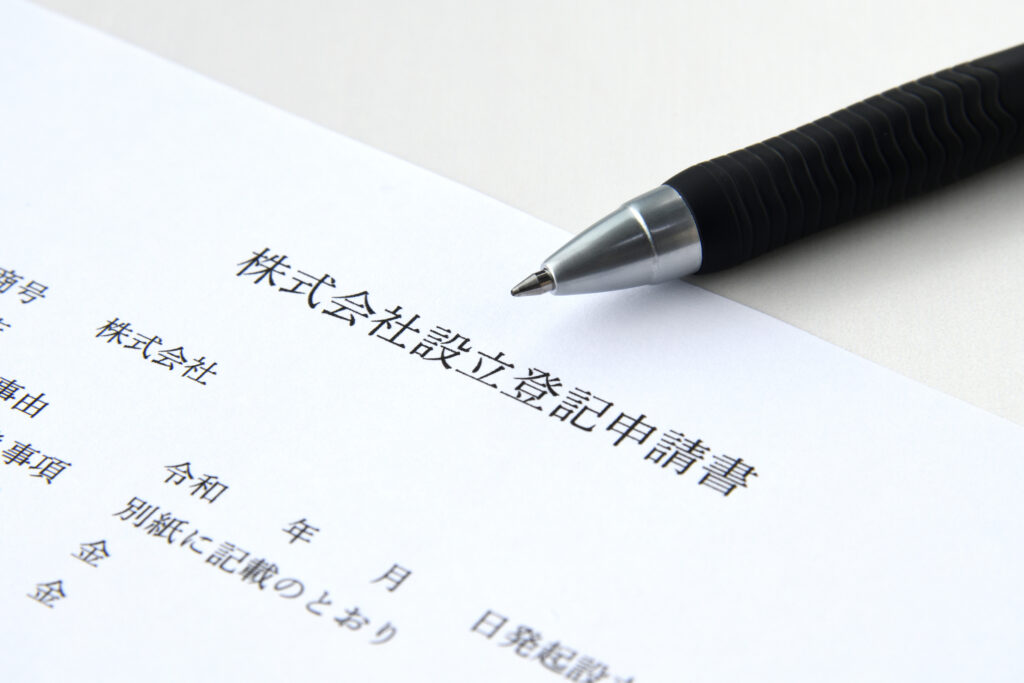
鳶職で独立する場合、基本的には個人事業主、もしくは法人化するか、どちらかを選ぶことになります。
多くのケースでは、はじめは個人事業主として働いて経験を積み、請け負う工事が増え売上が上がってきた段階で、事業を拡大するために会社を設立するケースが多いです。
ここからは、鳶職の独立方法をそれぞれご紹介します。
個人事業主
鳶職として個人事業主で独立する場合、税務署に開業届を提出する必要がありますが、独立のための手続きや費用が少なく、すぐに始められるのがメリットです。
また、請負契約で働くため、利益は個人事業主の所得となります。
また、会社を設立するのと比べて自由度が高いのが特徴で、自分の意思で仕事を選びたい、自由にスケジュールを管理したい、という方に向いています。
法人化
鳶職として会社を設立する場合、以下のようにさまざまな手続きが必要で、開業資金も用意しなければなりません。
- 会社の事業内容を決める
- 会社の実印を作成する
- 定款を作成し公証人の認証を受ける
- 資本金を払い込む
- 法務局に登記申請をする
- 会社設立後、年金や社会保険の手続きをする
法人化すると個人事業主より手続きが増えるものの、社会的信用度が向上し、大企業や行政の仕事を請け負いやすくなる傾向にあります。また、法人は有限責任であるため、原則として事業の負債が個人の責任とならないという点もメリットです。
鳶職が独立するとさまざまなメリットがある

鳶職は独立するメリットが大きいと言われており、独立を目指す職人が多いです。
具体的には以下のメリットがあります。
- 高年収を狙える
- 若い段階で独立できる
- 今後も需要のある業界である
それぞれ詳しく見ていきましょう。
高年収を狙える
鳶職の平均年収は約400万円前後と言われており、独立後の年収は請け負う仕事の内容や規模により異なりますが、成功すれば約500〜600万円以上を得るケースもあります。
会社を設立し、従業員を雇って事業規模を大きくすれば請け負える仕事の種類や数も増える可能性が高く、工夫や努力次第で年収アップが狙えるでしょう。
鳶職として独立し、会社を設立した方の中には年収1,000万円を超える人もいます。
年収アップのためには、技術力や経験の向上はもちろん、資格取得や外部研修の受講なども必要ですが、独立後の高収入が期待できる職業だといえます。
若い段階で独立できる
鳶職は比較的若い段階で独立しやすい業種といわれ、早いうちから独立の準備を進めると早ければ20代でも鳶職として独立できるでしょう。
未経験からスタートしたとしても、実務をこなしていき、数年経験を積めば、独立してある程度稼ぐことができる場合が多いです。
また、鳶職は技術のほかに体力も必要な仕事であるため、若いうちは体力的な面で現場作業に適している場合が多く、一定の優位性があると言えるでしょう。
今後も需要のある業界である
少子高齢化に伴い、働く人の数が年々減少傾向にあるほか、鳶職という仕事自体、「きつい」「危険」というイメージから若い人が仕事として選ぶ人が少なくなっている現状です。さらにベテランの鳶職人は高齢により引退する人も増え、この業界は人手不足に陥っています。
そのため、一定の需要は今後も見込まれると予想されます。ただし、経済状況などによっては変動の可能性もあるため慎重な計画が必要です。
鳶職が独立する際の注意点

足場鳶は若いうちから独立をして、親方として活躍できる業界であり、先程ご紹介した通り独立をするメリットも多くありますが、立場が異なるために気をつけなければならない点もあります。
ここでは、鳶職が独立する際の注意点をご紹介しますので、確認しておきましょう。
体調管理に気を付ける
鳶職は体が資本と言われ、怪我や体調不良によって仕事ができない状態が続けば、仕事に支障をきたす可能性もあります。
また、鳶職として現場で活躍できるのは40〜50代くらいまでが目安といわれていることを念頭に置いておく必要があるでしょう。
現場作業員として活躍するために体調管理を徹底するとともに、体を使った作業から身を引いたあとは、他の作業員をまとめたり、若い鳶職人に教えたりと、教育・指導する立場となり、スムーズに事業を回せる体制を整えておくのが有効です。
コミュニケーション能力を求められる
独立して、いち従業員から労働者を指揮・監督する立場になる場合、従業員の健康や安全を確保しながら的確な指示を出すポジションであるため、コミュニケーション能力を問われます。
一人親方であっても、現場で一人で作業するケースは少ないため、スムーズに仕事を行うためにも身につけておく必要がある能力です。
さらに、仕事を獲得するためには営業力や関連会社との信頼関係を構築するための対話力なども求められます。
鳶職以外のスキルも身につける
独立する場合、鳶職として必要なスキルだけでなく、以下の知識やスキルも身につける必要があります。
- 仕事のスケジュール調整
- 営業活動
- 経理業務
- 問い合わせ対応 など
特に、正しく確定申告を行うためには日々の会計業務が欠かせません。
鳶職としての業務に追われる場合は、税理士などの専門家に依頼するなど対策をとりましょう。
鳶職の会社設立にはいくらかかる?資金調達方法も紹介

鳶職人が独立して会社を設立する場合に心配になるのは会社設立にかかる費用ではないでしょうか。
ここからは、鳶職の法人化に必要な費用や資金調達方法について説明していきます。
鳶職の法人化に必要な費用
鳶職の法人化には法定費用などを納める必要があり、株式会社の場合は20万円前後、合同会社の場合6万円程度の費用が最低でも発生します。
そのほか、建設業においては以下の費用も用意する必要があるでしょう。
- 建築資材などの材料費
- 作業員などの人件費
- 業者に依頼するための外注費
- 足場の確保や事務所などの設置費用
事業が軌道に乗るまでに数ヶ月かかると仮定した場合、目安として500〜1,000万円程度用意しておくと安心です。
建設業で使える資金調達方法
鳶職人が法人化する際はさまざまな費用がかかるため、考えなければならないのは資金調達方法です。
建設業で利用できる資金調達方法としては、以下が考えられます。
- 新創業融資制度
- 信用保証協会付融資
- プロパー融資
- 自治体の補助金や助成金
日本政策金融公庫では新しく事業を始める人、事業を始めてから税務申告を2期終わっていない人を対象とした融資制度があり、厳格な審査が行われますが、無担保・無保証人で借入ができるなどのメリットがあります。
参考:日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金
また、銀行と借主の間に信用保証協会が入り、融資の保証を行う信用保証付融資や、地方自治体の補助金・助成金を活用するのも良いでしょう。
資金調達に悩んだら専門家に相談するのがおすすめ
「どの方法で資金調達すれば良いかわからない」「融資を受けたいけれど審査に通るか不安」という方は、資金調達のプロである融資コンサルタントや税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けると良いでしょう。
依頼すると報酬を支払わなければなりませんが、実績が豊富な専門家に相談することで自社に合った資金調達方法が分かり、必要な準備や対策ができ、融資を受けやすくなります。
また、鳶職の法人化においては資金調達に限らず税金の申告や納付など、専門的な知識が必要な場面が多くあるため、自身で全て行うのが困難な場合には税理士や社会保険労務士などの専門家に相談するのがおすすめです。
鳶職が会社設立するのに必要なスキルや資格
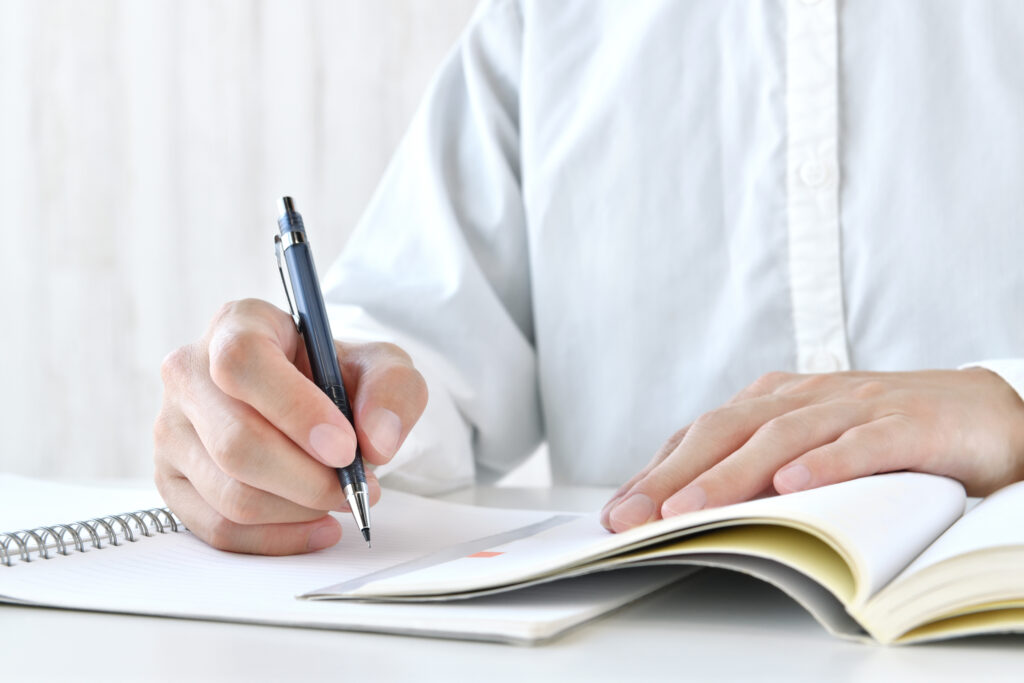
鳶職として独立するために、特別な資格が必ずしも必要なわけではありませんが、持っていると仕事上有利な資格やスキルは多くあります。
建設現場においては、法律でも「危険が伴う作業には有資格者を従事させなければならない」と定められており、資格を獲得することでより高度な作業が行え、高収入を獲得しやすくなるのです。
資格の中には講習を受けるだけで獲得できる免許から、国家試験を受ける必要がある資格など、さまざまあります。
ここからは、鳶職が会社を設立する際に役立つ資格やスキルをご紹介します。
とび技能士
とび技能士は、作業順序の考案や、足場の組み立てや解体、掘削、土止めや地業など、鳶に関するスキルを認定する国家資格で、この資格を持っていればとび職の仕事全般に関する技能が正式に認められるといえます。
とび技能士は1〜3級まで分かれており、とび職としてのレベルを証明するのに役立ちます。
最も難易度が高いとび技能士1級は、受験資格を得るまでに実務経験を積む必要があるため、これを取得すれば、とび職として独立する際にも自身の実力を証明でき、より多くの仕事を請け負うことができるでしょう。
参考:厚生労働省|とび技能士
玉掛け技能講習
鳶の仕事でまず初めに取得する資格とされるのが「玉掛け」です。
玉掛けは、クレーンなどのフックに物を掛けたり外したりする作業であり、建設現場や工場での作業で、資材や機械などの重い荷物をクレーンで持ち上げて運搬する際に必要になります。
適切な掛け方をしなければ荷物が落下し、荷物が破損したり従業員が負傷したりする恐れがあるため、正しい方法で玉掛けができるよう講習を受ける必要があるのです。
1t以上の荷重を扱う作業では、労働安全衛生法に基づいて資格取得が義務付けられており、玉掛け技能講習を修了するためには学科・実技それぞれの講習後、試験に合格する必要があります。
参考:厚生労働省|玉掛け技能講習規程(◆昭和47年09月30日労働省告示第119号)
足場の組立て等作業主任者
足場の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた国家資格であり、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した後に取得できる資格です。
労働安全衛生法では、つり足場、張出し足場または高さが5m以上の足場の組立て、解体または変更の作業を行う場合には、有資格者を現場の作業主任者として専任し、作業員の指揮をさせることが義務付けられています。
もし有資格者が所属していない状態で労働災害が発生すると、労働災害保険が適用されない可能性が高いため、会社を設立する場合にはあった方が良い資格といえます。
足場の組立て等作業主任者の資格取得のためには、満21歳以上で足場作業3年以上であり、「足場の組立て等作業主任者技能講習」を受講後、修了試験に合格しなければなりません。
参考:厚生労働省|足場の組立て等作業主任者技能講習規程(◆昭和47年09月30日労働省告示第109号)
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
前述した足場の資格と同様に必要になるのが、鉄骨の資格です。
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた国家資格であり、労働災害の防止、安全面を考慮して、高さ5m以上の鉄骨建築物組立てや解体の際には、この資格を持った者を配置しなければならないと法律で定められています。
この資格試験を受けるためには、鉄骨に関する作業経験が3年以上必要です。資格取得には技能講習を受講し、学科試験に合格することが求められ、鉄骨組立て等の作業に関する専門知識や技能が問われます。
参考:建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程
資格を取得し、資金調達を成功させて鳶職の法人化を目指そう

鳶職は独立がしやすい業種とされており、鳶職人が経験値を上げてから独立すると、高収入が狙えるなどさまざまなメリットがあります。
しかし、法人化にあたっては設立に必要な費用を用意したり、資格を取得したりと、さまざまな準備が必要です。
鳶職の法人化を目指している場合はこの記事を参考に、職人としての経験を積みながら会社設立に必要な知識を身につけ、開業を目指しましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。










