メニュー
会社設立
せどり業でマイクロ法人を設立するタイミングとは?メリット・デメリットや設立する流れも解説

読了目安時間:約 8分
マイクロ法人とは、従業員を雇わずに会社の代表者が1人で事業を行う会社です。
個人事業主がマイクロ法人を設立することで、所得の分散や社会保険制度の選択肢が広がり、結果として税金や保険料の負担を軽減できる可能性があります。ただし、マイクロ法人を設立するタイミングも重要な要素になります。
本記事では、せどり業でマイクロ法人を設立するタイミングを紹介します。
他にも「せどり業でマイクロ法人を設立するメリット・デメリット」や「せどり業でマイクロ法人を設立する流れ」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、せどり業でマイクロ法人を設立してみてください。
目次
せどり業でマイクロ法人を設立するタイミング

せどり業でマイクロ法人を設立するタイミングについては、以下の3つが挙げられます。
- 課税所得が800万円を超えた
- 課税売上高が1,000万円を超えた
- 事業を拡大したいとき
それぞれのタイミングについて解説していきます。
課税所得が800万円を超えた
せどりや転売ビジネスを法人として運営するかどうかを考える際には、課税所得が800万円を超えているかが一つの判断基準になります。
課税所得が800万円を超えると、個人として納める所得税の税率よりも法人に適用される法人税率の方が低くなる傾向があります。
例えば、個人事業主として課税所得が800万円から1800万円の範囲にある場合、所得税率はおおよそ22~33%になります。
一方、法人の場合、同じような利益であっても適用される法人税率は最大でも23.2%ほどとされており、税負担が軽くなる可能性があります。
このように、一定以上の収入が見込める段階で法人化を検討するのが、一般的には得策だと言われています。
参考:国税庁|法人税の税率
課税売上高が1,000万円を超えた
課税売上高が安定的に1,000万円を超えているかどうかは、消費税の課税事業者に該当するかどうかの重要な判断材料となります。
原則として、基準期間(2期前)における課税売上高が1,000万円を超えると、当該基準期間から数えて2期後の事業年度に消費税の納税義務が発生します。
たとえば2025年に課税売上高が1,000万円を超えていても、2026年中に資本金1,000万円未満で法人を設立した場合、設立1期目・2期目は一定の要件を満たせば免税事業者として扱われる可能性があります。
ただし、インボイス制度も導入されたことに加え、このあたりの判断は専門的な知識を必要とするため、事前に税理士に相談することをおすすめします。
事業を拡大したいとき
せどりを通じてビジネスを拡大したいと考えている場合も、せどり業でマイクロ法人を設立するタイミングと言えます。
法人として事業を運営することで、個人事業主よりも外部からの信頼を得やすくなり、金融機関による融資審査や、求職者に対する企業の印象にも大きく影響します。
例えば、社会保険にしっかり加入していることは、働く環境を整えている証拠とされ、採用活動でもプラスに働きます。
また、融資を受ける際にも、「しっかりと事業に取り組んでいる」と認識される可能性があります。
このように、法人化すればすぐに社会的な信頼が得られるわけではありませんが、長期的に見れば、個人で事業を行うよりも信頼性が高まりやすいというメリットがあります。
せどり業でマイクロ法人を設立するメリット
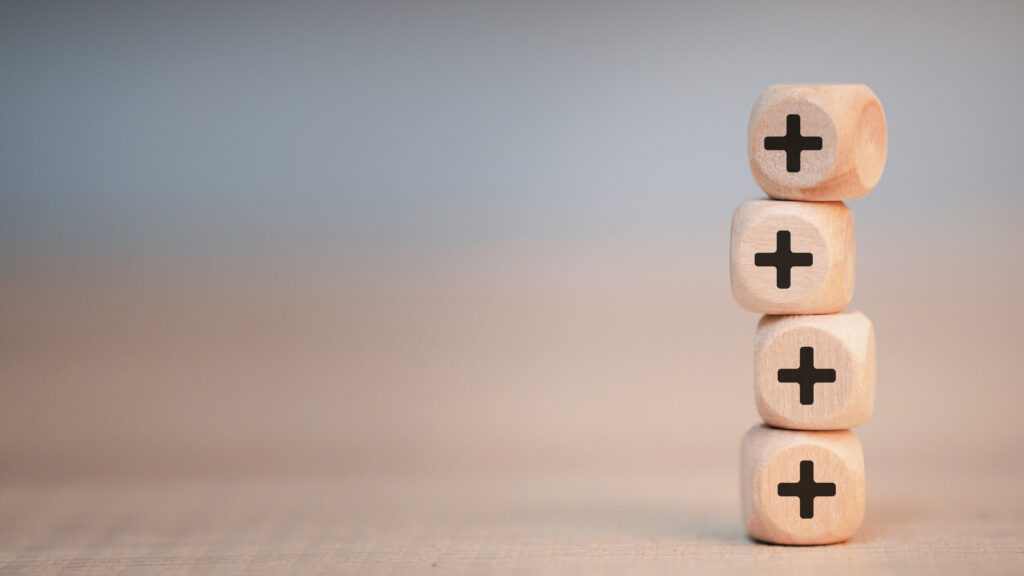
せどり業でマイクロ法人を設立するメリットについては、以下の4つが挙げられます。
- 経費にできる範囲が広がる
- 税金を抑えられる
- 社会的信用が向上する
- 消費税の免税事業者になれる
それぞれのメリットについて解説していきます。
経費にできる範囲が広がる
法人の方が個人事業主に比べて、経費として認められる支出の範囲が広い傾向にあります。
法人化することで個人事業主では計上できなかった、生命保険や出張手当なども経費として計上できるようになります。
しかし、名義が法人であっても、実際には個人が私的に使用するための支出である場合には、経費として認められないので注意が必要です。
税金を抑えられる
マイクロ法人を設立することによって得られるメリットの一つは、税金や社会保険に関する支出を抑えられる点にあります。
例えば、個人事業で得る収益とは別の収入源をマイクロ法人名義で計上し、その法人から年額162万5千円以内の役員報酬を受け取る形にすれば、給与所得控除として55万円が適用されます。
この控除によって、課税対象となる給与所得が減少するため、所得税や住民税の負担も軽減されるという仕組みです。
さらに、従来は個人事業主として加入していた国民健康保険や国民年金を、マイクロ法人の社員として健康保険や厚生年金に切り替えることになります。
その際、役員報酬を可能な限り低く設定することで、社会保険料の負担も抑えやすくなります。
このように、法人化することで全体的な支出を減らし、手取りを効率よく確保することが可能になります。
参考:国税庁|給与所得控除
社会的信用が向上する
個人事業主と法人を比較すると、外部からの信頼度においては、一般的に法人の方が優位になります。
実際に、法人を立ち上げる場合、法務局への登記が必要であり、その過程で設立日や所在地などの情報が登記簿に正式に記載されるので、会社が法的に認められた存在であることを示す証となります。
一方、個人事業主は税務署に開業届を出す必要はありますが、法人のように公的な登記簿で開業が証明されるわけではありません。
また、法人を設立する際には、ある程度の資本金を用意することが求められ、資本金の存在自体が経営基盤の強さを示す一つの指標となるため、企業としての信頼性が高いと判断される可能性があります。
消費税の免税事業者になれる
マイクロ法人を立ち上げるメリットの一つとして、消費税の支払い義務が免除される「免税事業者」になる可能性があることが挙げられます。
免税事業者とは、基準期間(2年前)における課税売上高が1,000万円未満であり消費税の納税義務が免除される事業者を指します。
しかし、法人設立が節税だけを目的として行われた場合には、税務署から租税回避行為と見なされ、問題視される可能性があるので注意が必要です。
また、インボイス制度の影響で以前よりも消費税の免税事業者になることが難しくなっている側面もあるため、あらかじめ制度の内容や影響をしっかりと把握し、慎重に判断するようにしましょう。
せどり業でマイクロ法人を設立するデメリット
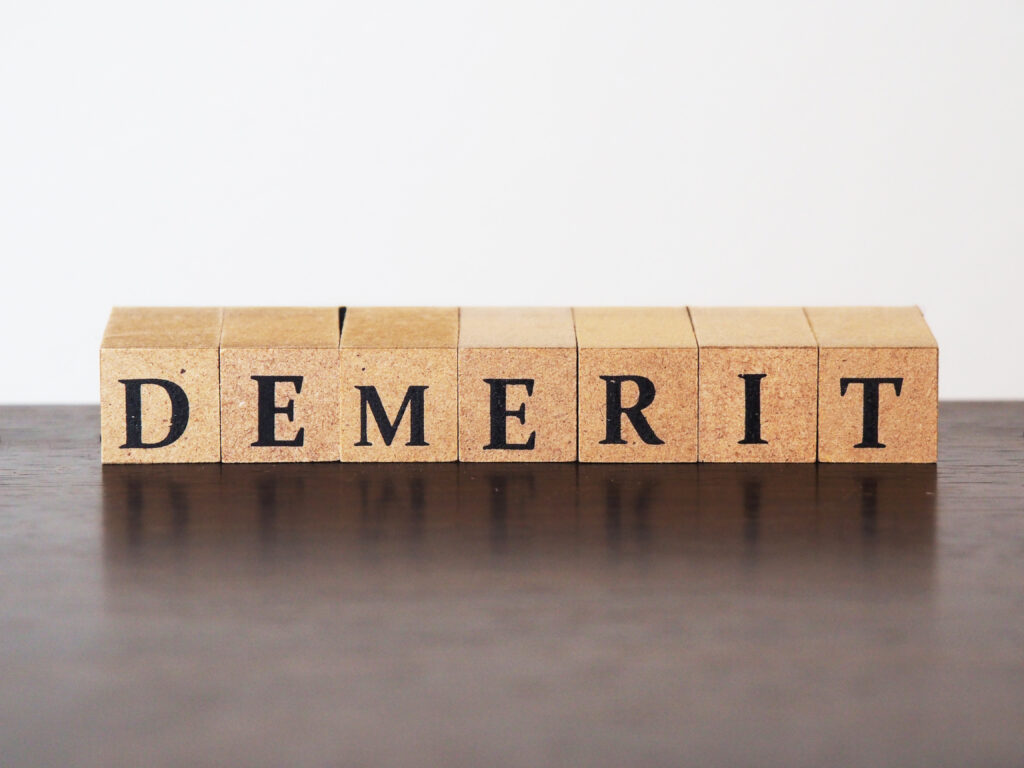
せどり業でマイクロ法人を設立するデメリットについては、以下の3つが挙げられます。
- 設立費用や維持費用がかかる
- 経理業務が複雑化する
- 赤字でも法人住民税の支払いが必要
それぞれのデメリットについて解説していきます。
設立費用や維持費用がかかる
マイクロ法人を立ち上げる際には、設立費用や維持費用がかかってしまうデメリットが挙げられます。
マイクロ法人を立ち上げるプロセスでは、まず定款を作成し、公証役場で認証を受けた上で、法人として登記を行う必要があり、登録免許税や印紙代といった費用が伴います。
また、自宅とは別に事務所スペースやバーチャルオフィスを契約する場合や、電話応対を外部に委託するなどの追加サービスを利用することで、出費がかさむこともあります。
経理業務が複雑化する
マイクロ法人を設立する際に最初に直面するマイナス面として、手続きの複雑さが挙げられます。
法人化した場合の決算申告が新たに必要になり、そのためには貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書といった会計書類に加え、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書などの多くの資料も準備する必要があります。
こうした書類の作成は専門知識が求められるため、個人で対応するのは難しく、多くの場合、税理士などの専門家に依頼することが多いです。
赤字でも法人住民税の支払いが必要
マイクロ法人を立ち上げた場合、たとえ利益が出ていなくても法人住民税を納める必要があります。
法人住民税は「都道府県民税」と「市町村民税」の2種類から構成されており、均等割と呼ばれる課税項目によって、法人の所在地でその額が決まります。
均等割とは、会社の資本金の規模や従業員数などに応じて、一定の金額を各法人に等しく負担させる制度です。
この均等割の金額は、地域ごとに差があるものの一般的には年間で数万円から十数万円程度とされています。
このように、マイクロ法人を設立すると、会社が赤字であっても支払い義務が生じるので、あらかじめ注意が必要です。
参考:総務省|法人住民税
せどり業でマイクロ法人を設立する流れ

せどり業でマイクロ法人を設立する流れについては、以下のとおりです。
- 会社概要を決める
- 実印作成
- 定款作成と認証
- 資本金の準備
- 登記申請書作成と手続き
- 行政機関への手続き
それぞれの項目について解説していきます。
会社概要を決める
マイクロ法人を立ち上げるには、まず会社概要を決める必要があります。
具体的には、次のような内容を事前に決定するようにしましょう。
- 事業内容(目的)
- 会社名(商号)
- 本社の住所
- 法人形態
- 資本金の額
上記の情報は、会社の「定款」と呼ばれる文書に記載する必要があるので、設立手続きを進める前にしっかりと検討しておくことが重要です。
実印作成
マイクロ法人を設立する際には、法人名義の実印と、代表者本人の実印の両方を準備する必要があります。
法人の実印は、会社の登記手続きや各種契約の際に正式な印鑑として使用されるため、重要なアイテムと言えます。
法人用実印は通常18mm以上のサイズが推奨され、個人の実印であれば12mm以上が適しています。
彫りの深さは、浅いものよりも深く彫られているほうが、印影がくっきりしていて実用性が高いとされています。
また、木材やプラスチック製のものは比較的安価ですが、長く使うことを考えると、黒水牛や象牙などの高級素材がおすすめです。
定款作成と認証
定款は、会社の目的、名称(商号)、所在地、資本金、経営陣の構成など、組織運営に欠かせない事項が網羅されています。
法人登記の申請時には、この定款を法務局に提出する必要があり、内容の正確さが求められます。
また、定款は法律に関わる専門知識を要するため、自分で一から作成するのは簡単ではありません。税理士や司法書士などのプロフェッショナルに相談・依頼することをおすすめします。
定款認証には手数料が発生し、最低でも5万円程度の費用がかかるので、あらかじめ注意が必要です。
資本金の準備
マイクロ法人を運営するためには、資本金が必要になります。
資本金は法人設立を希望する発起人が自ら資金を出して用意するのが一般的です。
金額に関しては法律上1円以上であれば設定可能で特に上限も設けられていませんが、実際のビジネスの規模や運営方針を踏まえて、無理のない範囲で適切な金額を定めることが重要です。
登記申請書作成と手続き
登記申請書は、マイクロ法人を設立する際に法務局へ提出する必要がある正式な書類です。
書類には、会社の基本的な情報に加えて、発起人の氏名や住所などの詳細を記載します。
書類の作成方法については、法務局のWebサイトなどで具体的な記載例が公開されており、誰でも確認することができます。
登記申請書が完成したら、その他の必要書類と共に法務局に提出します。
具体的に、提出が必要な書類としては、以下が含まれます。
- 登録免許税分の収入印紙を貼付した納付台紙
- 定款のコピー
- 発起人による設立に関する決議書
- 設立時の取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明
- 資本金の払込が完了していることを示す書面
- 会社の印鑑届出書
- 登記内容を記載した書類(電子データでの提出も可能)
これらの書類は、法務局に直接持参か郵送、もしくはオンラインで提出することが可能です。
しかし、必要な知識が不足したまま手続きを進めてしまうと、書類の不備によって処理が遅れる可能性もあります。
そのようなリスクを避けるため、税理士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
申請が完了すると、法務局による書類の審査が行われ、通常は10日前後で結果が出ます。
審査に問題がなければ、登記が正式に完了し、「登記完了通知書」が発行されることで、マイクロ法人の設立手続きがすべて完了となります。
参考:法務局|商業・法人登記申請手続
行政機関への手続き
マイクロ法人を設立した後は、行政機関に対して必要な手続きを行う必要があります。
主に以下のような申請や届出が求められます。
- 法人設立に関する届出を税務署へ提出
- 税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出
- 県の税務事務所に対して法人設立の届出
- 法人所在地の市区町村にも設立の通知が必要
- 社会保険の手続きとして管轄の年金事務所へ加入届を提出
- 労働保険に関して、労働基準監督署への届出が必要
これらの手続きには、提出期限や必要な書類、場合によっては手数料が定められています。
それぞれの機関で対応が異なることもあるため、事前にしっかりと確認し、漏れのないよう進めるようにしましょう。
せどり業でマイクロ法人を設立する際の注意点

せどり業でマイクロ法人を設立する際の注意点については、以下の2つが挙げられます。
- 脱税行為と判断されないようにする
- ペーパーカンパニーと見られないように対策する
それぞれの注意点について解説していきます。
脱税行為と判断されないようにする
マイクロ法人を設立する際には、税務署から脱税の疑いを持たれないよう、十分に配慮することが重要です。
特に、すでに個人事業を営んでいる人が新たにマイクロ法人を立ち上げる場合には、両者の事業内容をしっかりと分けておくことが求められます。
万が一、内容が似通っていると、一つの事業を意図的に二つに分けて所得を分散させていると疑われる可能性があるので注意が必要です。
ペーパーカンパニーと見られないように対策する
ペーパーカンパニーとは、法人としての登記は済んでいるものの、実際には事業活動を行っていない企業のことを指します。
実際に、税負担や社会保険料の軽減、あるいはビジネス上の信用力を高めるために設立される場合があります。
しかし、こうした企業は税務署や社会保険機関といった行政機関から厳重にチェックされやすくなっています。
ペーパーカンパニーと見なされた場合のリスクとして、税務調査を受ける可能性が高まり、過去の未納分の税金や保険料を追加で徴収される恐れがあります。
また、社会的信用を失い、取引先との関係に悪影響を及ぼすリスクも挙げられます。
ペーパーカンパニーと疑われないための実務ポイントとしては、実際に事業を行い、売上や利益などの成果を出したり、決算書や業務報告書など活動の記録を残し、第三者に説明できるようにすることが挙げられます。
これらの対策を講じることで、形式上だけの企業と見なされるリスクを減らし、社会的信頼を維持することにつながります。
マイクロ法人を設立してビジネスチャンスを創出しよう!

今回は、せどり業におけるマイクロ法人の設立について紹介しました。
マイクロ法人を活用することで、節税効果だけでなく、新たなビジネスを展開するための土台としても有効です。
小規模ながら法人という枠組みを持つことで、フリーランスの方々が抱える収入面での不安や将来への心配を軽減する手段となります。
特に、不安定な収入に悩む個人事業主にとっては、法人化が新しい収益機会を広げるきっかけにすることが可能です。
今回の記事を参考にして、マイクロ法人を設立してビジネスチャンスを創出してみてください。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。










