メニュー
創業融資
建設業で開業資金が必要な目安とは?調達する方法やポイントについても徹底解説

読了目安時間:約 7分
建設業で開業を目指す際には、どのくらいの資金が必要か把握しておくことで準備を円滑に進めることが可能になります。
本記事では、建設業で開業資金が必要な目安について紹介します。
他にも「建設業で開業資金を調達する方法」や「建設業で開業資金を調達するポイント」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、建設業で開業資金が必要な目安について理解を深めてみてください。
目次
建設業で開業資金が必要な目安とは?

建設業で開業資金が必要な目安については、以下2つのケースが挙げられます。
- 個人事業主として開業するケース
- 法人を設立するケース
それぞれのケースについて解説していきます。
個人事業主として開業するケース
個人事業主としての開業にあたって、手続きを自分で対応すれば開業届の提出にかかわる費用はほとんどかからないと言っていいでしょう。
しかし、事業をスムーズにスタートさせるには、少なくとも3ヶ月分の運転資金を用意しておくのが安心とされています。
具体的には、以下の日常的な出費が挙げられます。
- 商品や資材の仕入れ費用
- 従業員への給与
- 業務を外部に委託する場合の支払い
- 光熱費や通信費など
これらを合計すると、場合によっては数百万円が必要になることもあります。
特に、建設業のように仕事の受注から報酬の支払いまで時間がかかる業種では、最初の売上が実際に入ってくるまでにタイムラグが生じるケースが多いため、あらかじめ資金を準備しておくことが重要です。
また、必要な資金の額は業種や事業内容、立地条件や使用する設備によっても大きくことなるので、事業の規模を見極めたうえで、現実的な資金計画を立てるようにしましょう。
法人を設立するケース
法人の設立に関わる初期費用や資本金、最低でも3か月分の運転資金を事前に準備しておくことが推奨されます。
一般的に想定される費用の目安については、以下のとおりです。
- 設立関連手続きの費用:10万〜25万円程度
- 資本金:最低1円~(ただし、建設業許可取得には一定の資本金が必要)
- 運転資金(約3ヶ月分):事業内容によって異なるが数百万円程度
まず、法人として会社を設立する場合、事務所の賃貸費用やオフィス設備の購入に加え、定款の作成・認証や登記手続きなどの法的手続きが必要になります。
また、株式会社を設立するか合同会社にするかによって、かかる費用は異なります。
さらに、個人事業主と同様に、開業直後には仕入れ費用や人件費、外注先への支払いなど多岐にわたる出費が予想されます。
売上が実際に入金されるまでにはタイムラグがあることも多く、特に人件費については従業員の数に応じて3か月分を確保しておくようにしましょう。
参考:法務局|商業・法人登記申請手続
建設業で開業資金を調達する方法
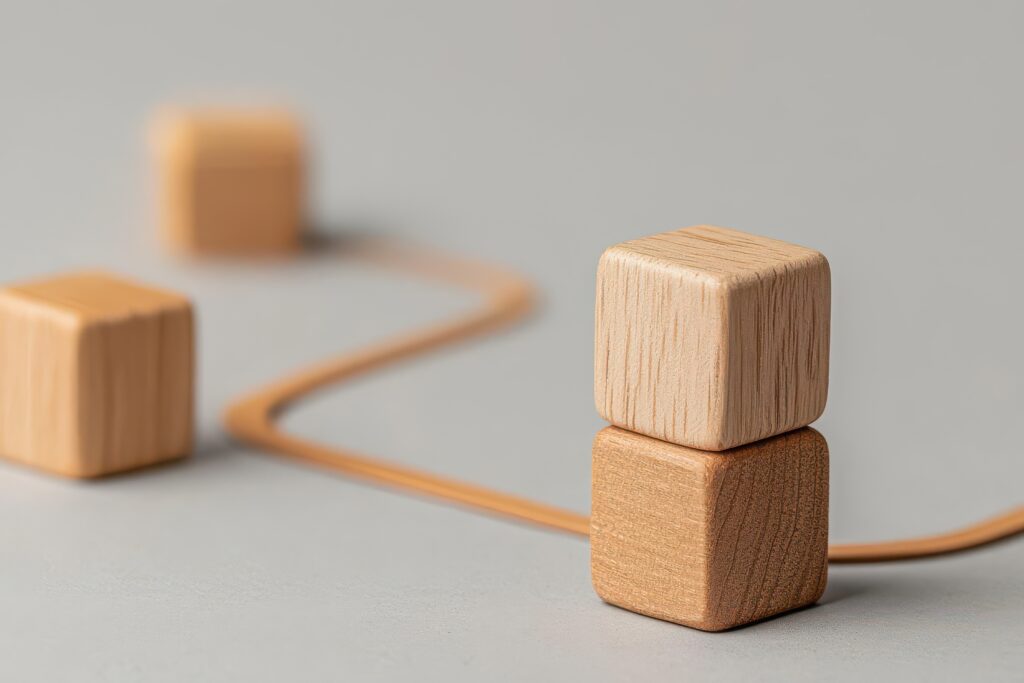
建設業で開業資金を調達する方法については、以下の6つが挙げられます。
- 日本政策金融公庫
- 制度融資
- 補助金や助成金
- 銀行融資
- 信用保証協会の保証付き融資
- 出来高融資制度
それぞれの方法について解説していきます。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫の融資制度は、国が運営している中小企業や個人事業主向けの公的融資制度で、一般的な民間銀行よりも低金利で資金を借りられるという特徴があります。
特に、「新規開業・スタートアップ支援資金」では、担保や保証人を必要とせず、最大7,200万円までの融資を受けることができます。
融資を受けるために必要な自己資金の要件はありませんが、少なからず自己資金がある方が融資は通りやすくなるでしょう。
そのため、事前にある程度の自己資金を準備しておくことが重要です。また、事業計画書を作りこむなど審査に通るための入念な準備が欠かせません。
参考:日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金
制度融資
制度融資とは、自治体が小規模事業者向けに金融機関、信用保証協会と連携して提供している融資制度です。
申し込んでから自治体の審査を通れば、金融機関に対して紹介状が発行されます。
各地方自治体が独自に実施しているため、自治体によって対象者・利用条件が異なるケースも多いです。
そのため、利用を検討している場合は、事前に自治体のホームページで制度融資について確認しておくことをおすすめします。
補助金や助成金
事業者の活動を後押しするために、さまざまな助成制度が整備されています。
例えば、起業や事業継承を支援する制度や小規模事業者の生産性向上を目指す支援金などが挙げられます。
また、助成金・補助金は、国や自治体が民間の事業活動を資金面で支える制度であり、条件を満たすことで申請できます。
融資とは異なり原則として返済の必要がないため、活用できる場合は積極的に検討すべきと言えます。
さらに、地域ごとの自治体でも独自の補助制度を設けている場合があり、自分の所在地に応じた情報収集も重要です。
銀行融資
銀行融資は、企業の信用度や規模に応じて多彩な融資メニューを用意しており、建設会社は日々の運転資金の確保から大型の設備導入まで、さまざまな資金ニーズに対応することが可能です。
特に、工事着工前に必要となる前払金や資材購入費などに対して利用されているケースも多くみられます。
銀行融資の魅力の一つは、返済期間や借入額を事業内容に合わせて柔軟に設定できる点です。
しかし、融資を受けるには厳密な審査が行われるため、建設業においては会社の経営状態や過去の業績が重視される傾向にあります。
融資を円滑に進めるためには、内容の整った事業計画書を作成し、提出することが不可欠です。
さらに、日頃から金融機関との信頼関係を築いておくことが審査を通る上で重要と言えます。
信用保証協会の保証付き融資
信用保証協会の保証付き融資は、信用保証協会が借入者に代わって金融機関に保証を行うため、借入希望者が十分な担保を持っていなかったとしても融資を受けやすい仕組みになっています。
特に、中小規模の企業や個人事業を営む方々にとっては、比較的利用しやすい制度であり、資金調達のハードルを下げてくれる点が魅力と言えます。
また、保証があることで金融機関側の貸し倒れリスクが減るため、より良い条件で資金を借りられる可能性もあります。
しかし、保証を受けるには保証料がかかるため、トータルのコストを事前にしっかりと確認し、資金計画を立てることが必要です。
制度をスムーズに利用するためには、必要な資料をあらかじめ準備し計画的に手続きを進めることが重要となります。
出来高融資制度
出来高融資制度とは、主に公共工事を請け負う企業に向けて複数の金融機関や団体が提供している制度です。
工事の進行状況に合わせて段階的に資金を確保することができるので、資金繰りの面で大きなメリットがあります。
特に、長期にわたる大規模プロジェクトを手がける企業にとっては、初期の資金負担を和らげる有効な資金調達手段となります。
工事の進捗に応じて資金が支払われるので、必要以上の借入れを避けることができ、無駄な金利負担のリスクも抑えられます。
さらに、金融機関への説明がしやすくなることから、審査の通過率向上も見込めるメリットも挙げられます。
しかし、制度を活用するには、契約書や出来高の報告資料などの提出が必須となるため、事前に整った準備が求められます。
参考:(一財)建設業振興基金|出来高融資制度|資金繰り対策
建設業で開業資金を調達するポイント

建設業で開業資金を調達するポイントについては、以下の4つが挙げられます。
- 資金調達先を複数確保しておく
- 自己資金を準備する
- 事業計画を立てる
- 資金調達先との関係性を深めておく
それぞれのポイントについて解説していきます。
資金調達先を複数確保しておく
事業を行うにあたり、特定の金融機関に依存することは大きなリスクとなるため、資金調達先を複数確保しておくようにしましょう。
融資の審査や条件は、経済状況や政策によって日々変化するので、複数の資金源を確保しておくことで、突発的な資金ニーズにも機敏に対応できる体制を整えることが可能です。
また、資金戦略を練る際には、目先の資金ニーズだけでなく、中長期的な経営の方向性を踏まえたうえで判断することが求められます。
資金調達にかかるコストや返済の条件を丁寧に比較し、自社にとって最も適切な手段を組み合わせて活用することで、資金面のリスクを大幅に軽減することにつながります。
自己資金を準備する
創業時の融資を受ける際には、どの程度の自己資金を用意しているかが審査において重要なポイントになります。
自己資金が豊富であればあるほど、事業に対する真剣な姿勢や準備の度合いが高く評価される傾向にあります。
逆に、自己資金が少ない場合は、資金計画に不安があるとみなされ、融資を受けるのが難しくなることもあります。
一般的には、起業資金の3分の1以上を自分で準備しておくと、審査がスムーズに進むケースが多いとされています。
事業計画を立てる
建設業で開業資金を調達するポイントとして、しっかりとした事業計画を練ることが重要です。
金融機関は、その事業が将来的に利益を生み出せるかどうかを慎重に見極めるため、提出された事業内容を詳細に精査しています。
事業計画書には、実際にどのような工事やプロジェクトを進めるのか、そのために必要な資金の内訳や収支予測、借入金の返済プランなどを明確に記載する必要があります。
特に建設業では、工事の開始時点で多額の資金が必要になるケースが多いので、資金の出入りがいつ・どのように発生するかを明確に示すことが大切です。
また、これまでの施工実績や年間の完成工事高といった客観的なデータを提示することにより、経営の安定性を印象付けることも有効です。
資金調達先との関係性を深めておく
建設業においてスムーズに資金調達するには、金融機関との信頼関係を深めておくことも重要です。
日頃から取引のある金融機関と積極的にコミュニケーションを取り、自社の経営状況や将来のビジョンをしっかりと伝える姿勢が求められます。
また、金融機関の担当者と日頃から良好な関係を築いておくことで、業界特有の課題や資金ニーズについて相談しやすくなり、場合によっては条件面での柔軟な対応や有益な提案を受けるケースもあります。
このように、金融機関と継続的に良い関係性を築くことが、建設業における資金調達の成功を左右する大きな要因となります。
建設業で開業資金を調達する際の注意点

建設業で開業資金を調達する際の注意点については、以下の3つが挙げられます。
- 資金繰りが難しい場合がある
- 適切な資金繰りをする
- 必要な資格や許可を取得する
それぞれの注意点について解説していきます。
資金繰りが難しい場合がある
建設業で開業資金を調達する際には、建設業は資金繰りが難しい傾向があるので、あらかじめ注意が必要です。
実際に、建設業で独立して事業を始める場合、日々の運営に必要な資金を見落としやすい傾向があります。
建設業は請負から入金までに時間がかかることが多く、利益が出ていてもタイミングによっては支払いに充てる資金が足りずに経営が行き詰まるケースもあります。
このような現象は「黒字倒産」と呼ばれ、その背景には資金管理の難しさがあるのも事実です。
このような事態を防ぐには、現金の出入りを見える化する「キャッシュフロー表」の作成が有効です。
資材の購入費や、人を雇っている場合は給与の支払いも含めて、必要な支出をしっかりと見積もるようにしましょう。
また、新しい案件を受ける際には、事前に資金面の見通しを立てて、途中で資金が足りなくなるといったリスクを避けることが重要です。
適切な資金繰りをする
建設業は、事業を始めるうえで多額の初期資金が必要になるケースが多いので、適切な資金繰りをするようにしましょう。
具体的には、資金の流れを的確に把握し、綿密な予算の設計を行うことが極めて重要です。実際に、資金の運用を誤れば、事業の発展が妨げられるだけでなく、経営そのものが行き詰まるリスクがあるのも事実です。
こうした事態を回避するためにも、計画的な資金繰りと現実的な予算管理は、企業の安定的な成長にとって不可欠な要素と言えます。
必要な資格や許可を取得する
建設業で開業資金を調達する際には、必要な資格や許可の取得も計画に入れることが重要です。
建設業を始めるには、まず専任技術者の資格取得や建設業許可が求められ、法律に基づいて事業を適正に運営するうえで欠かせない基本的な条件です。
また、資格や許可を得ることで、取引先や顧客に対して企業としての信頼性や専門的な能力をアピールすることも可能になります。
しかし、資格や許可の取得には一定の期間や費用がかかります。一般建設業許可を取得する際には、資本金500万円以上または500万円以上の自己資本金が原則必要という要件もあるため、事業を始める前に十分な準備と計画を立てましょう。
さらに、資格や許可の取得が不十分な状態で業務を行った場合、法的な罰則を受けてしまったり、顧客からの信頼を失い、事業の継続が難しくなる恐れもあるので注意が必要です。
このように、法令をしっかり理解し、万全の体制で事業運営することが重要です。
参考:国土交通省|建設産業・不動産業:建設業の許可とは
必要な開業資金を把握しよう!

今回は、建設業で開業資金が必要な目安を紹介しました。
建設業で独立を目指す際には、どの程度の費用がかかるのか、そしてその資金をどう確保するかをしっかりと把握しておくことが重要です。
特に建設業の場合、仕事を請け負ってから報酬の入金までに通常2〜3ヶ月のタイムラグがあるため、資金のやりくりが難しくなる傾向があります。
そのため、事業開始前から資金の流れを可視化し、余裕のある資金計画を立てることが欠かせません。
今回の記事を参考にして、公的な融資制度や金融機関のサポートを上手に活用し、自己資金だけに頼らない資金調達方法を確保しておきましょう。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。










