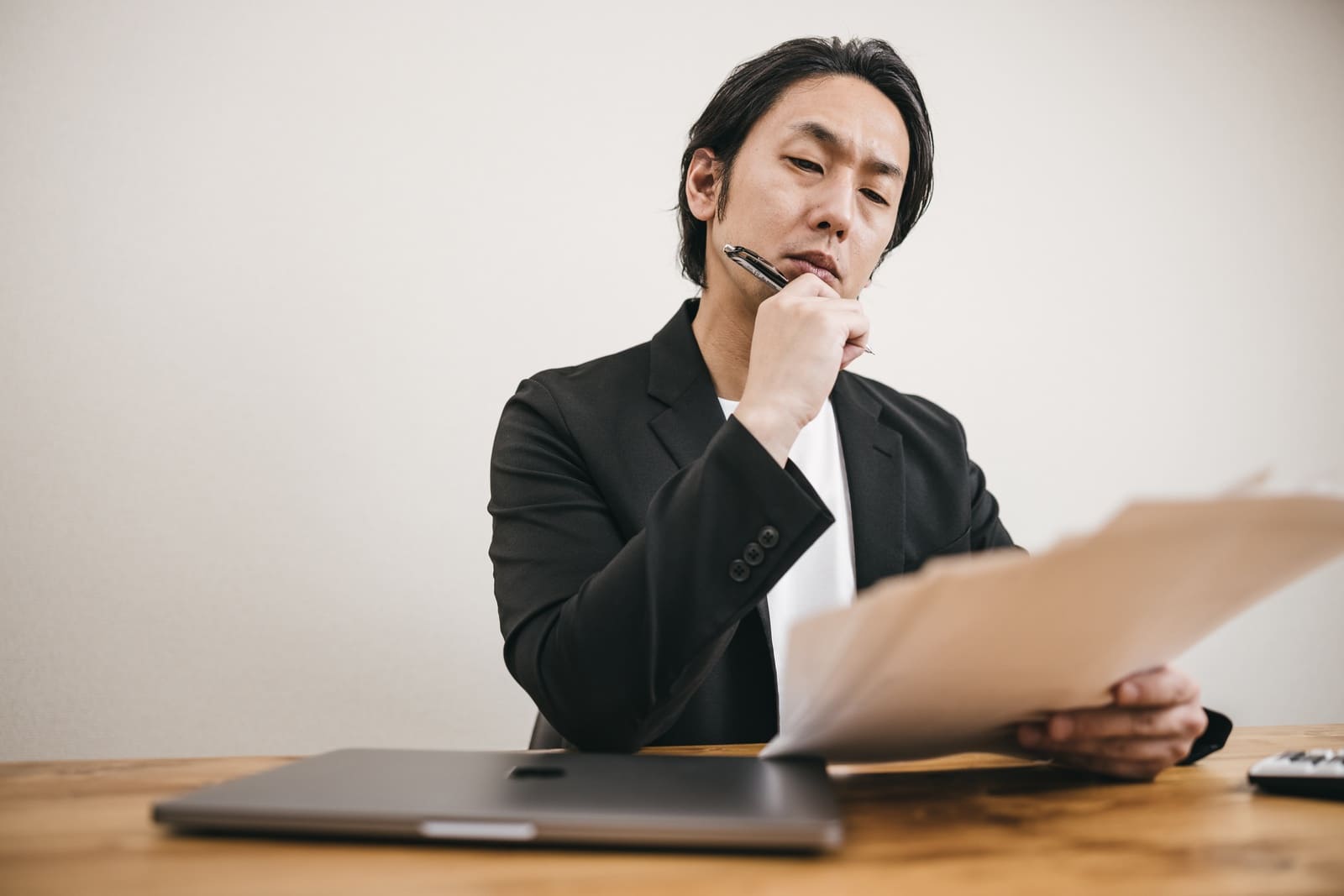メニュー
法人化
宗教法人を設立すべき?宗教団体との違い・要件や手続きについて

読了目安時間:約 6分
宗教法人を設立するには、宗教法人法に基づいて所定の手続きを行う必要があります。
宗教団体のままでも宗教活動は可能ですが、宗教法人を設立することで得られる利点について理解することは大切です。
本記事では、宗教団体との違いや必要となる要件について解説します。また、設立の手順についても紹介しますので、この記事を参考にスムーズな手続きを行っていただけたら幸いです。
目次
宗教法人とは法人格を有するもの
宗教法人は、宗教者と信者で構成される宗教団体が、所轄庁の認証を受けて法人格を取得したものです。
教義の普及や信者の育成などを目的とし、宗教活動を行っていきます。
法人格を有しないものは宗教団体とされており、所轄庁の認証を経て法人格を取得した団体が宗教法人となります。
文化庁により、宗教法人は以下のような種類に分類されます。
宗教法人には、神社・寺院・教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と、宗派・教派・教団のように神社・寺院・教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があります。単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、傘下にないものを「単立宗教法人」といいます。引用:文化庁|概要
宗教法人となるための要件とは
宗教団体として以下のような条件を満たすと、宗教法人を設立する準備が整ったといえます。
- 宗教団体の目的
- 宗教団体としての要件
- 宗教団体の実績
それぞれ見ていきましょう。
宗教団体の目的
宗教団体とは、以下の3つを主たる目的とする団体です。
| 目的 | 概要 |
| 教義を広める | 宗教や宗派の教えを多くの人に広めること。布教活動などとも呼ばれる。 |
| 儀式行事を行う | 信仰の対象に対して感謝や祈願、祈祷などを捧げる儀礼的式典を行う。 |
| 信者を育成する | 教義を学ぶための教育プログラムや講義を提供し信者が宗教的な知識を深める機会を作る。 |
参考:文部科学省|宗教統計調査-用語の解説
また、宗教団体は対信者としての活動だけではなく、地域社会にむけた慈善活動や教育活動を行うこともあります。
宗教団体としての要件
宗教法人上の宗教団体として認められるためにはいくつかの要件があります。以下、詳しくご説明します。
能動的な活動を行っている
信者が能動的に宗教活動を行っていることが要件のひとつとなります。
教義をただ聞くのではなく「広める」、儀式行事はただ参加するのではなく「行う」、という宗教活動の姿勢がポイントになってきます。
宗教法人の設立に向けては、このような活動をしている信者名簿も準備しておくと良いでしょう。
専任性のある団体固有の教師がいる
宗教活動をするための専任の教師とは、お寺で例を挙げるのであれば住職です。
専任性があるというのは、教師活動だけで生活できるという意味合いです。
宗教法人の場合、基本的には信者からのお布施収入が収入の基盤となりますので、教師の生活を支えるだけの信者が集まっている必要があります。
公衆的礼拝施設を備えている
宗教団体として認められるには、信者等が自由に出入りできる礼拝施設を備えている必要があります。
自宅にある神棚や仏壇のように家族のみが出入りする閉鎖的な空間ではなく、公衆性が求められます。
また宗教団体は現在存在していれば良いというものではなく、永続性が求められます。そのため、賃貸施設よりも自己所有の施設である方が永続的な宗教活動を支えやすいといえます。
ただし、賃貸ではいけないという訳ではなく、あくまで自己所有の方が次世代への継承などもしやすい傾向にあると認識していただくと良いでしょう。
団体運営能力がある
宗教団体組織としての目的を達成するための、管理(機能)能力が求められます。
宗教法人として法人格を与えるのであれば、それ相応の組織でなければいけません。
団体の規約や代表機関、総会の設置は行われているでしょうか。
また以下のような書類を適切に作成し、保管されている必要があります。
- 役員名簿
- 議事録
- 事務処理簿
- 財産目録
- 収支計算書
- 境内建物に関する書類
宗教団体の活動実績
宗教団体が法人化するには、実務上2~3年程度の活動実績が審査基準とされることが多いといわれています。
実績がないと健全な宗教活動を行う団体であるか否かの判断ができないためです。
宗教法人の認可申請時には、活動状況を確認するために所轄庁による実態調査が行われることもあります。
宗教法人を設立するメリット
宗教法人を設立すると以下のようなメリットがあります。
- 法人名義での財産保有ができる
- 宗教行為に該当する範囲の税優遇
- 墓地や納骨堂の経営が可能になる
- 宗教法人だと事業承継しやすい
- 社会的信用を得られる可能性が高まる
法人名義での財産保有ができる
法人化されていない宗教団体だと、団体として所有する財産の名義に困ってしまいます。
例えば、礼拝堂などの不動産の名義や仏具などの所有権など、個人が所有していると相続時に手続きが面倒になってしまうためです。
しかし宗教法人となれば、これらを法人名義で所有できるようになります。
権利の帰属先を法人にしておくと、財産管理が容易になりますし、支出の管理がしやすくなります。
多くの宗教団体が法人化を目指す理由のひとつになるといえるでしょう。
宗教行為に該当する範囲の税優遇
営利目的ではありませんので宗教活動に関する収入は非課税となりますが、駐車場貸出や結婚式、料理の提供など収益事業があれば課税対象となります。
宗教法人となると、以下のような税優遇が受けられます。
- 境内地や境内建物の固定資産税・登録免許税・不動産取得税が非課税
- 都市計画税を課されない
- 収益事業の法人税率が低い
- 法人事業税・道府県民税・市町村民税を課されない(収益事業を行わない場合)
収益事業には原則19%(資本金1億円以下)の税率が適用されますので、法人化のメリットとなります。ただし、宗教法人の収益事業区分は厳格に判断されることを理解しておきましょう。
参考:国税庁|宗教法人の税務
墓地や納骨堂の経営が可能になる
墓地や納骨堂の経営は原則として宗教法人に認められており、民間企業が経営するには特定の許可が必要です。
宗教法人となることで、墓地や納骨堂の経営が可能になります。
社会的信用を得られる可能性が高まる
閉鎖的な宗教団体だと、周囲からは実態が見えづらい状態となってしまいます。
しかし宗教法人となれば、代表者の住所や氏名が登記されて誰でも閲覧できるようになります。
外部から実態が見えやすくなりますので、透明性が高まり社会的な信頼に繋がります。
社会的な信頼を得られると、さらに宗教活動を行いやすくなり、その宗教法人にとっても良い環境となるでしょう。
宗教法人を設立するデメリット
宗教法人を設立するにはメリットだけでなく、以下のようなデメリットがあります。
- 設立手続きが困難
- 宗教法人法上の規定がある
- 補助金や助成金は対象外
設立手続きが困難
宗教法人となると税優遇などのメリットがありますので、宗教団体としての実態を正しく把握する必要があります。
宗教団体としての実態を把握する機関は所轄庁です。
そのため本当に宗教活動を行っている団体なのかの審査があり、この審査は2~3年と長い期間をかけて慎重に行われます。
株式会社の設立は2週間程度が目安といわれていますので、宗教法人設立には比較にならないほどの時間がかかります。
さらに必要書類が多いので、事務的な手間がかかるのも覚悟しておきましょう。
宗教法人法上の規定がある
宗教団体が宗教法人となると、宗教法人法の規制を受けるようになります。
参考:e-Gov法令検索|宗教法人法
財産処分の規制や帳簿類の所轄庁への提出義務など、宗教法人の業務運営に関する規定があります。
補助金や助成金は対象外
補助金や助成金は原則返済不要であり、起業家や中小企業で該当するものは積極的に活用するのをおすすめします。
しかし原則として、宗教法人は補助金や助成金の対象外となっています。
「税優遇がされている」「収益事業を行わない宗教法人は確定申告が不要」という理由があるためです。
宗教法人は金融機関からの融資が厳しいケースが多いので、いざという時の資金繰りは日頃から考えておく必要があるでしょう。
宗教法人設立の手順
宗教法人を設立するための手続きの手順を確認していきましょう。
- 宗教団体としての活動実績を積む
- 規則の作成と設立発起人会の決議
- 包括宗教団体の承認
- 設立公告
- 所轄庁に規則の認証申請
- 所轄庁の審査と認証
- 所轄庁から規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本交付
- 宗教法人設立登記(交付日から2週間以内)
- 所轄庁へ宗教法人成立登記の提出
全国の所轄庁については、内閣府のホームページを参考になさってください。
参照:内閣府NPO
宗教法人の税申告について
宗教法人を設立したら、宗教法人ならではの税申告が必要となります。
収益事業には法人税が課税されますので、宗教法人の税申告について正しく理解しておきましょう。
- 収益事業には法人税が課税される
- 宗教活動は非課税
- 源泉徴収義務がある
収益事業には法人税が課税される
宗教法人が行う活動の内、宗教活動と収益活動を分けて考えなくてはいけません。
お守りやおみくじは宗教活動となり非課税ですが、一般の物品販売業者が販売しているものの販売は収益活動となります。
例えば、絵葉書やカレンダー、数珠やキーホルダーなどが収益事業に該当すると考えられます。
お墓の土地の貸付や宿泊施設の経営なども収益事業となりますので、これらのボーダーラインを正しく理解するようにしましょう。
宗教活動は非課税
宗教活動のみを行っており、課税対象となる収益活動を行っていない宗教法人は法人税が課税されません。
そのため宗教活動のみを行っている宗教法人は、原則として確定申告が不要です。
ただし宗教活動のみでも収入8,000万円を超える場合は確定申告が必要になりますので、覚えておきましょう。
源泉徴収義務がある
宗教法人で住職や宮司といった代表役員に、給与や手当を支払うと源泉徴収を行わなければいけません。
顧問弁護士や税理士に支払う報酬も同様となりますので、正しく処理してください。
宗教法人に関するよくある質問
宗教法人設立に関するよくある質問をまとめました。
- 宗教法人の最低人数は決まっていますか?
- 宗教法人は社会保険の適用になりますか?
- 宗教法人の登記にはいくらかかりますか?
宗教法人の最低人数は決まっていますか?
宗教法人には、必ず3人以上の責任役員(うち1人は代表役員)を置くとされています。
参考:文化庁|宗教法人のための運営ガイドブック
また信者の数を定めている所轄庁がありますが、一方で明確にしていない所轄庁もありますので確認しておきましょう。
宗教法人は社会保険の適用になりますか?
法人登記されている事業所であって常時従業員を使用する場合は、厚生年金保険の適用事業所となります。
参考:日本年金機構|年金Q&A
宗教法人であっても常時従業員を雇用していれば、社会保険の加入義務があります。
宗教法人の登記にはいくらかかりますか?
宗教法人の設立登記の登録免許税はかかりません。
ただし専門家のサポートを受ければ、そのための費用が必要になります。
宗教法人の設立は税理士に相談を
宗教団体から宗教法人を設立すると、税優遇や事業継承などで大きなメリットがあります。
しかしどんな団体でも宗教法人になれるわけではなく、厳しい審査を通過しなければいけません。
宗教法人となったら正しく税申告をしていかなければいけませんので、事務的な負担が増える懸念があります。
宗教法人の設立や経営に関して、税理士法人松本でサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。