メニュー
法人化
建設業で独立して一人親方になる前に必要な準備や手続きは?メリット・デメリットについても解説

読了目安時間:約 7分
一人親方として独立するには、さまざまな公的な手続きを済ませる必要があり、さらに準備すべきことも多岐にわたります。
あらかじめ計画的に進めなければ、事業を始めた後に思わぬトラブルに直面するリスクがあります。
しっかりと必要な手順を把握し準備を整えることで、スムーズに事業を運営していくことにつながります。
本記事では、建設業で独立して一人親方になる前に必要な準備や手続きについて紹介します。
他にも「建設業で独立して一人親方として働くメリット・デメリット」や「建設業で独立して一人親方として成功するコツ」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、一人親方になるための準備に役立ててください。
目次
建設業で独立して一人親方になる前に必要な準備

建設業で独立して一人親方になる前に必要な準備には、以下の4つが挙げられます。
- 初期費用の準備
- 必要な許可や資格の取得
- ローン契約
- 人脈を広げる
それぞれの項目について解説していきます。
初期費用の準備
一人親方として独立するには、ある程度の初期資金を用意する必要があります。
初期費用には、仕事で使う工具や機材の購入費、作業場や倉庫を借りるための費用などが含まれます。
必要な資金の額は事業規模などによっても異なりますが、一般的には数百万円から多い場合で数千万円かかることもあります。
資金を準備する方法としては、自己資金に加えて、銀行融資や公的な支援制度の活用が考えられます。
例えば、日本政策金融公庫が提供している制度を利用することで、資金調達の選択肢を広げることができます。
独立に向けた計画を立てる際には、こうした融資制度の条件や申請方法についても事前に確認しておくことをおすすめします。
参考:日本政策金融公庫
必要な許可や資格の取得
一人親方として働くために必須の資格はありませんが、業務内容によっては取得すべき資格がある場合もあります。以下のような資格を取得することで、仕事の幅を広げたり、信頼性を向上させたりすることができます。
- 建設業許可
- 技能士資格
- 作業主任者資格
これらの資格や許可の取得には時間がかかるものもあるため、開業前から計画的に準備することが大切です。資格を取得することで、自身の技術力を高めることができるだけでなく、業界内での競争力の強化にもつながります。
これらの資格や許可の概要については、以下をご確認ください。
参考:国土交通省|建設産業・不動産業:建設業の許可とは
参考:厚生労働省|とび技能士、厚生労働省|玉掛け技能講習規程(◆昭和47年09月30日労働省告示第119号)
参考:厚生労働省|足場の組立て等作業主任者技能講習規程(◆昭和47年09月30日労働省告示第109号)
ローン契約
一人親方になる前には、作業車などのローン契約を済ませておくことをおすすめします。ローンの審査では個人の信用が重視されます。
実際に、独立後に作業車をローンで購入しようとしても、審査に通らないケースもあります。仮に審査が通ったとしても、金利が高くなる可能性があるため、支払い負担が増えることも考えられます。
このことから、ローン契約は信用力の高い会社員のうちに済ませておくことが一般的に推奨されています。
人脈を広げる
独立前にしっかりと人脈を広げておくことは、一人親方として成功するための重要な準備の一つです。
仕事を安定して受注できるかどうかは、どれだけ多くの人脈があるかにも左右されます。
特に、条件の良い案件や仕事が少なくなる時期の依頼は、普段から取引先と良好な関係を維持している方が集まりやすくなるので、独立前から積極的に人とのつながりを広げておくことが大切です。
人脈を広げる方法としては、異業種交流会などに参加しさまざまな分野の人々と関わるのも有効です。
また、これまで勤めていた会社との関係を良好に保つことも、独立後の仕事につながる可能性があります。
スムーズな独立を実現するためには、円満退職を意識して行動することも大切です。
建設業で独立して一人親方になる前に必要な手続き

建設業で独立して一人親方になる前に必要な手続きについては、以下の5つが挙げられます。
- 開業届の準備
- 青色申告の確認
- 国民健康保険への切り替え手続き
- 国民年金への変更手続き
- 労災保険への加入手続き
それぞれの手続きについて解説していきます。
開業届の準備
個人で事業を始める際、最初に行うべき重要な手続きが開業届の提出です。
開業届は、税務署に対して自分の事業を正式に開始したことを知らせるためのもので、事業を始めた日から1か月以内に提出することが定められています。事業を始めてからではバタバタしてしまうことも考えられるため、記入する内容についてはあらかじめまとめておきましょう。
開業届には、次のような情報を記入します。
- 事業主の氏名と住所
- 屋号(設定している場合)
- 事業の内容
- 事業開始日
- 事業を行う場所の住所
開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、事業の所在地を管轄する税務署に提出します。
参考:国税庁|個人事業の開業届出・廃業届出等手続
青色申告の確認
青色申告は、個人事業主や不動産収入がある人が利用できる確定申告の方法の一つです。
この申告制度を活用すると、税制面でさまざまな優遇措置を受けることができるため、一人親方などの事業主にとっても大きなメリットがあります。開業届を出すことで申請できる制度であるため、あらかじめ概要などは確認しておきましょう。
具体的に、青色申告のメリットについては、以下が挙げられます。
- 最大65万円の青色申告特別控除
- 赤字(損失)の繰越控除や繰戻還付
- 純損失を3年間繰り越して控除可能
- 家族従業員の給与を必要経費として計上できる
このように、青色申告には節税につながる利点が多く、事業を営む個人にとって有効な手段となります。このほかにも、白色申告という制度もあり、青色申告を選択しない場合はこちらの制度が適用されます。
詳しくは国税庁のホームページなどをご確認ください。
国民健康保険への切り替え手続き
勤めていた会社で社会保険に加入していた場合、退職後はご自身で国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。
手続きをしないままでは、新たな健康保険証が発行されず、万が一病院を受診した際には医療費を全額自己負担する必要があるので注意が必要です。
国民健康保険への加入手続きは、退職日から14日以内に住んでいる市区町村の役所で行うことが定められています。
期限を過ぎると、遡って未払いの保険料を請求されることがあるため、早めに手続きすることをおすすめします。
参考:厚生労働省|国民健康保険制度
国民年金への変更手続き
国民年金への切り替え手続きも必要になります。
企業に属し社会保険の被保険者だった間は厚生年金に加入していますが、退職するとその資格を失うため、自分で国民年金に加入する必要があります。
この手続きも退職日の翌日から14日以内に済ませる必要があり、手続きを行う場所は住んでいる市区町村の役所になります。
参考:日本年金機構
労災保険への加入手続き
一部例外を除き個人事業主は労災保険の加入が認められていませんが、建設作業や重量物の取り扱いを含む業務を行う一人親方は労災保険の特別加入制度が利用できます。
建設業は危険な現場で業務を行いますので、労災保険に加入しておきましょう。
労災保険の特別加入手続きを行うには、労働保険事務組合に加入しそこを通じて申請を行うことが一般的です。
参考:厚生労働省|労災保険への特別加入
建設業で独立して一人親方として働くメリット

建設業で独立して一人親方として働くメリットについては、以下の3つが挙げられます。
- 節税効果が高い
- 仕事量を調整できる
- 高収入を目指しやすい
それぞれのメリットについて解説していきます。
節税効果が高い
一人親方は個人事業主としてみなされるため、仕事にかかるさまざまな費用を収入から差し引くことが可能です。
確定申告の際には、事業に必要な経費を適切に申告することで、課税対象となる所得を減らし、結果的に節税につながる可能性があります。
計上できる主な経費の例として、以下のようなものがあります。
- 工具や機材の購入費用
- 車両に関する費用(燃料代、保険料、メンテナンス費など)
- 作業着やヘルメット、安全靴などの購入費
- 事務所や倉庫の賃貸料
- 通信費(携帯電話やインターネットの利用料金)
- 仕事用の広告宣伝費
このような業務に必要な支出を適切に経費として処理することで、税負担の軽減につながります。ただし、経費の申告には正確性が求められるため、必要であれば税理士に相談することをおすすめします。
参考:厚生労働省|安全衛生経費確保のためのガイドブック
仕事量を調整できる
一人親方として働くメリットとして、自分の裁量で仕事量を調整できる点があります。
忙しい時期には積極的に案件をこなし、収入を増やすことが可能です。
反対に、プライベートの予定がある時や体調を整えたい時には、仕事をセーブすることもできます。
実際に、柔軟な働き方は、ワークライフバランスの向上にもつながります。
家族との時間を優先したい方や、副業として一人親方を始める方にとって魅力的な選択肢と言えます。
高収入を目指しやすい
一人親方として働くメリットとして、高収入を目指しやすいメリットが挙げられます。
一般的に、企業に勤める場合は役職などに応じて給与が決まりますが、一人親方として働く場合、売上が収入に直結するため、雇用される立場よりも高い単価で仕事を請け負えることが多いのが特徴です。
一人親方自身のスキルや経験、専門的な知識を直接報酬に反映できるので、高収入を目指しやすいと言えます。ただし、収入は仕事の受注状況に影響されるため安全には注意が必要です。
建設業で独立して一人親方として働くデメリット
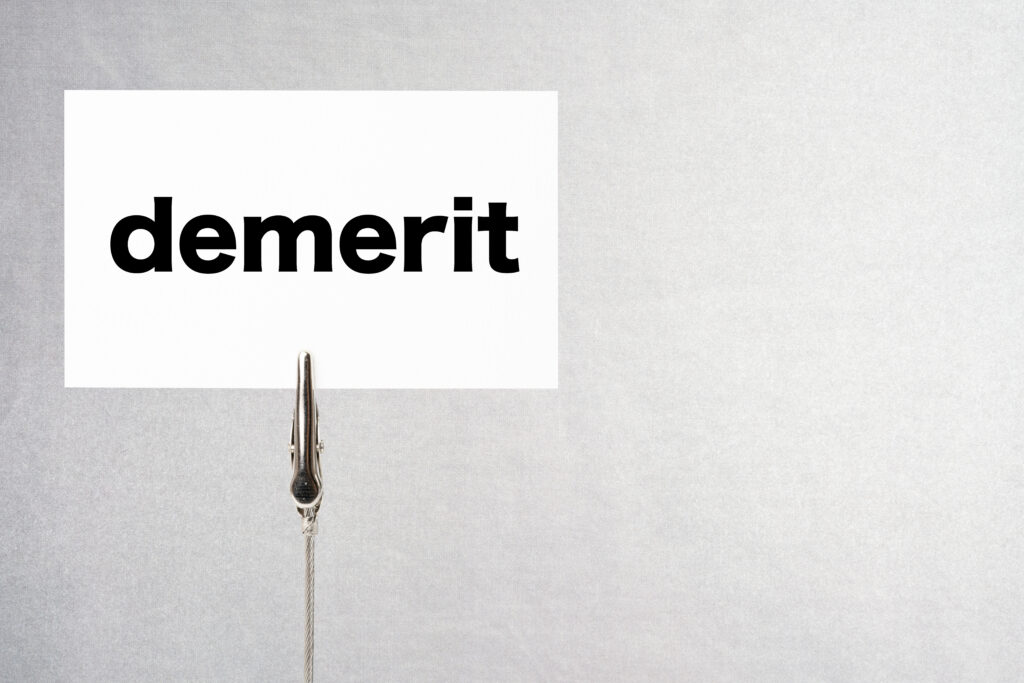
建設業で独立して一人親方として働くデメリットについては、以下の2つが挙げられます。
- 収入が不安定になる
- 融資審査が通りづらくなる
それぞれのデメリットについて解説していきます。
収入が不安定になる
一人親方として働く際のデメリットの一つは、収入が安定しにくいことです。
会社員とは異なり決まった給料が支払われるわけではなく、仕事の受注状況によって収入が大きく変わります。
特に建設業界では、景気の変動や季節的な要因の影響を受けやすく、仕事が少なくなる時期には収入が大幅に減少することもあります。
さらに、病気やケガで仕事を休まざるを得ない場合、収入が完全に途絶えてしまうリスクも考えられます。高収入を得られる可能性がある反面、収入が安定しないリスクには注意が必要です。
融資審査が通りづらくなる
銀行や金融機関は、安定した収入があるかどうかを重要視するので、一人親方として働くことで融資審査が通りづらくなるデメリットが挙げられます。
収入が一定でない一人親方は、住宅ローンや事業資金の融資を受ける際に審査で不利になることもあります。同様にクレジットカードの審査においても、収入の変動が理由で承認が難しくなるケースが見られます。
建設業で独立して一人親方として成功するコツ

建設業で独立して一人親方として成功するコツについては、以下の3つが挙げられます。
- 営業スキルを身につける
- 単価を上げる
- スケジュール管理を徹底する
それぞれのコツについて解説していきます。
営業スキルを身につける
一人親方として働く場合、自ら営業活動を行い、仕事を獲得していくことが求められます。
新規の案件を増やしたり、一つひとつの仕事の単価を上げることができれば、収入の安定化と向上が期待できます。
そのためには、専門技術の向上だけでなく、営業力や交渉力を磨くことも重要です。
特に、営業に不慣れなうちは、セミナーや研修を積極的に活用し、必要なスキルを身につけておくなども良いでしょう。
単価を上げる
建設業で独立して一人親方として成功するコツとして、収入に余裕が生まれスケジュールが埋まってきたら、少しずつ仕事の単価アップを目指すようにしましょう。
まずは、仕事を継続的に確保することが最優先ですが、単価を上げるにはある程度スケジュールに余裕を持つことが重要です。
現在の取引先との契約で単価を上げるのは簡単ではないため、新たなクライアントを開拓する必要も出てきます。
しかし、スケジュールが完全に埋まってしまうと新規の仕事を受ける余裕がなくなり、一方で現在の仕事を急にゼロにするのもリスクが大きいです。
そのため、安定した収入を維持しつつ、新しい案件に対応できる時間を確保しながら、徐々に単価アップを進めていくのが理想的です。
スケジュール管理を徹底する
独立した後に成功するためには、仕事を切らさずに、できるだけ早い段階で安定した収益を確保することが重要です。
十分な資金がなければ、新たな道具や設備を揃えることが難しくなり、精神的な余裕も失われてしまいます。その結果、事業の成長が妨げられるリスクが高くなることも考えられます。
実際に、予定が頻繁に空いてしまうと、安定した収入を確保するのが難しくなります。
また、依頼を受けた際に極力断らず、柔軟にスケジュールを調整することも、仕事を途切れさせないためのポイントです。
このように、複数の現場を効率よく組み合わせ、ムダのないスケジュールを立てる力を養うことが大切です。
一人親方になる前に入念な準備をしよう!

今回は、建設業で独立して一人親方になる前に必要な準備や手続きを紹介しました。
一人親方として働くと、自分の判断で仕事を進められる場面が増え、状況によっては高い収入を得られる可能性があります。
しかしその一方で、会社員のような労働者向けの保護制度の対象外となり、収入が安定しにくいというリスクも伴います。
また、事業を始める際には、税務署への開業届の提出が求められるほか、国民年金や国民健康保険などの加入手続きも忘れずに行う必要があります。
今回の記事を参考にして、一人親方になる前に入念な準備をしましょう。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。










