メニュー
会社設立
飲食店で合同会社設立するタイミングとは?メリット・デメリットや注意点も解説

読了目安時間:約 6分
飲食店では合同会社設立のタイミングによって、消費税の負担額や必要な手続きが大きく変わります。
合同会社設立には、社会的な信用力の向上や有限責任といったメリットがありますが、設立時に費用が発生することや税務関連の手続きが複雑になるといったデメリットもあります。
本記事では、飲食店で合同会社を設立するタイミングを紹介します。
他にも「飲食店で合同会社を設立するメリット・デメリット」や「飲食店で合同会社を設立する際の注意点」についても解説します。
ぜひこの記事を参考にして、飲食店で合同会社設立を検討してみてください。
目次
飲食店で合同会社設立するタイミング

飲食店で合同会社設立するタイミングについては、以下の4つが挙げられます。
- 課税売上高が1,000万円を超えた
- 課税所得が800万円を超えた
- 社会保険に加入したい
- 事業拡大をしたい
それぞれのタイミングについて解説していきます。
課税売上高が1,000万円を超えた
事業の売上が前々年に1,000万円を超えている場合、消費税の課税事業者に該当してしまい、売上にかかる税金に加えて、消費税の納税義務も生じます。
しかし、そのタイミングで法人化すると一定の要件を満たすことで最大2年間、消費税の納税義務が免除される可能性があります。
そのため、多くの事業者にとって「課税売上高1,000万円」は法人化を検討する際の一つの基準とされています。
参考:国税庁|納税義務の免除
課税所得が800万円を超えた
課税所得が800万円を超えると、個人事業主としての所得税率が法人税率を上回る場合があります。
法人にすることで給与所得控除を利用できるため、役員報酬の設定次第では税負担を抑えることが可能です。加えて、法人化すれば経費として認められる範囲が広がるため、利益のコントロールがしやすくなるメリットもあります。
このことから、課税所得が800万円を超えたタイミングで法人化を検討するのも一つの判断基準となります。
参考:国税庁|法人税の税率
社会保険に加入したい
原則として、事業を法人化すると社会保険へ加入することが定められています。
個人事業主のままでは社会保険の適用を受けられないため、事業主自身や従業員が将来にわたって安定した保障を得るのが難しくなる可能性があります。しかし、法人化すれば社会保険の加入が義務づけられ、従業員の福利厚生が手厚くなります。
結果として、従業員満足度や定着率の向上が期待されます。このことから、社会保険を目的として合同会社の設立を検討するケースもあります。
事業拡大をしたい
事業拡大をしたいタイミングも、合同会社設立する基準の一つです。
事業が順調に進み、さらなる成長を目指す段階になると、資金調達のしやすさや契約の柔軟性の面で、個人事業主よりも法人の方が有利になることが多いです。
また、社員を雇う予定がある場合も、法人化によって社会的信用が向上し、優秀な人材を確保しやすくなるほか、給与所得控除を活用できるようになるので、節税面でもメリットがあります。
今後、事業の拡大を視野に入れ、新たな取引先を開拓したり、従業員を雇用したりする計画がある場合は、法人化を検討することをおすすめします。
飲食店で合同会社を設立するメリット

飲食店で合同会社を設立するメリットについては、以下の4つが挙げられます。
- 社会的信用を得られる
- 有限責任になる
- 設立費用が安い
- 節税効果が高くなる
それぞれのメリットについて解説していきます。
社会的信用を得られる
飲食店で合同会社を設立すると、商号や所在地、資本金などの会社の基本的な情報が公開され、社会的な信用度が向上します。
その結果、銀行などの金融機関から融資を受けやすくなる可能性が高まります。
また、法人であることが取引先の信頼につながるケースも多く、特に大企業や公的機関との契約では、法人格を持つことが重要視されることがあります。
株式会社と比較すると信用度が低いケースとみなされる場合もありますが、近年は合同会社として起業する企業も増加傾向にあり、一定の信用を得られるケースも見られるようになっています。
信用度が向上することによって、個人事業主のままでは取引が難しかった企業ともビジネスを進められることにもつながります。
有限責任になる
法人化によって経営者の個人的な責任は限定されるため、基本的には会社の負債が直接個人に及ぶことはありません。
法人が負う借金は、基本的に法人の資産の範囲内でのみ処理され、経営者自身が個人の財産で返済する義務はありません。
例えば、出資した飲食店が負債を抱えたまま倒産した場合でも、経営者は投資した資金を失うだけで、原則として会社の借金を個人で支払う必要はありません。
個人事業主が事業の債務をすべて自分で負うケースとは異なり、経営者個人の資産が守られる仕組みになっています。
このように、飲食店が合同会社を設立することでリスクの高い事業にも安心して挑戦できることにつながります。
設立費用が安い
合同会社は、株式会社に比べて設立コストを抑えられるというメリットがあります。
例えば、株式会社を設立する際には約20万円の費用が必要ですが、合同会社ならおよそ6万円で済みます。(電子定款の場合)
また、株式会社は定款の認証を受ける必要がありますが、合同会社の場合は認証手続きが不要です。
その結果、合同会社は株式会社よりも設立に必要な手続きが少なく、一般的には短期間で設立しやすいとされています。
節税効果が高くなる
個人事業主としては経費として認められない支出も、合同会社を設立して法人化することで経費計上が可能になり、結果的に節税効果を高めることができます。
例えば、出張に関しても、交通費や宿泊費に加え、一定の条件を満たせば日当を経費として計上することも可能です。
さらに、法人では退職金の積み立てを経費にできるほか、中小企業に該当する法人であれば交際費のうち年間800万円までを損金算入することができます。
参考:国税庁|交際費等の範囲と損金不算入額の計算
その他にも、法人設立時にかかる費用や、税理士への顧問料なども経費に含めることができます。
このように、法人化すると経費計上できる範囲が広がり、節税対策の選択肢が増えるため、税負担を抑える効果が期待できます。ただし、経営状況などによっても異なるため、節税効果を目的としている場合は税理士に相談することをおすすめします。
飲食店で合同会社を設立するデメリット
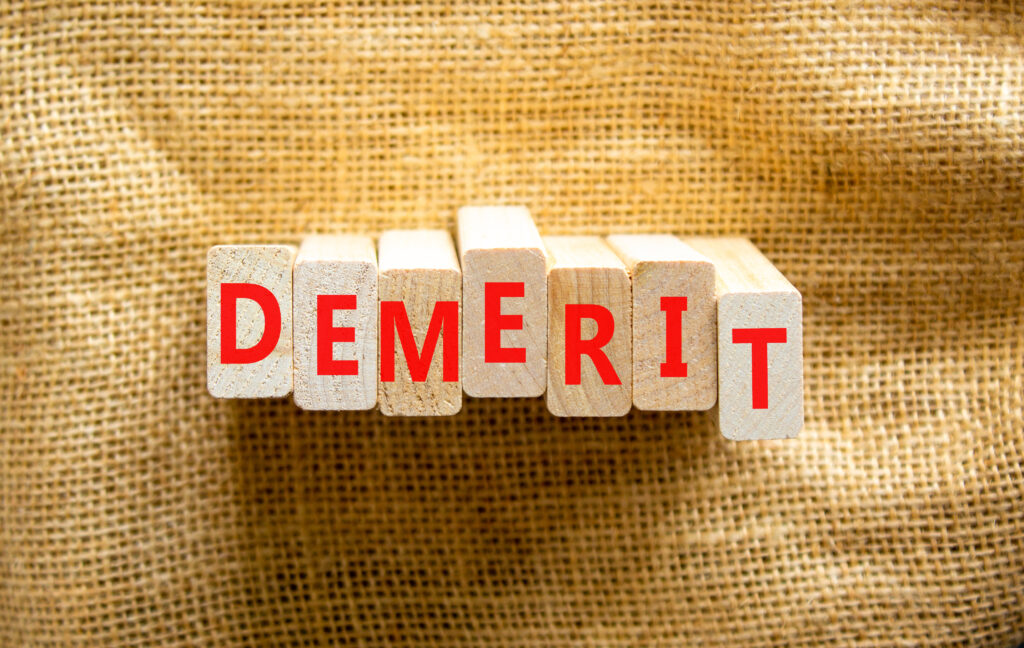
飲食店で合同会社を設立するデメリットについては、以下の4つが挙げられます。
- 設立費用がかかる
- 会計処理が複雑になる
- 運営コストが増加する
- 利益配分の自由度が下がる
それぞれのデメリットについて解説していきます。
設立費用がかかる
合同会社を設立するには、まず登記が必要となり、その際に登録免許税が発生します。
また、法人設立にあたっては、会社の印鑑作成や登記簿謄本の取得にかかる費用のほか、場合によっては司法書士や税理士などの専門家に依頼するための費用も発生する可能性があります。
そのため、特に資金に余裕のない小規模な飲食店にとっては、こうした初期費用が大きな負担となる可能性があります。
参考:国税庁|登録免許税の税額表
会計処理が複雑になる
個人事業主と比較すると会計処理や各種手続きが複雑になり、必要な書類も多くなります。
会社設立に関するものだけでも、定款の作成や設立登記申請、代表印の登録が必要になります。
法人として活動を始めると、法人設立届や青色申告の承認申請、社会保険の手続きなども必要になります。
これらの手続きは煩雑で手間がかかるため時間と労力を大幅に奪われてしまう場合があります。
運営コストが増加する
飲食店が合同会社を設立するデメリットとして、運営コストの増加が挙げられます。
法人として事業を運営する場合、税務申告や会計処理が個人事業主よりも複雑になるので、財務管理を適切に行うために税理士や会計士に業務を依頼する場合、顧問料や決算書作成費用といったコストが発生します。
また、法人を設立すると、毎年の決算書作成や税務申告が義務となるため、継続的に経費がかかってしまいます。
さらに、利益が出ていなくても一定額の法人住民税を支払わなければならないのもデメリットの一つと言えます。
利益配分の自由度が下がる
法人化のデメリットの一つとして、利益の使い道が制限される点が挙げられます。
個人事業主の場合、事業で得た利益はすべて自身の収入として自由に使えますが、法人を設立すると、会社の利益は法人のものと見なされ、自由に引き出すことができません。
具体的には、経営者が利益を受け取るには、役員報酬や配当金といった形で支給する必要があります。
役員報酬は事前に設定した金額に基づいて支払われ、年度途中で変更する際には税務上の手続きが必要です。
また、配当金として利益を受け取る場合、法人税が引かれた後の金額から支払われ、さらに個人の所得としても課税されるため、結果的に税負担が増える可能性があります。
このように、個人事業主のときのように利益を自由に使えなくなる点は、法人化の大きなデメリットと言えます。
飲食店で合同会社を設立する際の注意点

飲食店で合同会社を設立する際の注意点については、以下の3つが挙げられます。
- 営業許可の引き継ぎができない
- 個人事業廃業後の確定申告が必要
- 合同会社設立後に個人事業主に戻るには手間がかかる
それぞれの注意点について解説していきます。
営業許可の引き継ぎができない
個人事業主として取得した営業許可は、その個人に紐づけられるため、法人化する際には法人名義で新たに許可を申請する必要があります。
営業許可の取得においては、「申請者の資格」と「営業所の所在地」が重要な要素になります。
そのため、法人として事業を継続する場合、個人で取得した許可は無効となり、改めて法人としての営業許可を取得する必要があります。許可の再取得には現地調査が再度行われるため、事前の準備をしっかりと行うようにしましょう。
詳しくは、許可を管轄する役所や行政機関に確認してください。
個人事業廃業後の確定申告が必要
事業年度の開始日である1月1日から廃業日までの期間は、引き続き個人事業主としての収入が発生していたとみなされるため、適切に所得を計算し確定申告を行う必要があります。
ただし、所得金額が48万円以下の場合は確定申告が不要です。
合同会社設立後に個人事業主に戻るには手間がかかる
法人化した後に再び個人事業主へ戻るには、複雑な手続きを踏む必要があるので注意が必要です。
まず、法人を解散するための手続き、その過程で様々な届け出や法的義務が発生します。
さらに、株主や取引先などの関係者へ法人解散を周知するため、公告を出す必要があります。
これらの手続きには時間と手間がかかるだけでなく、費用の負担もかかってしまいます。
そのため、法人から個人事業主へ戻る際には、相応の準備と計画が求められます。
事業規模に合わせて合同会社を検討しよう!

今回は、飲食店で合同会社設立するタイミングやメリット・デメリットを紹介しました。
合同会社という形態が誕生して以来、スタートアップや小規模事業者が会社を設立しやすい環境を整えることが可能になりました。
飲食店が合同会社を設立するメリットとして、設立時のコストが抑えられることと、経営の柔軟性が高いことです。
また、事業が順調に成長し、さらなる拡大や資金調達を視野に入れる段階になれば、合同会社から株式会社へ移行することも可能です。
本記事の内容は一般的な制度をもとにしており、個別の事情によって異なる場合があります。会社設立に関する判断は、税理士などに相談のうえ行うようにしましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。










