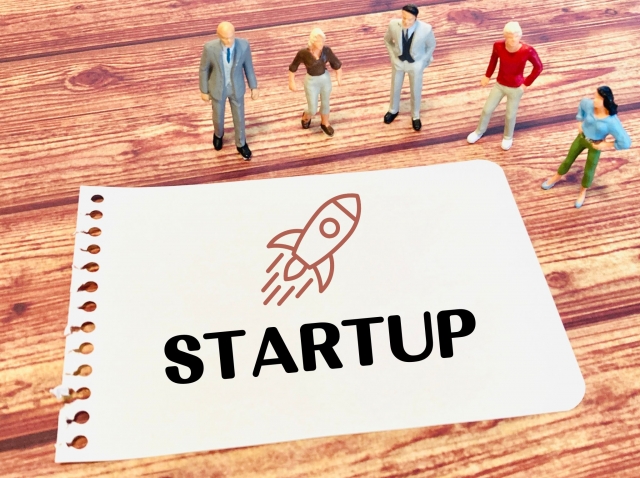メニュー
法人化
法人成りする際の在庫の引き継ぎ方法とは?会計処理方法や注意点についても徹底解説

読了目安時間:約 7分
法人成りする際、現在保有している資産を法人側に引き継ぐことは可能です。
しかし、単純にそのまま法人で使用し続けることはできず、一定の手続きを踏む必要があります。
資産の取り扱いについては、複数の方法があり、それぞれの方法に沿って正しい経費処理が求められます。
本記事では、法人成りする際の在庫の引き継ぎ方法について紹介します。
他にも「法人成りで在庫を引き継ぐ時の会計処理方法」や「法人成りで在庫を引き継ぐ際の注意点」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、法人成りする際の在庫の引き継ぎ方法について理解を深めてみてください。
目次
法人成りする際の在庫の引き継ぎ方法とは?
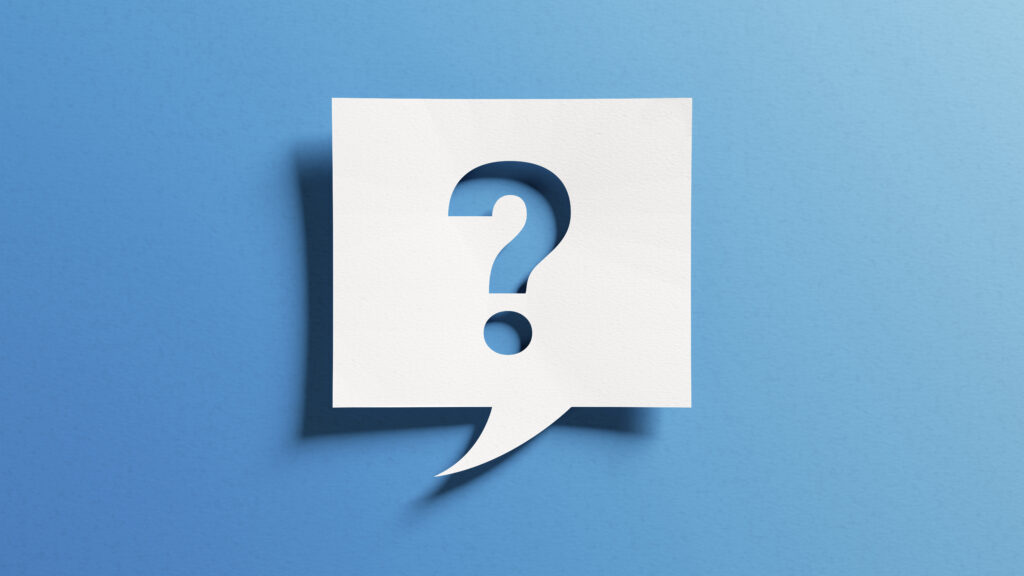
法人成りする際の在庫の引き継ぎ方法には、以下の4つがあります。
- 方法①:売買契約
- 方法②:現物出資
- 方法③:賃貸借契約
- 方法④:贈与契約
それぞれの方法について解説します。
方法①:売買契約
一つ目が、売買による譲渡です。
個人が保有する資産を法人へ売る形をとり、個人と法人の間で売買契約を結ぶことで移転ができます。
そのため、実務上の手間も少なく導入しやすい方法と言えます。
ただし注意点として、法人側は資産を取得するための対価を個人に支払う必要があります。
また、個人側では売却によって譲渡所得などの課税対象が発生する可能性があり、税負担が生じることもあるので、あらかじめ注意が必要です。
方法②:現物出資
個人事業で所有している現金以外の資産を法人へ移し、会社設立時の資本金として組み入れる方法です。
現金ではない資産には、自動車やパソコン、不動産などが含まれ、これらを資本金として活用することが可能です。
現在では、資本金1円からでも法人設立が認められていますが、資本金は創業初期の運営資金の基礎となるため、少しでも多く確保しておきたいのも事実です。
そこで、現金が不足している場合でも、こうした「現物」を資本金に変えることで、法人の信用力を高める手段になります。
しかし、現物を移すことで会社の帳簿上の資本は増えますが、実際の資金が増えるわけではないので注意が必要です。
また、資産の内容や価値を明らかにするために、一定の手続きが必要となります。
このように、現物出資は資本金を充実させる手段として有効ではありますが、状況によっては法人化のスケジュールに影響が出る可能性もあるので、事前に慎重な検討と準備が必要です。
方法③:賃貸借契約
個人が所有する資産を新しく設立する会社に貸し出すという方法です。この場合、資産の所有者は引き続き個人であり、法人側は賃料を支払うことで資産を使用することができます。
賃貸借契約は、売買契約と同様に、資産を引き継ぐための比較的シンプルな手段の一つです。
特に、不動産など売却に際して多くのコストや手続きが発生する資産において、よく選ばれる方法です。
ただし、個人事業主は法人から受け取る賃料収入について、所得として毎年確定申告を行い、税金を納める義務が生じます。
方法④:贈与契約
贈与契約とは、個人事業主が所有している資産を新たに設立した法人へ、無償で譲る形で引き継ぐ方法です。
この方法を用いれば、法人側は資産の取得にあたって購入費用を準備する必要がありません。
しかしお金のやり取りが発生していなくても、税務上はその資産が時価で譲渡されたとみなされる点に注意が必要です。ここでいう「時価」とは、譲渡が行われた時点での市場における相場価格を意味します。
このような取り扱いを「みなし譲渡」と呼びます。このみなし譲渡が適用されると、資産を受け取った法人は、その資産に見合う「受贈益」が発生したと見なされ、その分が法人税の課税対象となります。
一方、資産を譲り渡した個人事業主の側も、その譲渡によって所得が生じたと扱われ、所得税が課されることになります。
参考:国税庁|譲渡所得の対象となる資産と課税方法
法人成りする際に引き継げない在庫

法人成りする際には、保有するすべての資産をそのまま会社に移転できるとは限らないので、事前に理解しておくことが重要です。
例えば、リース契約や借用契約で使用している不動産や車両、設備などは自動的に法人に引き継がれるわけではありません。
これらは個人名義で契約されているケースが多いため、法人として使用を継続するには、法人名義であらためて契約を締結する必要があります。
さらに、契約の名義変更に伴って、賃貸条件など契約内容そのものが変更となる可能性もあるため、事前に貸主や契約先としっかり協議を行い、慎重に手続きを進めることが求められます。
法人成りする最適なタイミング

法人成りを検討する上での一つの目安として、以下のようなタイミングが挙げられます。
- 課税所得が800万円を超えた
- 売上高が1,000万円を超えた
- 事業拡大をしたい
それぞれのタイミングについて解説していきます。
課税所得が800万円を超えた
個人事業主と法人では、それぞれ所得に対して課される税金の仕組みが異なります。
個人事業主は累進課税方式が採用されており、所得が増えるほど税率も上がっていきます。
一方、法人には「比例税率」が適用され、ある一定の割合で法人税がかかります。
個人事業主の所得税率は次のように段階的に設定されています。
- 195万円まで:5%
- 195万円以上330万円以下:10%
- 330万円以上695万円以下:20%
- 695万円以上900万円以下:23%
- 900万円以上1,800万円以下:33%
- 1,800万円以上4,000万円以下:40%
- 4,000万円以上:45%
一方、資本金1億円以下の一般法人の場合、法人税は所得が800万円までが15%、所得が800万円を超える場合は23.2%に設定されています。
このように、一般的には所得が800万円を超えたタイミングが法人化を検討する目安とされています。
しかし、実際の税負担は所得控除の内容や事業以外の収入、法人化後の役員報酬の設定などによって大きく異なる可能性があります。
したがって、事業所得が700万円を超えたあたりで、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
課税売上高が1,000万円を超えた
課税売上高が1,000万円を超えたら、法人化を検討するタイミングといえます。
個人事業主としてこの金額を超えると、一定の条件を満たせば最大で2年間、消費税の納付が免除される可能性があります。
これは、起業初期の負担を軽減するために設けられている「消費税の簡易課税制度」による恩恵です。
制度の目的は、小規模なビジネスや個人での事業展開を後押しすることにあります。
さらに、法人として設立した翌年度においても、設立前2年分の売上が存在しないこと、加えて設立初年度の前半6ヶ月間の売上が1,000万円を下回っていれば、その年度も引き続き免税事業者として扱われ、消費税の支払いが免除されるケースがあります。
しかし、このような優遇措置を受けるためには、法人の資本金が1,000万円未満であることやその他所定の条件を満たしていることが前提になるのであらかじめ注意が必要です。
参考:国税庁|納税義務の免除
事業拡大をしたい
法人成りする最適なタイミングとして、事業規模を拡大したり、大きな資金調達を行うことを検討していることが挙げられます。
特に以下のような状況に該当する場合、法人化を進めるのに最適なタイミングと言えるでしょう。
- 法人でないと契約が結べない案件が存在する
- 株式発行などを通じて資金調達を行う予定がある
さらに、法人化することで、個人事業主では利用できない補助金や助成金の申請が可能になります。
個人事業のままでは事業の規模に限界があり、より一層の成長を目指すのであれば、法人化を検討するようにしましょう。
法人成りでの資産を引き継ぐ際の処理項目

法人成りで資産(在庫)を引き継ぐ際の処理項目については、以下の4つが挙げられます。
- 減価償却資産
- 棚卸資産
- 不動産
- その他(買掛金や借入金)
それぞれの方法について解説していきます。
減価償却資産
減価償却資産とは、車両やパソコン、事務用の備品など使用するうちに価値が少しずつ減少していく資産のことを指します。
これらの資産は、企業間で譲渡されることも多くありますが、その際の評価額は現在の時価に基づく点が重要です。
しかし、自動車のように市場価格が明確なものは時価で判断しやすいですが、そうではない資産については、帳簿上の残存価格(簿価)を用いて処理されるのが一般的です。
簿価とは、減価償却を進めた後に残っている価値、つまり残存期間を加味した金額のことを意味しています。
参考:国税庁|主な減価償却資産の耐用年数表
棚卸資産
棚卸資産とは、商品を販売や製造、業務上で消費するために取得し、一定期間保管している資産を指します。
例えば、今後販売する商品や仕掛品、製品を作るための原材料、事務作業などで日常的に使う消耗品などが含まれます。
個人で事業を営んでいた際に保有していたこれらの資産を法人に移す場合、通常は市場での一般的な販売価格に相当する額で法人に譲渡する形になります。
しかし、品質の劣化や破損などによって価値が下がっている場合には、その時点の時価をもとに処理されることが多いです。
会計処理の面では、個人事業主の側ではこの引き継ぎを売上として記録し、法人側では仕入れとして取り扱い、形式上は資産の売買が行われたという形になります。
不動産
不動産を個人から法人に引き渡す方法としては、売却(譲渡)と賃貸の2つの手段が存在します。
売却の場合は、個人事業主が所有する不動産を法人に売るという形式になります。
これによって、物件の所有権は法人に移転し、売却を行った個人事業主には譲渡所得が生じます。
一方、購入する法人側は、その不動産を自社の資産として帳簿に記録し、特に建物については減価償却を用いて会計処理を行います。
賃貸という方法では、不動産の所有権を変更せずに、個人事業主が法人に貸す形になります。
この場合は、不動産の名義変更などの煩雑な手続きは不要で、賃貸借契約を交わすだけで完結します。
しかし、個人事業主は法人から得た家賃収入を所得として申告する必要があります。
その他(買掛金や借入金)
事業を個人から法人へと移行する際には、買掛金や借入金といった項目引き継ぐことが可能です。
法人化する時点で負債が残っている場合、個人としてすべて返済を済ませておく方法と法人化後に法人として返済を行う方法の2種類があります。
最もシンプルで分かりやすいのは、個人事業主時代に抱えた借入や未払い金などの債務を法人化する前にすべて処理してしまうことです。
負債を法人に引き継がないことで、協議や契約変更手続きを避けられるというメリットがあります。
しかし、資金的な余裕がなく、個人のままでは負債の返済が難しい場合は、法人化後に設立する会社の名義で金融機関などから資金を借り入れ、負債の返済資金を確保する方法も検討できます。
このように、法人化に伴って負債をどのように扱うかは重要なポイントになるので、事前に借入先の金融機関などとしっかり相談し、引き継ぎの方法について合意を得ることが大切です。
法人成りで在庫を引き継ぐ際の注意点

法人成りで在庫を引き継ぐ際の注意点については、以下の2つが挙げられます。
- 資産譲渡に消費税がかかる
- 資産とのバランスに注意する
それぞれの注意点について解説していきます。
資産譲渡に消費税がかかる
個人事業主であっても、一定の条件を満たすと消費税を納める義務が生じます。
特に資産を売却した際、その取引が消費税の対象となるケースがあり、事業として行われる資産の譲渡が課税対象となることが挙げられます。
課税事業者として認められるには、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 適格請求書発行事業者に登録していること
- 基準期間(通常は全前年度)の課税売上高が1,000万円を超えていること
- 前年の1月1日から6月30日までの課税売上高と給与の支払額の合計が1,000万円を超えていること
これらの条件のいずれかに当てはまる場合、その個人事業主は課税事業者となり、資産の譲渡に対しても消費税の支払いが必要になります。
特に高額な資産の売却を行う際には、想定される消費税の額も加味して、事前に計画的に検討することが大切です。
参考:国税庁|消費税のしくみ
資産とのバランスに注意する
法人成りする際に、資産よりも負債が多い状態で事業の引継ぎを行う場合は、特に慎重な対応が求められます。
実際に、資産よりも負債が多い状態で事業の引継ぎを行うことで、法人から個人が資金を借りているような会計上の形になってしまいます。
これにより、法人が個人の経済的なマイナス分を補填していると見なされるリスクもあります。
こうした見方がされると、法人としての信用度が損なわれたり、今後の資金調達に支障をきたしたりする可能性があります。
そのため、法人化の際には、どの資産や負債を新会社に引き継ぐかをしっかり精査し、バランスのとれた移行を目指すことが重要です。
法人成りで不安がある場合は専門家に相談しよう!

今回は、法人成りする際の在庫の引き継ぎ方法を紹介しました。
法人成りを行う際には、個人が所有していた資産や負債を法人へ移す必要があります。
在庫や資産などを移行する方法はいくつかありますので、この記事を参考に適した方法を検討してみてください。
また、個人事業と法人は法的にも会計上も別の存在とみなされるため、個人事業の廃業届の提出や最終年度分の確定申告といった事務的な手続きも発生するので、あらかじめ注意が必要です。
今回の記事を参考にして、適切に在庫の引き継ぎを行うようにしましょう。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。