メニュー
- 税務調査
株式投資で得た収益を無申告にした場合のリスクをわかりやすく解説
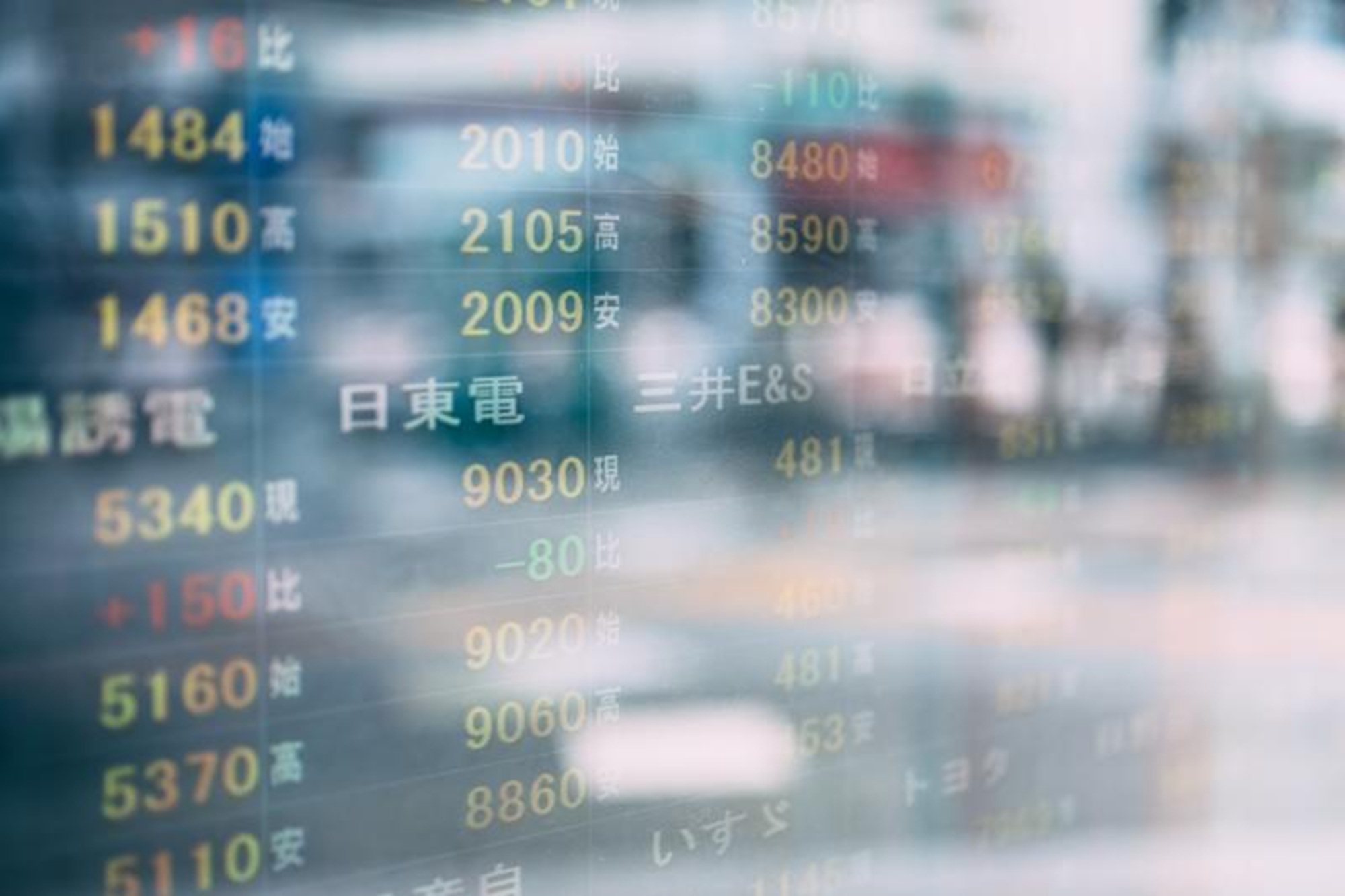
読了目安時間:約 7分
株式投資で得た利益を無申告にしていた場合、どのようなリスクが考えられるのでしょうか。「確定申告しない方がバレない」「税務署は個人のところには税務調査に来ない」といった噂が事実なのかも気になるところです。
本記事では、株式の売却などで得た利益を無申告にしていた場合のリスクや税務署にバレる可能性、税務調査が入った場合の注意点などについてわかりやすく解説しています。
株式投資の収益は無申告でも大丈夫なケース
株式投資で収益が出た場合に、無申告にしていても大丈夫なケースについて見ていきましょう。株式投資によって利益が出ていても、必ずしも確定申告が必要でない場合もあります。例えば、以下のケースでは確定申告は不要となります。
株式投資が副業で、利益が20万円以下の場合
会社員などの本業があり、副業で株式投資を行って利益を得た場合、年間の利益が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
他にも副業がある場合や、給与所得が2,000万円を超える場合には確定申告が必要となります。
株式投資の利益が48万円以下で他に収入がない場合
本業を持たずに、株式投資の利益のみを得ている場合、年間の利益が48万円以下であれば基礎控除の枠内におさまるため、確定申告は不要となります。
特定口座を利用している場合
源泉徴収ありの特定口座やNISA口座を利用して投資を行っている場合には、売却益に対して証券会社が所得税と住民税を源泉徴収するため、確定申告の必要はありません。特定口座でも源泉徴収なしの場合は、自身で確定申告する必要があります。
株式を保有しているだけの場合
株式を売却せず、保有しているだけの状態であれば、確定申告は不要となります。
無申告でも問題ないが、申告した方がよいケースも
株式投資で損失が出たケースでは確定申告は不要ですが、確定申告することで損失を翌年度へ繰り越せる、税金の還付が受けられるといったメリットが得られる場合があります。
会社員などの本業がなく、各種控除の申請や不動産の契約などで所得証明が必要な場合も、確定申告することで手続きが進められるようになるでしょう。
なお、確定申告が不要の場合であっても、住民税は申告の必要があります。住民税の申告を忘れると、住民税に延滞税がかかる可能性があるため注意が必要です。
住民税は住民票のある市区町村の住民税担当窓口へ申告を行いますが、確定申告期間中は役所内に臨時の申告窓口を設置しているケースもあるため、市区町村のホームページなどで確認してみましょう。
確定申告が不要なケースでも、申告によるメリットを受けたい場合は確定申告できるように、収支に関する書類の保管やデータのダウンロードなどを行っておくことをおすすめします。
株で得た利益を無申告にしていると税務署にバレるのか
株式投資で得た利益について確定申告しないでいると、税務署にバレる可能性があるのかについて解説します。
株で得た利益を無申告にした場合はほぼ100%税務署にバレてしまう
株式投資で得た利益を確定申告せず放置していた場合、税務署にはほぼ100%の確率で無申告者として認識されると考えた方がよいでしょう。
その理由として、証券会社が税務署へ提出する「支払調書」の存在が挙げられます。
支払調書とは、証券会社が一定以上の取引を行った支払者に関する詳細を記載した書類のことです。
1回の取引で30万円を超える利益が出たケースや、1年間を通して100万円を超える利益が出たケースでは、証券会社が収益の支払い先の住所氏名、支払った金額や対象銘柄などの詳細を支払調書へ記載して、税務署へ提出します。
提出された支払調書に記載された支払い先からの確定申告がなされていない場合、無申告の可能性がある者として税務署に情報を把握されてしまうのです。
税務署では、毎年きちんと期限を守って申告・納税を行っている人々が強い不公平感を抱かないように、無申告者については厳格な対応を取っています。収益を得てから何年経っていても、税務署には状況を把握されており、いつ税務調査が来てもおかしくない状況にあると思った方がよいでしょう。
無申告が税務署にバレるとどうなるのか
株式投資で得た収入を確定申告せず、無申告を続けた場合、税務署から税務調査を実施される可能性が高まります。税務調査で無申告を指摘された場合、最大で7年前まで遡って修正申告、追徴課税の対象となってしまいます。
税金の債務は自己破産しても免れることはできないため、多額の追徴課税のリスクは大きいものです。何年も無申告を続けていた場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金といった刑事罰の対象となる可能性もあります。税務調査で指摘を受ける前に、できるだけ早く自主的に確定申告を行うようにしましょう。
株式投資による収益の税率
ここでは、株式投資によって得た収益の税率について解説します。
株式投資による収益の種類
株式投資による収益には、大きく分けて株式を売却して得る「売却益(キャピタルゲイン)」と、株式の保有によって受け取る「配当金(インカムゲイン)」とに分けられます。
売却益(キャピタルゲイン)の税率
2025年3月現在、株式の売却益にかかる税率は15.315%の源泉徴収税(所得税および復興特別所得税)と、5%の住民税の計20.315%となります。
配当金(インカムゲイン)の税率
株式の配当金にかかる税率は、上場株と非上場株で異なります。
上場株の場合は15.315%の源泉徴収税と、5%の住民税の計20.315%となりますが、非上場株式の場合は住民税なし、20.42%の源泉徴収税がかかることとなります。
参照:国税庁「株式・配当・利子と税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm
配当金への課税は確定申告で還付されるケースも
配当金が振り込まれる際、源泉徴収なしの特定口座や一般口座を利用していても、源泉徴収後の金額が振り込まれる場合があります。
確定申告が不要なケースに該当していても、配当金が源泉徴収済みの場合は確定申告することで所得税の還付が受けられます。
株式投資の利益を確定申告するには
株式投資で得た利益を確定申告する場合の手順や方法について解説します。
そもそも確定申告とは
確定申告とは、会社で年末調整された給与所得以外に一定以上の所得がある場合や、税金の還付、損益通算や損失の繰越しなどを行う際に、所得額に応じた税率で所得税を計算して税務署へ申告、納税を行う手続きのことです。
確定申告する税金には所得税や消費税、相続税や贈与税などさまざまな種類がありますが、一般的に「確定申告」と呼ぶ場合、所得税の確定申告をさすことが多いでしょう。
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの収支をもとに計算し、翌年の2月16日から3月15日(土日祝日にあたる場合は翌営業日)を申告期限として、申告書類を作成して提出、納税を行います。
税金の還付がある場合は、確定申告してから一定の期間後に、指定の振込先へ税金が還付されます。通常、郵送や窓口で直接申告書類を提出した場合は1か月から1.5か月、e-taxで確定申告した場合は3週間ほどで還付が受けられます。
株の収益は青色申告できる?
確定申告する際には、青色申告と白色申告のいずれかの方法を選択することが可能です。それぞれの主な違いは以下のようになります。
青色申告:事前に届出をすることで利用できます。申告書類作成に手間がかかるものの、特別控除や最長で3年間の損益繰越などを受けることが可能です。
白色申告:事前の届出は必要なく、青色申告に比べると申告書類もシンプルですが、特別控除や損益繰越といった特典を受けることはできません。
通常、青色申告は事業所得や不動産所得、山林所得などの申告が対象となるため、給与所得や株式投資による所得は原則として青色申告はできないこととなっています。
給与所得が2,000万円以上あり、会社で年末調整できない場合や、株式投資以外に本業として事業所得があるなど、青色申告の要件を満たしている場合は、事前に届出を行うことで青色申告での確定申告が可能です。
青色申告が利用できるメリットは大きいため、自身のケースが青色申告の要件に該当するか不安な場合は、税理士などの専門家へ問い合わせてみてもよいでしょう。
確定申告の方法
確定申告の方法には「郵送」「窓口へ直接提出」「e-taxによる申告」の3つがあります。e-taxの利用には、マイナンバーカードとスマートフォン(またはリーダーライターとパソコン)、マイナポータルの設定や利用者識別番号や電子証明書の取得など、いくつかの事前準備が必要となります。
最初の設定には手間がかかりますが、税務署で並ぶ必要なく、自宅にいながら確定申告ができる点や、税金の還付を受けられるスピードが早く、進捗状況も確認できるといったメリットがあります。
提出する確定申告書類は、税務署の窓口で入手する方法のほか、国税庁のホームページからのダウンロードする方法があります。また、確定申告書作成アプリ、会計ソフトなどを使用することでも入手可能です。
参照:e-tax「ご利用の流れ」
https://www.e-tax.nta.go.jp/start/index.htm
無申告の時期について確定申告する場合
確定申告は毎年期限が設けられており、例えば2024年の1月1日から12月31日までの所得については、翌年2025年2月17日から3月17日までが申告期限となっています。
期限を過ぎた場合も確定申告することは可能ですが、期限までに申告しなかったペナルティが課せられます。
期限を過ぎてから確定申告した場合のペナルティには、以下が挙げられます。
・延滞税:税金の納付期限の翌日から起算して、完納された日までにかかった日数に応じて加算されます。延滞税の税率は7.3~14.6%です。
・無申告加算税:期限までに申告がなかった場合に加算されます。税務調査で無申告を指摘された場合の税率は15~20%ですが、税務調査前に自主的に確定申告を行った場合の無申告加算税の税率は5%となります。
また、国税庁のホームページには、以下の要件に該当する場合は、無申告加算税がかからないことが記載されています。
“(1) その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
(2) 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次のイおよびロのいずれにも該当する場合をいいます。
イ その期限後申告に係る納付すべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
ロ その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。“
引用:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
期限を過ぎてから納付する税金の納付期限は申告した日となるため、即日納付することとなります。
無申告を放置している期間が長いほど、その分だけ延滞税がかかってしまいます。無申告を放置して税務調査となった場合、上記のペナルティに加えて過少申告加算税、悪質とみなされる場合には重加算税などの追徴課税や、刑事罰を受ける可能性も高いでしょう。
株式投資の確定申告でお悩みの場合は税理士法人松本へご相談を
「株で儲けた分の確定申告をした方がよいのかわからない」「一般口座でも確定申告しなくてよいと思い込んでいた」など、株式投資や無申告に関する不安や悩みをお持ちの場合は、1度税理士法人松本へご相談ください。
税理士法人松本には、国税OBや元税務署長の税理士が10名以上在籍しており、税務調査対策に全力で対応しています。追徴課税ゼロの実績も多数あり、お客様からも多くの喜びの声をいただいています。
税務署から調査がある旨の連絡が入ってからの相談や、追徴課税に強い不安があるといった内容も気にせずお気軽にご相談いただけます。
ご連絡は全国どこでも、ご相談予約はフリーダイヤルまたは専用フォーム、LINEなどからお気軽にお問い合わせください。
まとめ
株式投資で一定以上の収益を得た場合、原則として確定申告が必要となります。株式投資の確定申告は一般的に雑所得に分類され、配当金と売却益とは分けて考える必要があるなど、確定申告書類を作る際には迷ってしまうことも多いものです。青色申告の可能性や無申告の期間があるかもしれない場合は、税理士などの専門家への相談も検討してみましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
- 現在、税務調査が入っているので困っている
- 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
- 税務調査に強い税理士に変更したい
- 自分では対応できないので、税理士に依頼したい
税務調査の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
- 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
- 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から対応できます
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断









