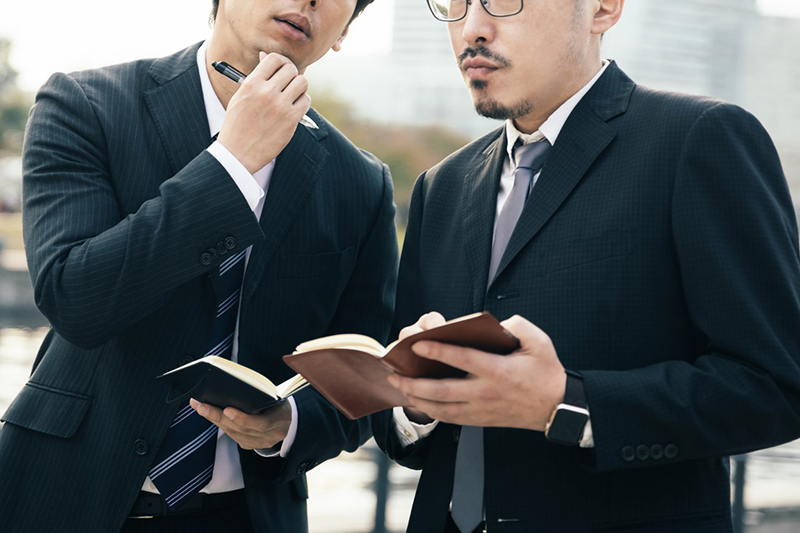メニュー
- 税務調査
- 無申告
相続税の無申告はバレる?税務調査が実施されるタイミングはいつ?

読了目安時間:約 6分
「相続をしたけれど、相続税の申告が必要になるのか分からないから申告をしていない」、「相続税は無申告でもバレないだろう」という理由で、相続税の申告をしていない人もいるかもしれません。しかし、税務署ではさまざまな情報から、相続税の無申告者の情報を掴んでおり、毎年、相続税を対象とした税務調査も実施されています。では、税務署はなぜ相続税の無申告状態であることが分かるのでしょうか。
今回は、相続税の無申告状態がバレる理由や税務調査がいつ実施されるのか、相続税の無申告者に対して税務調査が実施されやすいタイミングについてご説明します。
相続税の無申告がバレる理由とは
相続税を申告していない無申告の状態は、不正に納税をしていない状態です。相続税の無申告状態は税務署にバレます。なぜ、税務署では相続税の無申告状態を把握できるのでしょうか。
相続税の無申告がバレる理由についてご説明します。
死亡届は税務署にも通知される
人が亡くなったときには、亡くなった日から7日以内に市区町村役場に死亡届を提出しなければなりません。死亡届を受理すると、市区町村役場では戸籍に死亡した旨を記述し、住民票の抹消手続きを行います。また、死亡届を受理することで、火葬の許可証が発行され、火葬ができるようになります。
さらに、市区町村役場には、死亡届を受理した日の翌月末までに税務署に亡くなった人の情報を伝える義務があります。したがって、税務署では誰がいつ亡くなったのかという情報も把握できるのです。その際には、死亡した人が所有していた固定資産の内容やその評価額も翌月までに税務署に通知されることになります。
つまり、税務署では、死亡した翌月末までには人が亡くなったことの事実と保有していた固定資産の状況の把握ができているのです。
KSKシステムで情報を共有している
KSKシステムとは、国税総合管理システムの略称で申告や納税に関する情報を一元管理するシステムのことです。KSKシステムには、納税者の収入から納税の状況までが登録されており、国税局や税務署では納税者の情報を速やかに確認することができます。
KSKシステムには、過去の納税の状況も登録されています。そのため、市区町村役場から死亡の情報を受け取った後に、KSKシステムを使って過去の収入や所有する不動産の状況を確認すると、どの程度の財産を保有している可能性があるかを把握できるのです。つまり、税務署では死亡の報告を受けてから、相続税が発生しそうな人の目星を付けている可能性が高いと考えられるでしょう。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。通常、亡くなったことを知った日は、亡くなった日と考えることができます。したがって、相続税の申告が必要な人は、被相続人が死亡してから10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。この期間に申告をしなければ、無申告の状態となります。
税務署では、相続税の申告が必要になる可能性がある人に対し、相続税についてのお尋ねという書類を送付することがあります。このお尋ねがいつ発送されるかというと、被相続人が死亡してから4~6ヶ月後が目安となっています。お尋ねを送付する時点では、すでに税務署では、相続税の申告対象となる財産があるということを把握しており、まだ申告がなされていないことも確認していると捉えることができるでしょう。
死亡後の財産の流れを把握している
不動産を所有している人が亡くなった場合、不動産の名義変更手続きが必要です。不動産の名義変更をする際には、法務局での手続きが必要になり、法務局では税務署に登記変更がなされた旨の報告を行います。さらに、被相続人が生命保険に入っており、相続人に保険金が支払われた場合、保険会社は税務署に対して支払調書を送ります。そのため、税務署では被相続人が亡くなった後の財産の流れを把握できるようになっているのです。
また、税務署では必要があれば、金融機関に対し、預金残高やこれまでの取引履歴について照会する権利をもっています。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座も調べることができるため、被相続人が亡くなってからの口座の動きはもちろん、生前に贈与された財産についても情報を得ることが可能です。
相続税の無申告がバレた場合のリスク
相続税の申告をしていない、無申告の状態がバレた場合、税務署では税務調査を実施し、相続財産の状況について詳しく調査を行います。
税務調査の2つの種類
税務調査には、任意調査と強制調査の2種類があります。
強制調査とは、巨額の脱税が行われた場合に実施される税務調査で、裁判所の令状をもって強制的に調査が行われます。強制調査は拒否することはできません。
また、一般的に税務調査と呼ばれる調査は、任意調査に該当します。任意調査は税務署の調査官によって実施される調査で、原則として事前通知が行われ、予め調査に入る旨と調査日時についての連絡がなされます。任意調査では、日程調整は可能ですが、調査自体を拒否することはできません。任意調査の場合、調査日時に調査官が2名体制で訪れ、被相続人の自宅などで通帳などの資料の確認やヒアリングが行われます。
税務調査後には追徴課税がなされる
無申告の状態の場合、申告漏れについて指摘がなされ、正しく申告を行い、納税をするように求められます。その際、本来の相続税に加え、申告をしなかったペナルティである無申告加算税、納税が遅れたことに対するペナルティである延滞税も加算される点に注意が必要です。また、強制調査が実施されると、多くの場合は重加算税が課せられます。無申告時の重加算税の税率は40%と、その他の加算税に比べて最も重い税率となっています。
相続税の税務調査の実施件数
国税庁では、毎年、相続税の税務調査の実地件数を公表しています。
令和5年の相続税の税務調査の実施状況
令和5年に実施された相続税の税務調査の件数は、実地調査件数が8,556件となっています。実地調査件数とは、実際に調査官が訪問し、調査を行った件数のことです。
8,556件のうち、申告漏れなどが指摘された件数は7,200件にも上っており、実際に税務調査を受けた人の85%近くが、相続税を正しく申告していなかったことが分かります。
また、7,200件のうち悪質な隠蔽や仮装行為が認められ、重加算税が課された件数は971件であり、申告漏れがあった人の13.5%が重加算税の対象になっているのです。
相続税の税務調査による申告漏れ課税価格は2,745億円、追徴税額は本税と加算税を合わせて735億円にも上っています。1件当たりの申告漏れ課税価格は3,208万円、追徴税額は859万円です。
令和5年の相続税の無申告事案に対する税務調査の実施状況
相続税の申告をしていない無申告の状況は、正しく申告・納税をしている納税者に対する公平感を著しく損なうものであるとして、国税庁では相続税の無申告事案に対して積極的に税務調査をすると公言しています。
相続税の無申告状態に対して実施された実地調査の件数は、令和5年は690件です。そのうち88.8%に該当する613件に申告漏れが発覚しており、1件当たりの申告漏れ課税価格は1億899万円、追徴税額は1,787万円にも上っています。相続税の実地調査全体における1件当たりの申告漏れ課税価格は3,208万円、追徴税額は859万円であったことと比べると、無申告者を対象とした税務調査では、不正に税金を逃れようとしていた金額が大きいことが分かります。
簡易な接触の件数は18,781件
電話や文書、来署依頼による面接によって相続税の申告漏れや申告のミスなどを指摘する簡易な接触も実施されています。令和5事務年度の相続税の簡易な接触件数は18,781件で、申告漏れが発覚した件数は5,079件となっています。簡易な接触によって発生した追徴税額の合計は122億円、1件当たりの追徴税額は65万円です。
簡易な接触の場合、実地調査に比べて調査件数は多いものの、追徴税額の総額と1件当たりの追徴税額は、低くなっていることがお分かりになるでしょう。偶然、実地調査の方が多額の納税逃れをしていた人が多く、追徴税額が多くなったということは考えにくいはずです。このことから、税務署では税務調査を実施する際には、相続税の多額の申告漏れがあることを把握しており、その是正のために実地調査を実施していると考えられるでしょう。
相続税の税務調査はいつ行われる?
相続税の無申告状態である場合、税務調査の対象として選ばれる可能性が高くなります。では、相続税の申告をしていなかった場合、いつ頃税務調査が行われるのでしょうか。
相続税の税務調査が実施されやすい時期
税務署が、相続税の税務調査を実施する時期を公表しているわけではありません。しかし、相続税の税務調査が実施される時期としては、8月~11月くらいが多くなるようです。
まず、2月~3月は確定申告の時期であり、法人の多くは3月末を決算時期としているため、4月~5月は法人の申告が多く、税務署では忙しい時期であると考えられます。また、税務署の人事異動は7月にあることから、体制が整った8月ごろから相続税の税務調査を開始するケースが多いようです。
相続税の税務調査はいつ頃行われる?
次に気になるのは、相続税の税務調査は、相続が発生してからいつ頃のタイミングで行われるかということではないでしょうか。まず、相続税の時効は基本的には5年となります。相続税の申告期限は、相続が発生した日から10ヶ月以内になるため、被相続人が亡くなってから5年10ヶ月後が相続税の時効になると考えられます。
相続税の税務調査が入る可能性が高い時期は、相続税の申告後1~2年程度です。税務署では、被相続人が亡くなった翌月末までには、死亡したという事実を把握しています。そこから相続財産の状況について調べ、相続税の申告状況と照らし合わせても、相続発生から1~2年以内には調査を実施できる状態になるでしょう。
したがって、無申告状態である場合には、相続発生から1~2年の間に税務調査が実施される可能性が高くなると考えられます。ただし、相続税の時効は5年のため、その後も5年が経過するまでは、税務調査の対象になる可能性はあるといえます。
さらに、財産について改ざんや隠匿があった場合など、悪質な不正行為があった場合には相続税の時効は7年に延長されます。したがって、7年間は税務調査の対象になる可能性があるのです。
相続税の無申告でも税務調査の心配がいらないケースとは
相続が発生した場合、誰でも必ず相続税の申告が必要なわけではありません。次のようなケースは、相続税が無申告でも問題はなく、税務調査に入られる心配もありません。
相続額が基礎控除額を下回った場合
相続税には、基礎控除額が設定されており、基礎控除額より相続額が低い場合には、無申告であっても何も問題はありません。基礎控除額は次の計算式で算出できます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が1人だった場合、相続した財産が3,600万円以下のときには相続税の申告は不要です。また、法定相続人が2人だった場合は、4,200万円、法定相続人が3人の場合は4,800万円を超えなければ、相続税の申告をしない無申告の状態でも税務調査が入ることはありません。
特例や控除の活用によって相続税が0円になるケースは注意が必要
相続税にはさまざまな特例や控除制度があります。しかし、特例や控除を活用した結果、相続税が0円になった場合でも申告が必要になる場合がある点に注意必要です。例えば、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、農地の納税猶予の特例、特定計画山林の特例、相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税の特例などについては、たとえ相続税の計算額が0円になっても申告が必要となります。
まとめ
基礎控除額を超える財産を相続した場合には申告をし、相続税を納税しなければなりません。国税庁では、税の不公平を是正するため、無申告者に対する調査を強化する旨を明言しています。
税務署ではさまざまなルートから被相続人の生前の財産状況を把握しています。そのため、相続税の無申告状態の場合、税務調査が実施され、追徴課税が行われる可能性が極めて高くなるといえるでしょう。税務調査が実施される時期は、申告期限の1~2年後が多くなっていますが、いつ税務調査の対象になっても無申告状態であれば、無申告加算税や延滞税の納税が求められることに変わりはありません。そのため、相続税は正しく申告することが大切です。
-免責事項-
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
- 現在、税務調査が入っているので困っている
- 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
- 税務調査に強い税理士に変更したい
- 自分では対応できないので、税理士に依頼したい
税務調査の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
- 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
- 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から対応できます
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断