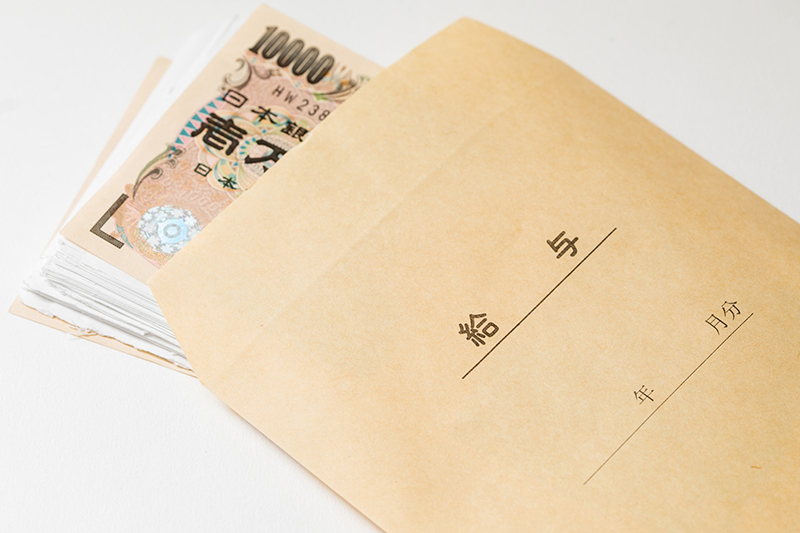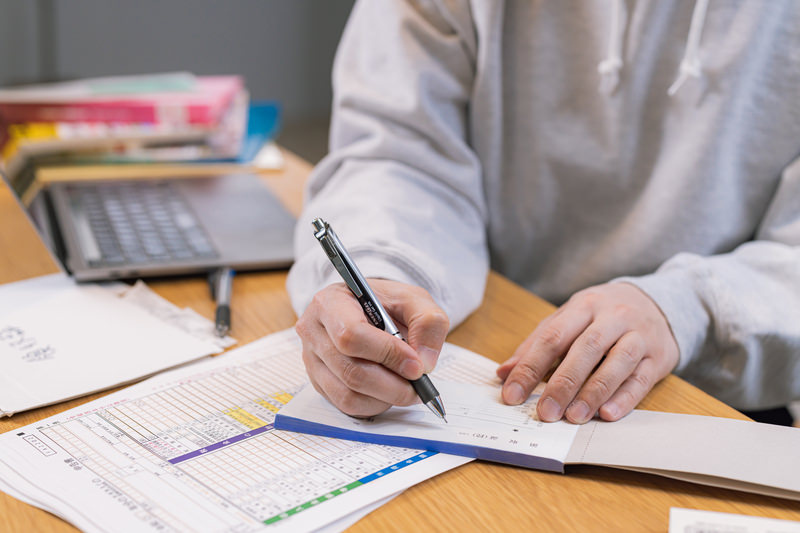メニュー
- 税務調査
税務調査で指摘されやすい売上の期ズレとは?事例や注意点を解説!

読了目安時間:約 6分
税務調査で指摘されやすいポイントの1つに、売上の「期ズレ」が挙げられるのを聞いたことはないでしょうか。期ズレとは何なのか、どのようなことが問題で、税務調査で指摘されてしまうのでしょうか。
この記事では、期ズレの概要や税務調査で指摘されやすいポイントなどを、事例を挙げてわかりやすく解説しています。税務調査に備えた注意点や対策も紹介していますので、疑問や不安の解消にお役立てください。
期ズレとは
まずは「期ズレ」とはどのような状態なのか、改めて確認していきましょう。
本来計上するべき時期がズレていること
期ズレとは、売上や経費などが本来計上するべき時期からズレてしまっている状態をさします。
当期に計上するべき売上や経費が、前年度や翌年度で計上されているような場合に「期ズレ」と呼ばれます。
個人事業主の場合は1月1日から12月31日まで、法人の場合は設定した決算日までの1年間を区切りとして、売上や経費が年度内に正しく含まれているかどうかが期ズレを判断するポイントとなります。
期ズレの理解に重要な3つの会計基準
期ズレの理解をする上で重要となるポイントの1つに、日本の会計基準として「発生主義」と「実現主義」が採用されている点が挙げられます。損益計算書の会計基準は、それぞれ以下の3つに大きく分けられます。
・発生主義
発生主義とは、売上や支払いが発生した日の日付で記帳する方法のことです。
・実現主義
実現主義とは、収益や費用が実現した日の日付で記帳する方法をさします。
・現金主義
現金による取引や、入出金日の日付で記帳する方法です。
日本の会計基準では、収益は発生主義、費用は実現主義で記帳することが原則となっています。
収益は発生主義、費用は実現主義で記帳する理由
売上は入金があった日ではなく売上が立った日付で計上し、経費は出荷日や納品日ではなく、支払いが行われた日付で計上することとなります。
発生主義に基づかないで収益の記帳をした場合、当期に売上が発生しているにも関わらず、一部入金を翌年度にまわすと売上が少ないように見えてしまいます。
また、実現主義に基づかずに費用を記帳すると、前金だけを支払って実際の納品は翌年度へまわすことで、経費が大きく見えるケースも出てしまうでしょう。
こうしたことを防ぎ、損益を正確に把握できるようにするために、原則として収益には発生主義、費用には実現主義が採用されているのです。
なお、一定の要件を満たした個人事業主であれば、現金主義による記帳も認められています。
こうした発生主義、実現主義に基づかないで記帳を行い、年度をまたいで取引が行われた場合に「期ズレ」が発生することがあるのです。
期ズレが起きやすい事例
売上や経費の記帳において、期ズレが起きやすい事例について見ていきましょう。
売上の期ズレが起きやすい事例
売上の期ズレが起きやすい事例には、以下が挙げられます。
・月の途中に締め日がある場合
月末締めで取引をしている場合、決算月においても通常通りの仕訳で月末までの売上を当期に計上することができますが、15日締めや20日締めなど、月の途中に締め日がある場合、締め日以降から月末までの売上が翌年度に計上されることとなり、期ズレが発生してしまいます。
15日締めの場合、決算月には16日から月末までの売上を当期分として記帳することで、期ズレを回避することが可能です。
・入金前に納品した場合
収益は発生主義で記帳するため、商品代金が入金される前であっても、納品のタイミングで売上を計上する必要があります。
決算月に納品した場合、入金が翌年度になったとしても、当期で売上を計上しないと期ズレとみなされてしまいます。
また、逆に納期が遅れるなどの理由で入金が当期、商品の納品が来期になる場合、売上は来期の計上となるため、入金については「前受金」などの勘定科目を使って記帳します。
入金前であっても、決算月末までに発生した売上は「売掛金」「未収金」などの勘定を使って記帳することとなります。
経費の期ズレが起きやすい事例
経費の期ズレが起きやすい事例には、以下が挙げられるでしょう。
・費用を前払いした場合
商品やサービス、備品や消耗品などの購入費用を前払いした状態で決算を迎えた場合、決算月までに受け取っていない商品やサービスについては、翌年度に計上しないと期ズレとみなされます。
・ローンで購入した商品がある場合
2回以上の分割払いで購入した商品がある場合、完済した日ではなく、商品を受け取った日で記帳する必要があります。
支払いが当期で、商品の受け取りが来期になる場合は「前払金」などの勘定科目を使って記帳します。出金前に商品が先に到着した場合は「買掛金」「未払金」などの勘定科目を使って仕訳することとなります。
税務調査で期ズレを指摘される際に知っておきたいポイント
税務調査で期ズレを指摘されやすい点や、知っておきたい知識について解説します。
税務調査で指摘されやすい売上と経費のポイント
税務調査では、売上において以下のようなポイントの指摘を受けやすくなります。
・売上を少なく計上していないか
計上漏れや計算ミスなど、売上を本来よりも少なく計上していないかはチェックされやすいポイントの1つです。
・期ズレが起きていないか
上記で挙げたようなケースを踏まえて、期ズレが起きていないかどうかは、税務調査でチェックされやすいポイントといえるでしょう。
また、経費において指摘されやすいポイントとしては以下が挙げられます。
・私的な支出を流用していないか
特にプライベートの外食や旅行、プレゼントなどを経費として計上していないかは、しっかりと調査されることが多いでしょう。
・期ズレが起きていないか
経費においては、前倒し計上などの期ズレが起きていないかをチェックされることとなります。
知っておきたい「費用収益対応の原則」
費用と収益は同時に発生する訳ではなく、例えば仕入れた商品を販売して売上が出る、といったように、先に費用が発生し、後から収益化するのが一般的な流れとなります。日本の会計基準としても、費用は実現主義、収益は発生主義で記帳することは上記で解説した通りです。
利益が出るまでには一定の期間が必要となり、費用と収益の発生には計上時期にズレが生じるため、どれだけの費用に対して収益が得られたのかがわかるようにしておかなければ、適正な損益計算が難しくなってしまいます。そこで、日本の会計基準では「費用収益対応の原則」も採用しています。
費用収益対応の原則では「売上と原価は対応させなければならない」とさだめられています。対応方法は、次の2つに分けられます。
・個別対応
費用と収益の関係がはっきりしている場合の対応方法です。例えば、特定の期間中に100個仕入れた商品を60個販売した場合、その期間中に生じた収益に対応する費用は商品60個分となります。
・期間対応
費用と収益の関係が曖昧な場合の対応方法です。例えば、家賃や広告宣伝費など、商品の売上高に直接関連のない費用については、1つの年度で区切って対応させることとなります。
上記の対応にならって会計処理を行う場合、翌年度に収益が出る予定の売上に対応する費用は翌年度の計上となります。税務調査で翌年度分として計上された売上が期ズレにあたると指摘された場合でも、対応する売上原価も翌年度分で計上されている場合、修正申告しなくてもよい(認容)とみなされる可能性があることは知っておくとよいでしょう。
税務調査で期ズレを指摘されるとどうなる?
税務調査で期ズレを指摘された場合にどうなるのかについて解説します。
修正申告の対象となる
税務調査で期ズレを指摘された場合、ズレている分の売上について修正申告をすることとなります。
なお、修正申告は税務調査で指摘される前に、気づいた時点で自主的に行うことも可能です。入金があるまで売上に気づかず、決算後の入金で売上の計上漏れに気づくケースはよくあるため、気づいた時点で修正申告することで、故意の申告漏れなどが疑われるリスクの回避に繋がります。
追徴課税の対象となる
税務調査で意図的に期ズレさせ、売上の申告を少なくしたとみなされた場合、漏れていた売上分の税金に加え、過少申告加算税や延滞税などの追徴課税の対象となってしまいます。
悪質とみなされた場合には、重加算税などのさらに重いペナルティの対象となる可能性もあるため要注意です。
更正処分を受ける
更正とは、税務調査後の指摘によって修正がなされていない申告について、税務署が税額を決定する処分のことです。税務調査で修正申告となった内容について納得がいかない場合、更正処分となるのを待ってから異議申し立てなどの手続きを取ることが可能となります。
ただし、異議申し立てをしたからといって確実に言い分が通る訳ではない点に注意が必要です。
異議申し立てが却下や棄却となったり、税務訴訟へ発展して相当の期間や弁護士費用などが発生したりするリスクがあることも知っておきましょう。
税務調査で期ズレを指摘されないための対処法
税務調査で期ズレを指摘されないための対処法について解説します。
会計原則を理解して記帳する
発生主義や実現主義、費用収益対応の原則などについての基本知識を身につけることは、適正な申告、納税を行う上でも重要となります。
可能であれば1度税理士などの専門家へ相談するなどして、自身の理解に間違いがないかを確認してみることをおすすめします。専門家へ相談する際にも、基礎知識があるかどうかで質問の精度が変わり、専門家からもらえる回答の理解度も高まります。思い込みによる記帳の間違いなども防げるため、相談前にこの記事のような情報に軽く触れておくこともおすすめです。
計算ミス、間違いをなくす
記帳の原則を理解していても、ちょっとした計算ミスや勘定科目の選び間違い、借方と貸方を逆に記帳するといったケアレスミスがあれば、修正申告の対象となってしまいます。
「わざとではなかった」と主張しても、間違いについては修正申告が必要です。
多数のケアレスミスがあると、意図的な帳簿操作などを疑われるリスクにも繋がるため、書類提出前には見直しやダブルチェックを行うようにしましょう。
期ズレを指摘された際の受け答えをシミュレーションしておく
税務調査で期ズレを指摘された場合でも、費用収益対応の原則などに基づいて、対応する売上原価が翌年度で計上されていれば認容できるものとして主張できます。調査官からの質問や指摘に対してどのように対応するかのシミュレーションを事前に行うことは、毅然とした対応を取れるようにしておくためにも重要です。
税務調査の際、調査官から売上原価に関する指摘がなかった場合でも、売上と仕入れはセットで考えるということが把握できていれば、期ズレを指摘された際の受け答えについてシミュレーションしやすくなるでしょう。
期ズレの税務調査が不安な場合は税理士法人松本へご相談を
「税務調査の時に毅然と主張したり、交渉したりできる自信がない」「そもそも申告内容が正しいかどうかも不安」といった不安や悩みがある場合は、1度税理士法人松本へご相談ください。
税理士法人松本には、国税OBや元税務署長の税理士が10名以上在籍しており、税務調査の対応はもちろん、期ズレやその他の修正申告サポートなどにも対応しています。
税務調査の連絡を受けてからの相談や、顧問税理士には相談しにくいと感じるような内容などにも親身に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
ご連絡は全国どこでも、ご相談予約はフリーダイヤルまたは専用フォーム、LINEなどからお気軽にお問い合わせいただけます。
まとめ
期ズレとは本来計上するべき年度に売上や経費が計上されておらず、前年度や翌年度にズレてしまっているとみなされる状態をさします。税務調査では期ズレは必ず確認される事項の1つとなっているため、会計原則の知識に基づいた処理が重要となります。
期ズレを指摘されても、売上原価に対応した仕訳となっている場合には、認容となるケースも少なくありません。会計に関する基本的な知識を身につけてミスや間違いに留意し、必要に応じて税理士などの専門家のサポートも受けて適正な申告、納税を行いましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
- 現在、税務調査が入っているので困っている
- 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
- 税務調査に強い税理士に変更したい
- 自分では対応できないので、税理士に依頼したい
税務調査の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
- 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
- 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から対応できます
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断