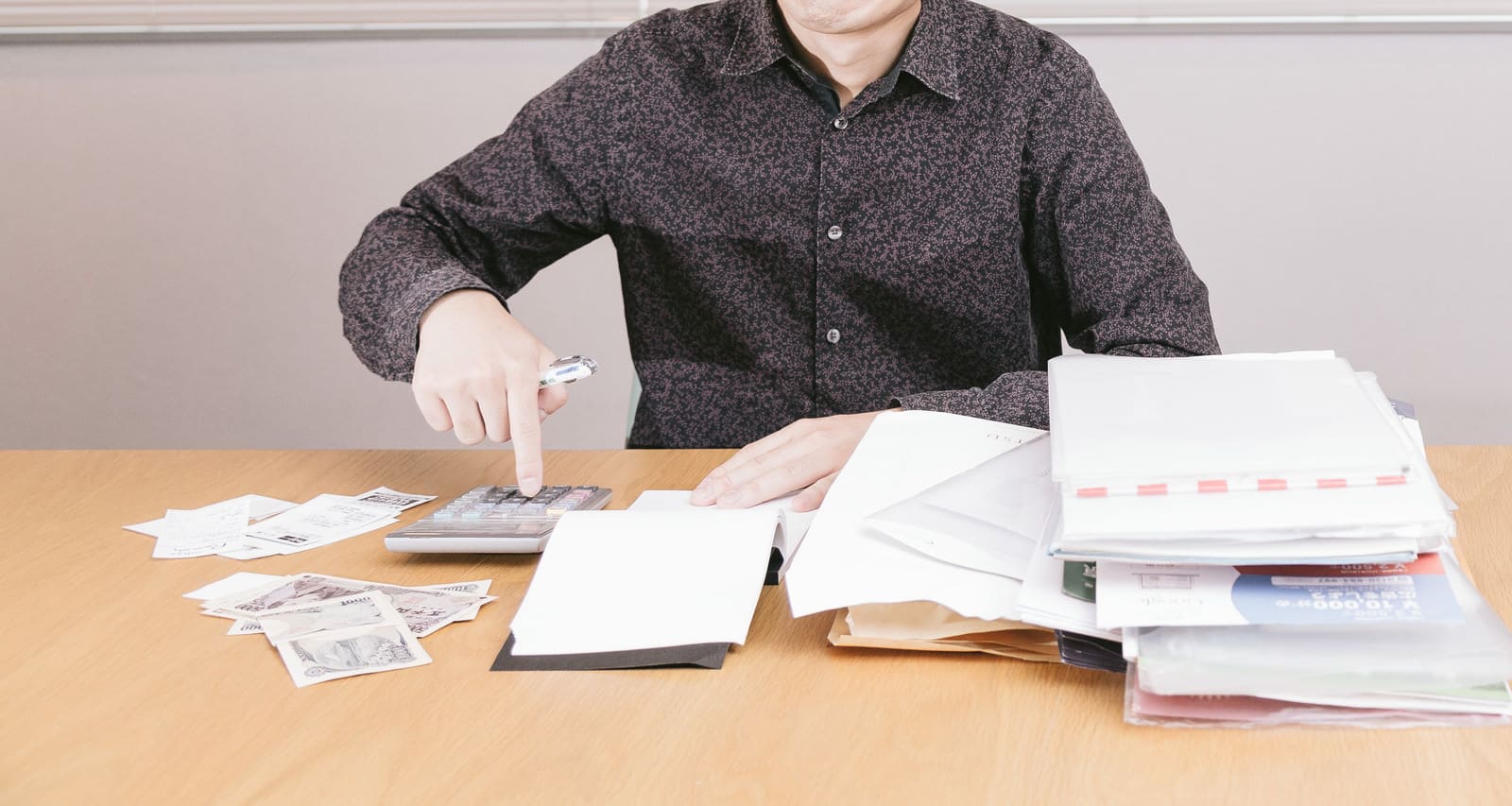メニュー
- 無申告
- 期限後申告
確定申告の期限に遅れた場合はどうなる?リスクや対処法を解説

読了目安時間:約 6分
法人の場合も個人の場合も、確定申告ができる期間は決まっています。つまり、確定申告は決められた期間内に行わなければなりません。そのため、確定申告をする際には期限を確認し、定められた日までに確定申告を済ませられるよう準備を進めることが大切です。
しかし、何らかの事情によって期限までに確定申告ができず、遅れることもあるかもしれません。では、確定申告に遅れた場合はどうなるのでしょうか?
今回は、確定申告の期限に遅れた場合のリスクや遅れた場合に取るべき対処法などについてご説明します。
目次
確定申告の期限とは
確定申告の期限は、法人であるか個人であるかによって変わってきます。法人税の場合、確定申告は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。また、個人の所得税の確定申告の期間は、原則として毎月2月16日から3月15日と決まっています。ただし、2月16日や3月15日が土曜、日曜、祝日に重なる場合は、次の平日が期日となります。
確定申告の期限は提出方法によっても変わります。税務署の窓口に直接持参する場合は、確定申告の期限となる日の17時までに提出が必要となります。ただし、時間外の収受箱に投函する場合は、翌日の開庁時間までに投函すれば問題ありません。確定申告の書類を郵送する場合は、提出期限日の消印までが有効です。e-Taxを使い、オンラインで提出する場合の期限は、提出期限日の24時を超えるまでとなります。
確定申告が遅れた場合のリスク
確定申告が遅れた場合、次のようなペナルティが科せられる可能性がありますが、確定申告の期日に遅れた場合でも、納税が免除されるわけではありません。したがって、確定申告が遅れたときはできるだけ早く書類を作成し、申告を行う必要があります。
確定申告が遅れた場合に生じるリスクは、次のようなものです。
無申告加算税が課される
無申告加算税とは、確定申告が遅れたことに対して課せられるペナルティの税金です。確定申告をしなければ、納めるべき税金の額が確定せず、必要な納税も行えなくなってしまいます。無申告加算税の税率は、納めるべき税額が50万円までの部分に関しては15%、50万円を超え300万円以下の部分は20%、300万円超の部分に関しては30%です。
ただし、確定申告の期限に遅れた場合でも、税務署からの指摘を受けず、期限後に自主的に申告を行った場合は、無申告加算税の税率は5%にまで軽減されます。また、税務署から税務調査の事前通知を受けて、税務調査の前までに自主的に期限後申告をした場合も、無申告加算税の税率は50万円までは10%、300万円までは15%、300万円以上は25%とする軽減措置が用意されています。
延滞税が課される
確定申告が遅れた場合、納税も遅れることになります。延滞税は、納税が遅れたことに対して科せられるペナルティで、遅れた分の日数に応じた利息に相当する額の納付を求められる加算税です。
延滞税の税率は、法定納期限の翌日から納税を完了する日までの日数に応じて次のように変わります。
・法定納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
具体的な延滞税の税率は次のとおりです。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は、年2.4%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%
・法定納期限の翌月から2ヶ月を経過した日以降
年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合
具体的な延滞税の税率は次のとおりです。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は、年8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%
個人の場合は青色申告特別控除が減額される
青色申告をしている個人の場合、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。青色申告特別控除を受けられれば、控除額分を利益から差し引くことができるため、所得額を抑えられ、節税につながります。しかし、65万円もしくは55万円の青色申告特別控除を受ける要件の1つは、期限内に確定申告を行うことです。そのため、確定申告の期限に遅れた場合には、65万円または55万円の控除は適用されません。ただし、期限に遅れた場合でも確定申告をすれば10万円分の青色申告特別控除を受けることは可能です。
法人の場合は青色申告の承認が取り消される場合も
法人が2期連続で確定申告の期限に遅れた場合、つまり事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に確定申告を行わないことが2年続いた場合、青色申告の承認が取り消されます。青色申告の承認が取り消された場合、1年間、青色申告の申請をすることができません。青色申告の承認が取り消された場合、赤字があった場合の繰り越し控除も適用できなくなるなど、さまざまなデメリットが生じます。
確定申告が遅れた場合でも無申告加算税が課されないケース
期限内に確定申告を行わなかった場合でも、無申告加算税が免除されるケースがあります。それは、次のような要件を満たしている場合です。
やむを得ない理由で期日までに申告ができなかった場合
大きな地震が起きた場合など、自然災害が理由で期日までに確定申告ができない場合があります。また、コロナウィルスの感染拡大があったように、感染症などの流行によって期限までに確定申告ができない場合など、やむを得ない理由がある場合には申告期限の延長申請をし、承認を受けることで無申告加算税が免除されます。また、自然災害などの影響によって期限に遅れる人が多くなると想定される場合には、特に個別の手続きをしなくても、国税庁長官が指定した地域の申告期限が延長されるケースもあります。
法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告をした場合
確定申告に遅れた場合でも、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告をした場合、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当していれば、無申告加算税が免除されます。
期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合とは、次のすべての条件を満たす場合です。
・期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付している
・期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがない
つまり、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、確定申告書を提出はしていないものの、税金の納付は済ませており、確定申告の期限後1ヶ月以内に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税は課されないということです。しかしながら、確定申告書の提出が遅れても、納税は遅れることなく期限までに済ませるケースというのは、極めてレアケースになるといえるでしょう。
確定申告が遅れた場合はできるだけ早く期限後申告をする
確定申告が遅れた場合は、無申告加算税や延滞税の納税が求められます。しかしながら、前述のように、税務調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は5%にまで軽減できます。
税務調査が実施される前には、原則として、税務署から事前に税務調査に入る旨の電話連絡が入ります。この連絡を事前通知と言いますが、事前通知を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合には、納税の意思が認められるために無申告加算税が軽減されるのです。また、事前通知を受けた後でも、税務調査が実施される前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税の税率を軽減する措置もあります。
加えて、延滞税は日割り計算で課せられる税金です。そのため、税金の納付が遅れれば遅れるほど延滞税の税率は高くなります。したがって、無申告加算税の負担も、延滞税の負担もできるだけ少なく抑えるためには、確定申告に遅れたことに気が付いた時点で、早めに期限後申告をすることが重要なのです。
事情があって確定申告が遅れる場合の対処法
さきほど、やむを得ない理由がある場合には、無申告加算税が免除されるケースがあるとご紹介しました。また、次の事情があり、期限までに納税が難しい場合は、所得税、消費税、地方消費税の納税の猶予が認められる可能性があります。納税猶予が認められる可能性があるのは、次の1から4までに掲げる要件のすべてに該当するときです。その場合、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められます。
1. 次の(1)から(6)までのいずれかに該当する事実があること。
(1) 財産について、災害を受けたり、盗難にあった
(2) 納税者や家族が病気にかかったり、負傷した
(3) 事業を廃業したり、休業した
(4) 事業について著しい損失を受けた
(5) 上記の(1)から(4)に類する事実があった
(6) 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した
2. 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
3. 申請書が提出されていること
4. 原則として、担保の提供があること
ただし、次のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合
- 担保として提供することができる種類の財産がない場合
猶予を受けた税金は、原則として猶予期間中の各月に、分割して納付することとなります。しかしながら、猶予期間内に完納することが難しいやむを得ない理由が認められる場合は、申請によって、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で、猶予期間の延長が認められます。
病気や怪我、災害、盗難、事業の著しい損失などによって納税が遅れそうな場合には、早めに税務署に相談することをおすすめします。
所得税の納税が難しい場合の対処法
確定申告の期限内に所得税を納税することが難しい場合は、延納制度を利用することも可能です。延納制度を利用すると、確定申告の期限までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日までに延長することができます。ただし、延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。そのため、どうしても期日までの所得税の納税が難しい場合は、延納制度の利用も検討しましょう。
延納を希望する場合は、確定申告書を作成する際、申告書の第一表「延納の届出」の欄に、延納届出額と申告期限までに納付する金額を記入することで申請ができます。
確定申告を期限内に行うためには
確定申告は、決められた期日までに遅れずに行うことが大切です。確定申告が遅れた場合、無申告加算税や延滞税が課せられるため、本来よりも多い額の税金を支払わなければなりません。また、個人事業主の場合は、確定申告に遅れると青色申告特別控除の控除額が減ってしまい、結果として納税額が増えてしまいます。さらに、法人の場合には2期連続で確定申告に遅れると、青色申告の承認が取り消されてしまうというリスクも生じます。
確定申告は、特別な事情がない限り、期限内までに行うことが大切です。そのためには、日頃から正しく帳簿を付ける、書類を管理しておく、といった処理が重要になります。
また、忙しくて確定申告書を作成する時間が確保できないという場合は、税理士への相談をおすすめします。税理士に依頼した場合、税理士に支払う報酬が発生しますが、正しい確定申告書の作成ができ、期日までに確実に申告できるようになるでしょう。さらに、節税についてのアドバイスがもらえる可能性があるため、負担する報酬以上のメリットを得られる可能性があります。
確定申告が遅れた場合も早めに税理士に相談を
うっかり確定申告を忘れていた場合や忙しすぎて期日までに確定申告が終わらなかった場合などは、できるだけ早く期限後申告をすることが大切です。税務調査の前であれば、自主的に期限後申告をすることで無申告加算税の税率は軽減されます。処理すべき内容が多い場合や確定申告のやり方が分からない場合などは、税理士に相談するとスピーディーに期限後申告を終わらせることが可能です。
確定申告は遅れれば遅れるほど延滞税の負担が大きくなります。できるだけ早めに期限後申告を済ませるようにしましょう。
まとめ
確定申告の期限に遅れた場合には、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課されます。また、個人事業主の場合には青色申告特別控除の減額、法人の場合には青色申告の承認が取り消されるリスクもある点に注意が必要です。
やむを得ない理由があり、確定申告が遅れそうなときには、税務署に相談をすることで納税が猶予されたり、延納が認められたりする可能性があります。期日までの納税が難しい場合などは、早めに税務署に相談してみましょう。
-免責事項-
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
- 現在、税務調査が入っているので困っている
- 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
- 税務調査に強い税理士に変更したい
- 自分では対応できないので、税理士に依頼したい
税務調査の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
- 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
- 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から対応できます
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断