メニュー
- 税務調査
- 無申告
相続税の無申告の時効は何年?申告しなくてもバレない?
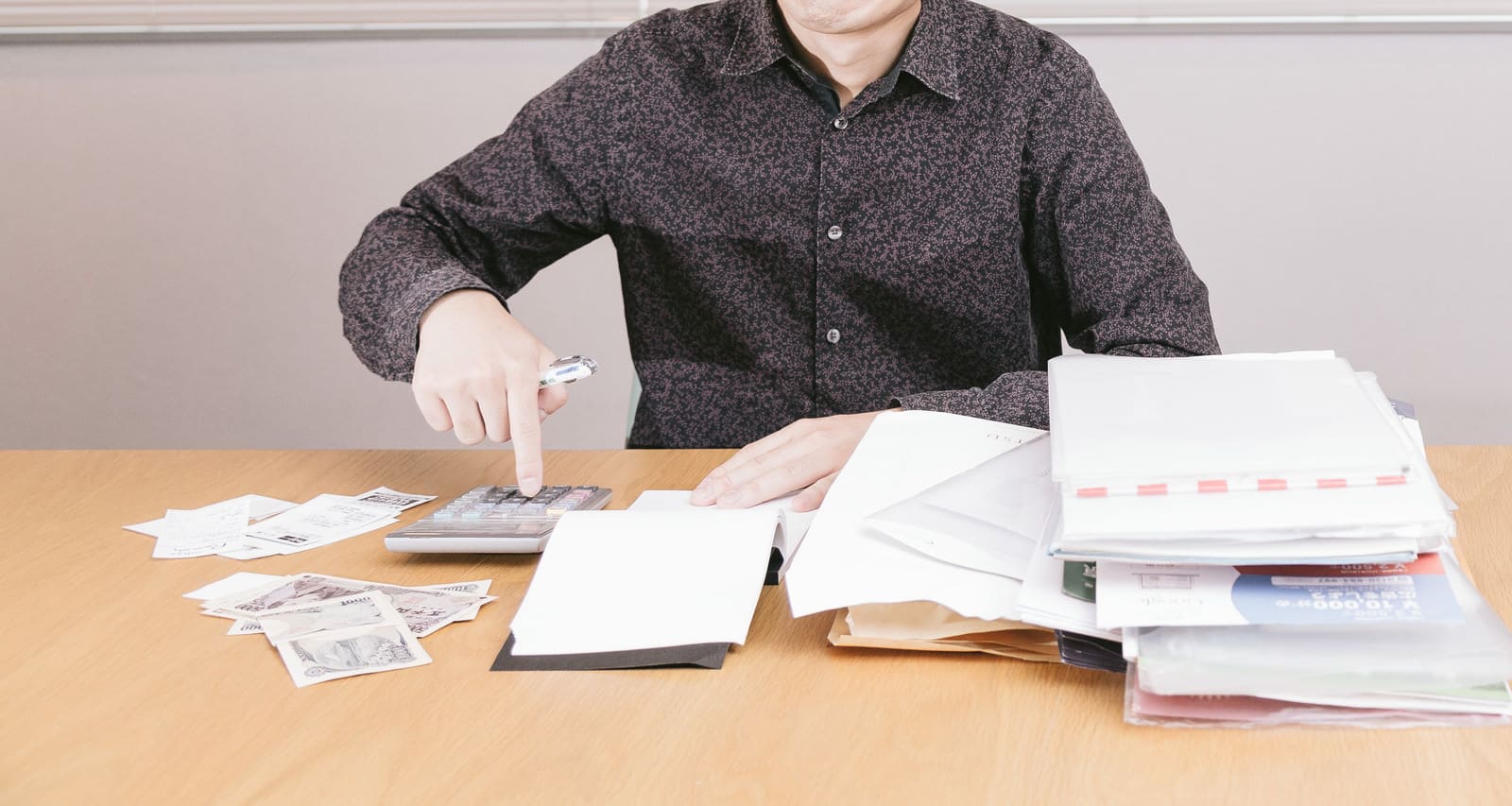
読了目安時間:約 7分
相続税の対象となる財産を相続した場合、相続税の申告をしなければなりません。しかし、人が亡くなったときは、さまざまな手続きが必要になり、忙しく過ごすケースがほとんどです。そのため、相続税の申告手続きをうっかり忘れ、無申告状態となっている人もいるかもしれません。また、中には相続税の負担を避けたいと考え、時効が成立するまで待てば、納税を免れるのではと期待している方もいるようです。では、相続税の無申告には時効があるのでしょうか。
今回は、相続税の無申告の時効などについてご説明します。
目次
相続税とは
相続税とは、親など、亡くなった人から財産を相続した場合に課せられる税金のことです。まずは、相続税の概要から確認しましょう。
相続税の対象
相続した財産がすべて相続税の対象になるわけではありません。相続税がかかる財産は、金銭に見積もることができる次のようなものに限定されます。
・預貯金
・株式などの有価証券
・土地や建物などの不動産
・貴金属 など
相続税がかかる財産の額
相続税は、基礎控除額以上の遺産を相続する場合に発生します。相続財産の基礎控除額は、3,000万円と法定相続人1人につき600万円を足した額で算出します。したがって、法定相続人が1人の場合は3,600万円、法定相続人が2人の場合は、4,200万円以上の相続財産がある場合、相続税の手続きと納税が必要となります。
相続税の申告手続き
基礎控除額を超える財産を相続した場合、相続税の納税が必要です。相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所を管轄する税務署に申告をし、納税を行わなければなりません。つまり、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内となります。
相続税の無申告とは
相続税の無申告とは、相続税の申告が必要な財産を相続したにもかかわらず、申告を行わない状態のことです。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月となるため、この間に相続税の申告と納税をしなかった場合は相続税の無申告状態となります。
相続税の無申告の時効は何年?
相続税の申告をしない無申告の場合、時効は成立するのでしょうか。
時効とは
時効とは、ある出来事から一定の期間が経過したことで、法律上の権利を確定させることです。刑事事件の場合は、時効が成立すると、検察官は被疑者を起訴できなくなります。
また、民事事件の時効には、取得時効と消滅時効の2つがあります。取得時効とは、一定期間以上、ある物を占有することで、その物の所有権を取得できるというもので、消滅時効とは、一定期間行使されなかった権利を消滅させることです。
相続税の時効について
相続税の時効とは、一定の期間が過ぎることで、国が国税である相続税の納税を求める権利を失うことを意味します。相続税の無申告の時効が成立すると、国は納税を求めることができないため、納税者は相続税を払わずに済むようになります。
相続税の無申告の時効は原則として5年
相続税の時効は、原則として5年です。先ほど、相続税の申告期限は相続が発生してから10ヶ月後であることをご説明しました。したがって、相続税の時効は、申告期限の5年後となります。
国税通則法第70条1項には、次のように記載があります。
(国税の更正、決定等の期間制限)
第70条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があったものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
この条項から、国税である相続税の時効は申告期限の5年後ではと考えられるのです。
相続税の無申告の時効が7年になる場合もある
相続税の無申告の時効は、原則として5年です。しかし、時効が2年延び、7年になることもあります。
それは、不正に納税を免れようとした場合です。相続税の申告が必要であることを知らずに、相続税の申告をしていなかった場合の時効は5年になりますが、申告の必要性を知っていたにもかかわらず、申告をしていなかった場合には、時効が7年となるのです。
相続税の無申告は時効まで待てばバレない?
相続税の無申告に時効があるのであれば、時効が成立するのを待つことで納税を免れるのではと思うかもしれません。実際、相続税の無申告状態でも時効は成立するものなのでしょうか?
相続税の無申告の時効が成立するケースはほとんどない
結論から申し上げると、相続税の納税をしない無申告の状態で、時効が成立するケースはほとんどありません。税務署では、あらゆる情報ネットワークを駆使し、相続に関する情報を収集しています。そのため、相続税の無申告が時効を迎えるまでにバレないケースはほとんどないのです。
相続税の税務調査実施件数とは
相続税の無申告状態が疑われる場合、税務調査が行われます。税務調査では、税務署の調査官が相続人の自宅などを訪れ、相続の状況について詳しい調査を実施するものです。
国税庁が令和6年12月に公表した「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」を見ると、令和5年に実施された相続税の税務調査の実施件数は、8,556件にも上っています。このうち、申告漏れなどが指摘された件数は、7,200件にも上っており、実に、税務調査を受けた84.2%の人が相続税の申告内容の誤りを指摘されているのです。
また、調査官が訪問して対面式で行う調査とは別に、電話や書面、来署による面接などによって相続税についての問い合わせを行う、簡易な接触も行われています。相続税の簡易な接触は、令和5年には18,781件も実施されており、このうち、申告漏れなどの指摘を受けた件数は5,079件に上っています。
税務調査と簡易な接触を合わせた、令和5年1年間の相続税に関する調査実施数は27,337件にもなるのです。
相続税の無申告の時効は成立しない理由とは
相続税の無申告の時効は、成立するケースはほとんどないとご説明しましたが、では、なぜ相続税の無申告の時効は成立しないのでしょうか。
それは、時効を迎えるまでに、相続税の申告をしていないことが税務署にバレるからです。税務署では、相続税に関するさまざまな情報を把握しており、無申告の相続人を対象に税務調査を実施しています。なぜ、税務署に無申告がバレるのか不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。税務署は次のような理由から相続税の無申告状態を把握できるのです。
死亡届の情報は税務署にも通知される
まず、相続が発生する状況は、誰かが亡くなったということです。人が亡くなったときには、亡くなったことを知ってから7日以内に市区町村役場に死亡届を提出しなければなりません。市区町村役場は死亡届を受理すると、税務署にも通知しなければならないことが法律で決められています。また、死亡届が税務署に通知される際には、被相続人が保有する不動産に関する情報も通知されています。
したがって、税務署では、被相続人が亡くなったことも被相続人が所有していた不動産の情報も迅速に把握できる仕組みになっているのです。
KSKシステムで納税状況を把握している
全国の国税局と税務署をネットワークで結び、申告や納税の実績などを共有できる国税総合管理(KSK)システムでは、被相続人の生前の納税状況についてのデータも蓄積されています。つまり、税務署では生前にどの程度、どのような所得を得ていたのか、税務申告の情報を把握しているのです。
会社に勤めていた場合や会社を経営していた場合は、給与や役員所得、退職金の額までKSKシステムには記録されています。また、不動産経営をしていた場合は不動産所得、不動産や株式を売却した場合の譲渡所得などについても記録されているため、亡くなったときに、どの程度の財産を所有していたか、推測することができるのです。
市区町村役場からの死亡届を受け取ると、税務署ではKSKシステムを使い、過去の納税状況などを調べます。そのうえで、法人税の申告書が提出されているか、また提出された申告書の内容と生前の所得の状況、不動産の保有状況などが大きく乖離していないかをチェックするのです。したがって、相続税の申告書が提出されていない無申告状態の場合、時効を迎えることなく、無申告であることがバレることになります。
税務署は金融機関の情報も把握できる
税務署は、税務調査に必要な情報であれば、本人の同意がなくても、金融機関に対し、対象者の取引情報の開示を求める権利があります。そのため、相続税の無申告が疑われる場合は、亡くなった被相続人の銀行口座だけでなく、財産を相続した相続人の口座を調べることも可能です。そのため、被相続人が生前に、相続人に財産を贈与した場合などの情報を調査することもできます。
2024年1月から、生前贈与であっても相続開始前7年以内の贈与は、相続税の課税対象として扱うこととなりました。したがって、銀行口座の動きから生前贈与が認められれば、生前贈与の分に関しても相続税の対象として申告がなされているか、調査が行われることになります。
相続税の無申告がバレた場合のリスク
相続税の無申告は時効を待たずにバレるケースがほとんどです。では、無申告がバレた場合はどのようなリスクがあるのでしょうか。
無申告加算税が課される
無申告加算税とは、期限内に申告を行わなかった場合に課せられるペナルティです。所得税の確定申告を行わなかった場合も無申告加算税は課されますが、相続税も期限までに申告・納税をしなかった場合、無申告加算税が課されます。
無申告加算税の税率は、税額が50万円以下の部分は15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%です。正しく期限までに申告していた場合、無申告加算税が課されることはありません。しかし、時効が成立するのを待つ間に無申告であることがバレれば、無申告加算税が課されるために、本来よりも多くの相続税を納めなければならなくなってしまいます。
重加算税が課される
重加算税とは、悪質な仮装・隠蔽行為が認められた場合に加算される税金です。相続税を申告していなかった場合に課せられる重加算税の税率は40%であり、重加算税が課せられると正しく申告をしていた場合の1.4倍もの納税をしなければならなくなります。
延滞税が課される
延滞税は、納税が遅れたことに対して課せられるペナルティです。延滞税の税率は、納付期限の翌日から2ヶ月以内と、2ヶ月を経過した場合とで変わり、納税が完了するまで日割りで課されるという特徴があります。
相続税の時効を待つと納税額が増える
相続税の時効は、原則として5年です。しかしながら、ご説明してきたように、税務署はさまざまなルートで情報収集をしています。そのため、相続税の申告義務があるにもかかわらず、申告を行わない場合、時効が成立する前にバレることがほとんどです。
時効が成立するかもしれないと無申告状態を続けると、その間、延滞税が課され続けます。また、無申告加算税の納税も求められます。そのため、相続税の納税額をできるだけ抑えたいのであれば、時効を待つのではなく、期限までに正しく申告を行うべきなのです。
相続税の申告をしていない人は早めに期限後申告を
相続税の無申告を続けても、時効が成立する可能性は極めて低く、時効を待つ間に課せられるペナルティの額はどんどん増えていきます。そのため、何らかの理由で相続税の申告をしていない場合は、時効を待たずにできるだけ早く期限後申告をするようにしましょう。
自主的な期限後申告で納税額の負担を軽減できる
税務調査で相続税の無申告が発覚した場合、前述のように無申告加算税が課せられます。しかし、税務調査が実施される前に自主的に期限後申告を行うと、無申告加算税の税率は軽減される措置があります。
税務署から事前通知を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合の無申告加算税の税率は5%にまで軽減されます。また、事前通知を受けた後でも、税務調査が実施される前に自主的に期限後申告を行うと、5%ずつ税率が軽減され、50万円までの部分については10%、50万円超300万円未満の部分については15%、300万円超の部分については25%となるのです。
ペナルティを最小限にとどめるためにも、無申告状態であることに気が付いた時点でできるだけ早く期限後申告を行うことをおすすめします。
時効を待つことで親族に迷惑をかける場合も
相続人が複数おり、そのうちの誰かが相続税の無申告を続けた場合、他の相続人が代わりに納税をしなければならないというルールがあります。例えば2人の相続人がおり、そのうち1人が相続税の納税をしない場合、正しく申告をしていたもう1人の相続人に、未払い分の相続税の納税が求められるのです。親族に迷惑がかかるのを避けるためにも、相続税の申告をしていないのであれば、早めに期限後申告を行うようにしましょう。
まとめ
相続税の無申告の時効は、原則として5年です。ただし、悪質な場合は時効が7年まで延長されます。しかしながら、相続税の時効が成立するケースはほとんどありません。なぜなら、税務署には市区町村役場から死亡届の情報が共有され、税務署は、被相続人の生前の納税状況についても把握ができるからです。また、銀行口座などについても調査を実施できるため、時効が成立する5年もの間、相続税が無申告状態であることが税務署にバレないということは考えられません。
無申告状態を続ければ続けるほど、重いペナルティが課せられます。少しでも納税額を抑えたいのであれば、税務調査が入る前に自主的に期限後申告を行うようにしましょう。
-免責事項-
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
- 現在、税務調査が入っているので困っている
- 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
- 税務調査に強い税理士に変更したい
- 自分では対応できないので、税理士に依頼したい
税務調査の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
- 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
- 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から対応できます
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断









