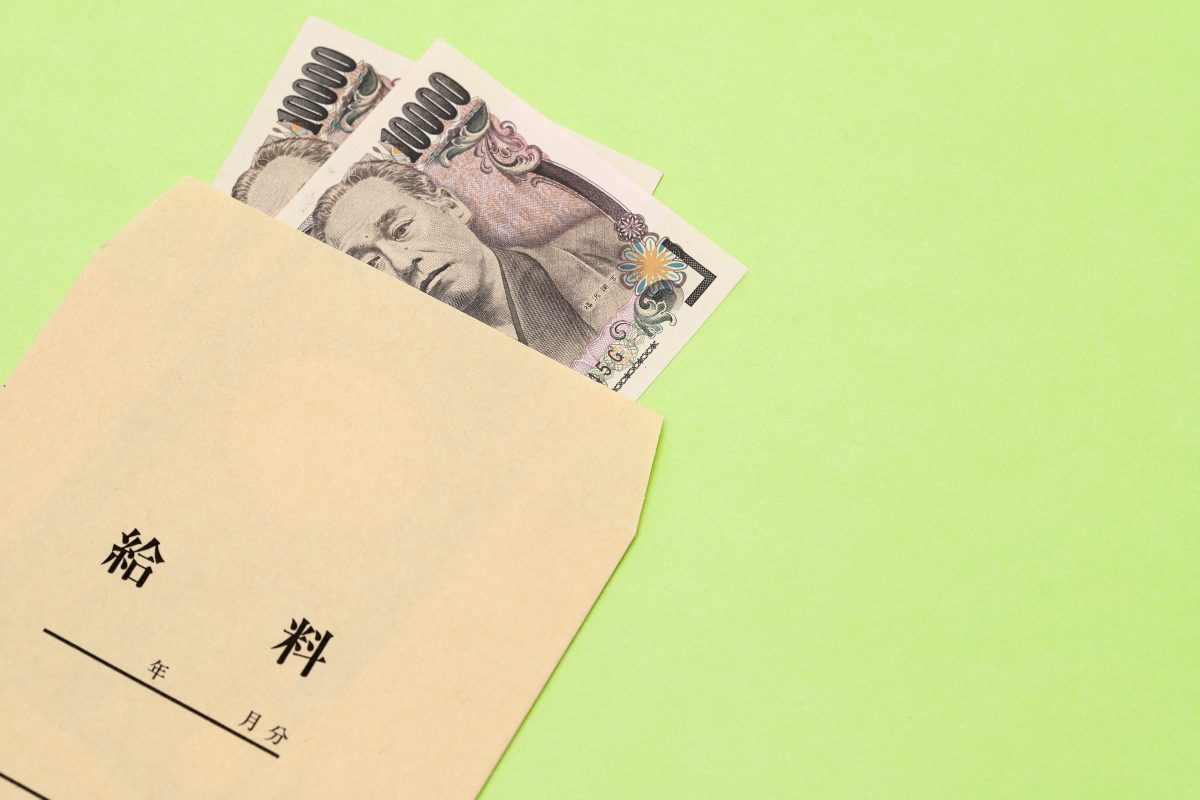メニュー
- 税務調査
法人が税務調査を受ける確率と調査をスムーズに終えるための対策

読了目安時間:約 6分
法人の経営者にとって、税務調査はできるだけ避けたい調査でしょう。なぜなら、税務調査の対象になった場合、申告内容の不備を指摘される可能性があり、修正が求められれば、追徴課税の可能性が高くなるからです。では、法人が税務調査の対象として選ばれる確率はどのくらいあるのでしょうか。また、税務調査の対象に選ばれた場合、調査をスムーズに終えるためにはどのような対策をすべきなのか気になる方も多いかもしれません。
そこで今回は、法人に対して税務調査が実施される確率と税務調査をスムーズに終えるための対策についてご紹介します。
法人を対象に行われる税務調査とは
まず、法人を対象に実施される税務調査の概要から確認していきましょう。
強制調査と任意調査について
税務調査は大きく分けると、国税局査察部によって実施される強制調査と税務署の調査官によって実施される任意調査の二種類があります。
まず、強制調査とは、裁判所の令状を持って強制的に行われる調査で、事前に調査についての通知がなされることはなく、予告なしで調査が開始されます。巨額な税逃れが疑われる場合や悪質な仮装・隠蔽が疑われる場合に実施される調査が強制調査となります。
一方、一般的に税務調査と呼ばれる調査が任意調査です。任意調査は、原則として事前通知が行われ、税務調査を実施する日時や調査対象となる税目などについて、電話で連絡が行われます。任意調査も調査を拒否することはできませんが、日程の都合がつかない場合は日程調整をお願いすることが可能です。
法人の税務調査の対象税目と対象期間について
法人に対して税務調査が実施される場合、法人税が主な調査対象税目となり、消費税や、源泉所得税などの調査も同時に実施されることになります。また、法人を対象とした税務調査でも、法人の役員報酬に問題が生じた場合などは、役員個人の所得に対して調査が実施されることもあります。
また、税務調査で調査対象となる期間は一般的には過去3年分までとなります。しかしながら、3年分の調査を行い、申告漏れやミスなどが発覚した場合は、5年分をさかのぼって調査をする場合もあります。また、巨額の脱税などが疑われる場合は過去7年分について調査される可能性も出てきます。
法人税の税務調査の実施件数と実施確率
令和5年に法人税の実地調査が行われた件数は59,000件です。また、法人税の申告件数は、3,176,000件とされています。そのため、税務調査の対象となる確率は、1.85%程度となります。1.85%の確率であれば、税務調査に入られる可能性の方が低いのではないかと思うかもしれません。
しかし、税務調査はランダムに行われているわけではありません。実際には、何らかの不正が疑われる法人や規模の大きな法人を抽出したうえで調査を実施しているケースが多いのです。
たとえば、令和5年に法人税の実地調査が実施された件数は59,000件ですが、このうち、何らかの申告漏れなど、ミスが発覚した件数は45,000件となっています。このデータから計算をすると、76%の法人が何らかのミスを指摘されていることが分かります。
法人の税務調査で指摘されやすいポイント
法人を対象とした税務調査でチェックされやすいポイントについてご説明します。
売上の計上漏れはないか
法人の税務調査では、売上の計上漏れがないか、契約書や納品書、請求書などの資料と照合しながら、正しく売上が計上されているか、細かなチェックが行われます。
また、事業主によっては売上の一部を隠蔽するために、特定の取引だけ、別の口座に入金させているケースもあります。税務調査で必要があれば、税務署では金融機関に対し、調査対象となる法人や個人の預金口座の残高や取引履歴を、本人の了承なく照合することが可能です。そのため法人が使用している口座だけでなく、代表者名義の個人口座などもチェックされる場合があります。隠し口座を使って売上を隠蔽していた場合も、税務調査が実施されれば、バレることになるでしょう。
売上の計上時期がずれていないか
売上の期ズレも税務調査でチェックされやすいポイントです。売上の期ズレとは、その事業年度に計上すべき売上額を翌年度などに計上することです。法人税の額は、売上の額から経費を差し引いて算出した所得額に応じて変わります。そのため、売上の計上時期がずれると、1年間の所得額が変わってしまい、納めるべき法人税の額が変わってしまうのです。そのため、税務調査では売上の計上時期にズレがないか、詳しく調査が行われます。
経費の水増しや二重計上はないか
経費を水増しした場合、売上から差し引ける額が増えるため、納税額を圧縮できます。そのため、架空の請求書を作って、支払いがあったかのように経費を計上するケースや同じ経費を二重に計上していたりするケースがあるのです。経費が正しく計上されているかどうかも、法人の税務調査ではチェックされやすいポイントです。
役員の私的な支出を経費にしていないか
役員の私的な支出は経費に計上することはできません。たとえば、接待交際費として計上されている支出には、取引相手などが含まれている必要があります。また、ゴルフの場合も接待で行ったゴルフの費用であれば、接待交際費として計上できますが、プライベートなゴルフの費用まで計上することはできません。そのほか、役員の趣味のために購入した美術品や役員が個人的な知り合いに贈るためのプレゼントの購入費用なども、経費には計上できないものです。私的な支出が経費として計上されていないかどうかも、税務調査ではチェックがなされます。
役員報酬の額は適切か、処理方法に問題はないか
役員報酬は原則として、損金算入はできません。ただし、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与については、損金算入が可能です。
定期同額給与は、役員の給与に該当するもので、毎月同じ額を支給するものであり、定期同額給与の額は、事業年度開始から3ヶ月以内でなければ変更ができません。そのため、定期同額給与の額が毎月同額になっていなければ、損金算入はできないのです。
また、事前確定届出給与は役員の賞与に該当するもので、支給にあたっては税務署に事前に「事前確定届出給与に関する届出書」の提出をしなければなりません。また、支給する際には届出に記載した額を届出に記載した日に支払う必要があります。届出内容と支給金額や支給日が違っていた場合、損金算入は認められません。
業績連動給与は、会社の業績状況に応じて支給する役員報酬のことです。業績連動給与はあらかじめ金額を確定する必要はないものの、報酬の算定方法が所定の指標を基にした客観的なものであり、有価証券報告書に記載または開示されていなければなりません。また、同族会社は業績連動給与を支給することはできません。
税務調査時には、役員報酬の支給方法だけでなく、役員報酬の額が従業員の給与と比べて極端に高額でないか、業務の内容に見合ったものか、同業他社と比べて相応な額かという点にチェックがなされます。
架空の人件費を計上していないか
従業員に支払う給与は、経費として計上できる支出です。そのため、経費を増やして所得額を圧縮するために、実際には雇用していない従業員に対して給与を支払ったように見せかけている場合があります。特に、飲食店などの人の出入りが多い法人などでは、架空の人件費を計上している例があり、税務調査時には従業員の勤務状況について詳細にチェックがなされます。また、実際には勤務していない家族などに対して給与を支払っているケースもあるようです。そのため、タイムカードと給与の支払い実績が合致しているか、社会保険や雇用保険などの加入状況と合っているか、履歴書は保管されているかなど、細かな点もチェックがなされます。
源泉所得税の計算や処理に誤りがないか
法人は、従業員に支払う給与から所得税を天引きし、個人に代わって納税をしなければなりません。また、正しい所得税の税額を算出するためには、1年間の総所得額や控除内容なども含めた計算が必要になります。そのため、法人では年末調整を行い、源泉所得税の額を計算しなければなりません。
税務調査では、期日までに源泉所得税をしっかり納付しているか、年末調整等における計算に誤りがないか、チェックが行われます。
棚卸資産は正しく計上されているか
小売業や卸売業など、商品を販売する事業は、販売商品を仕入れます。また、製造業では製品を作る材料などを仕入れるでしょう。販売や消費することを目的で仕入れ、保有しているこれらの在庫は棚卸資産と呼ばれます。
棚卸資産も税務調査でチェックされやすいポイントです。販売の見込みがない商品を処分し、廃棄損を計上するケースがあります。しかし、廃棄損は利益操作に使われる場合があるのも事実です。なぜなら、廃棄損は損金として計上できるため、所得額を圧縮でき、課せられる法人税を抑えることができるからです。そのため、実際には廃棄していない在庫を廃棄したように見せかけていないか、税務調査では細かくチェックがなされます。
消費税の申告漏れはないか
インボイスの登録をしていない場合、資本金が1,000万円以下で課税売上高が1,000万円を超えていない法人は、消費税納税義務はありません。しかし、消費税課税事業者であるにもかかわらず、消費税の納税をしていない法人もいます。税務調査では、課税売上高を調査し、消費税の申告漏れがないかについてチェックがなされます。
また、課税取引を非課税取引として扱っていないか、仕入税額控除の選定には誤りはないかなどについても税務調査ではチェックされます。
法人の税務調査をスムーズに終えるための対策
法人に対する税務調査では、上に紹介したようなポイントを中心に調査が進められますが、ご紹介したポイント以外にも調査は行われます。税務調査の目的は、間違いや不正を見抜き、正しく納税するよう是正をすることです。したがって、申告内容に疑わしき部分があれば、税務調査で指摘がなされることでしょう。
では、法人が税務調査をスムーズに終えるためには、どのような対策が有効なのでしょうか。
日頃から正しく売上や経費の管理をする
まず、日頃から売上や支払いなど、取引の状況を正しく記帳しておくことが大切です。取引内容はこまめに記帳することが重要であり、忙しいからといってまとめて記帳しようとすると、記帳漏れが生じる可能性が高くなります。
また、事業用の通帳以外にも通帳を持っている場合、取引内容を把握しにくくなるだけでなく、税務調査の際に不正を疑われる原因ともなります。現金での取引が多い業種の場合は、原則として、毎日売上は入金し、記帳しておくと安心です。
経費に関しても社内のルールを徹底するようにしましょう。さらに、領収書にはメモをつけ、支出の対象となった取引先や担当者の名前、支出の目的などを記載しておくと、税務調査時に経費であることを証明できる有効な対策となります。
決算月の計上ルールを徹底する
売上や経費などの期ズレは、税務調査でも指摘されやすいポイントです。期ズレを防ぐためには、売上をどのように計上するのか、税法に則り、一定のルールを設けるという対策も有効になるでしょう。特に、決算月の計上には注意するように気をつけ、ルールに則って処理を行うようにしましょう。
また、棚卸に関しても在庫表を作成し、在庫数が正しく管理されているか、定期的にチェックを行うことが大切です。不良在庫を廃棄損として計上する場合には、廃棄した棚卸資産の購入時期や購入金額、商品名などのリストを作成し、廃棄直前に写真を撮影するなどしておくと、税務調査時の対策となります。また、廃棄した際に廃棄を依頼した業者から発行された請求書等もしっかり保管しておきましょう。
役員報酬や人件費は正しく管理する
人件費を正しく支払っていることを証明するためには、日頃からタイムカードなどで出勤の記録を行い、記録もしっかり保管しておくことが大切です。また、役員報酬についても、定期同額給与や事前確定届出給与の損金算入要件をしっかり満たすよう、注意しましょう。また、役員報酬の額が妥当な額であることを証明できるよう、役員報酬の算出根拠なども示せるようにしておくとよいでしょう。
まとめ
法人が税務調査の対象になる確率はそれほど高いわけではありません。しかし、税務署では、正しく申告をしていない疑いが強い法人を中心に税務調査を実施する傾向にあります。そのため、税務調査を回避したいのであれば、日頃から正しく売上や経費を管理し、正しく申告・納税を行うことが最も重要な対策になります。また正しく処理をしていれば、税務調査の対象となった場合もスムーズに対応できるようになるでしょう。
しかしながら、これまでの申告内容に不備がある場合や申告内容が正しいか不安がある場合に税務調査の事前通知を受けた際には、1つの対策として税務のプロである税理士に相談することをおすすめします。
-免責事項-
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
- 現在、税務調査が入っているので困っている
- 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
- 税務調査に強い税理士に変更したい
- 自分では対応できないので、税理士に依頼したい
税務調査の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
- 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
- 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から対応できます
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断