メニュー
法人化
個人事業主の飲食店でもマイクロ法人を設立できる?メリット・デメリット、おすすめのタイミングを紹介

読了目安時間:約 6分
これまで個人事業主として営んできた飲食店の事業が軌道に乗ってきた場合に、法人化を検討するケースも多くあります。
そもそも、個人で飲食店を経営していた人が会社を設立することはできるのでしょうか。
結論として、経営者一人で飲食店を行っていた場合でも、マイクロ法人として会社の設立が可能です。ただし、法人化には良い点ばかりではないので十分考慮する必要があります。
本記事では、飲食店が法人化するメリットやデメリット、適切なタイミングを解説します。
飲食店を経営していて法人化に興味がある方は、ぜひこの記事を参考に会社設立に関する知識を深めていただけたら幸いです。
目次
マイクロ法人は経営者一人が事業を行う会社

一般的にマイクロ法人とは、役員や従業員を雇用せず、経営者一人で事業を行う小規模な法人を指します。
マイクロ法人には法的に明確な定義はありませんが、会社法で定められる会社設立のための条件を最低限満たしているものとも言えるでしょう。
税務上でメリットがある点や比較的運営がしやすいことから、フリーランスなどの個人事業主が社会保険料や税金を節減するのを目的に、マイクロ法人を設立するケースが多いです。
マイクロ法人で飲食店を経営できる?
個人事業主として飲食店を行ってきた事業主が、マイクロ法人を立ち上げることは可能です。
ただし、後述しますが飲食店の法人化にはメリットだけでなくデメリットもあるため、法人化を検討する場合は十分注意しなければなりません。
マイクロ法人は一人で経営を行うため、効率的かつ小規模な事業や業種が法人化に向いています。以下はその一例です。
- 資産運用
- Webクリエイター
- オンラインサロン運営
- フードデリバリー
- アフィリエイター
- マッサージ師・整体師
- 不動産業
- 執筆業
また、個人事業主としての業務を継続しつつ、マイクロ法人を設立することも可能です。ただし、同じ業種を選択すると税務署から不正な税務処理と疑われる場合があるため、業務内容や収益の流れを明確に区別しておくことが大切です。
マイクロ法人の設立方法
マイクロ法人を設立する際の基本的な流れを見ていきましょう。
- 会社の基本事項を決める
- 定款を作成する
- 法人印を用意する
- 資本金を払い込む
- 法人設立に関する各種申請を行う
- 法人口座を開設する
- 役員報酬を決定する
- 社会保険の手続きをする
このように、法人を設立する場合は、定款の作成や法務局での法人登記などが必要で、煩雑な手続きが発生したり、決算に伴う事務作業に手間がかかったりします。
スムーズに法人化を進めるためにも、法人化の目的を明確にしたうえで計画的に行うようにしましょう。
飲食店は法人化すべき?メリットを紹介

個人事業主として経営してきた飲食店が軌道に乗り、売上が上がってきた際にマイクロ法人の設立を検討するケースが多いかと思います。
ですが、どのようなメリットがあるのか具体的に知らない方もいるのではないでしょうか。
ここでは、個人事業主が飲食店を法人化するメリットをご紹介しますので、理解したうえで検討しましょう。
社会的信用が向上する
個人事業主と法人を比較すると、外部からの信頼度においては、一般的に法人の方が優位になることが考えられます。
法人を立ち上げる場合、法務局への登記が必要であり、その過程で設立日や所在地などの情報が登記簿に正式に記載されるので、会社が法的に認められた存在であることを示す証となります。
一方、個人事業主は税務署に開業届を出す必要はありますが、法人のように公的な登記簿で開業が証明されるわけではありません。
また、法人を設立する際には、ある程度の資本金を用意することが求められ、資本金の存在自体が経営基盤の強さを示す一つの指標となるため、企業としての信頼性が高いと判断される可能性があります。
節税対策になる
飲食店の法人化の大きなメリットとして、節税効果が得られる点が挙げられます。
法人化すると課税される税金の種類が個人事業主と異なり、経費として計上できる項目が増えるため、節税対策になるのです。
また、個人事業主の飲食店の場合、所得税は所得が多ければ多いほど税率が高くなり、最大税率45%の累進税率が適用されますが、法人の場合にかかる法人税は最大税率が23.2%であり、所得額が高くなっていったとしても、納める税金の割合がそれよりも高くなることはありません。
そのため、売上金額によっては法人の方が個人事業主の方が税負担が軽減される可能性があります。
消費税が2年間免除される

課税事業者である限り消費税の支払い義務が発生しますが、個人事業主が法人成りすると、最初の2年間は消費税が免除されるメリットがあります。
通常、消費税は前々年度の売上が1,000万円を超える場合に納付義務があるのですが、法人化した場合、原則として設立1期目・2期目は消費税の納税義務が免除されるケースがあります。
つまり、個人事業主で2年経営し、その後に法人化するとトータルで4年近く消費税が免税されるということになります。
ただし、これは資本金1,000万円以下で法人成りをした場合かつ課税売上高1,000万円未満の場合に限られますので注意しましょう。
詳しくは、国税庁「納税義務の免除」をご確認ください。
退職金を支給できる
個人事業主の場合、自身に対して退職金を支給できませんが、法人の場合は代表取締役である自身に対して勤続年数に応じた退職金を支給することができます。
退職金は、分離課税といって他の所得と分けて課税される仕組みで、税制上非常に優遇されているのが特徴です。
さらに、法人が支払った退職金は不当に高額なケースを除いては、原則として損金計上が可能となるため、節税効果も期待できます。
社会保険に加入できる
個人事業主から法人化すると、原則として社会保険に加入することが義務付けられています。
社会保険の加入にあたっては、事務負担が増えるのに加え、事業主が社会保険料の半額を負担しなければならないなどのデメリットもありますが、以下のようにさまざまなメリットもあるのです。
- 年金の給付額が増える
- 節税に繋がる
- 扶養の範囲内であれば親族も加入できる
- 人材を確保しやすくなる
このように、法人化すると社会保険の保障内容が充実し、従業員や役員に対する福利厚生が向上するため、優秀な人材を確保しやすくなり、人手不足に悩む飲食店にとっては大きなメリットになると言えるでしょう。
赤字を最大10年間繰り越せる
個人事業主の場合、青色申告をすれば赤字を3年間繰り越すことができます。
それに対して法人は、赤字を最大10年間繰り越せるのです。
そのため、法人化すれば、たとえ赤字になったとしても、翌年以降の黒字と相殺し、法人税を減らすことができます。
飲食店の場合、人材を確保するために、はじめに経費が多くかかる傾向にあるため、この赤字繰越を上手く活用すれば税金対策につながるでしょう。
賠償の範囲が限定される
個人事業主の飲食店では、経営が悪化して仕入れの未払いや金融機関からの借入の返済が滞った場合などは全て経営者個人の責任となり、個人が債務を抱えることになります。
しかし、法人化により、責任は出資額に限定される有限責任となるのです。
そのため、事業が法的な問題に直面したり、負債を負ったりした場合に、経営者の個人資産は大部分守られます。
飲食店の法人化にはデメリットもある

ご紹介したように、飲食店が法人化するとさまざまなメリットを得られますが、それと同時にデメリットも存在します。
個人事業主からの法人化を検討する場合は、会社設立後に後悔しないためにも、メリットとデメリット両方を比較する必要があるのです。
ここからは、飲食店が法人化する場合のデメリットについて説明していきます。
利益が少ないうちは税金の負担が重くなる
税務上のメリットが大きい法人化ですが、売上や利益が少ないうちに法人化すると、かえって税金の負担が重くなる懸念があります。
なぜなら、利益が少ないうちは法人税の税率と比較して所得税の税率が低いため、個人事業主でいる方が税金の面で有利になるからです。
そのため、小規模事業での法人化を検討している場合には、事業状況や将来性を十分に考える必要があります。
法人になると赤字の場合でも税金の支払いがある
個人事業主では、事業が赤字であった場合に所得税や住民税の負担がありませんが、法人は赤字や黒字に関係なく税金が発生します。
法人の場合は法人住民税が課されますが、法人住民税は、均等割と法人税割で構成されており、均等割は資本金や従業員数によって金額が定められるため、赤字であっても税金を納付しなければならないのです。
このように、赤字でも税金を支払わなければならないのは法人化のデメリットと言えるでしょう。
参考:総務省|法人住民税
会社を設立するコストがかかる
個人事業主の場合、税務署に開業届を提出することで手数料なく開業できます。
一方、法人化するにあたっては、法定費用を納めなければならないほか、以下の費用もかかる点に注意が必要です。
- 資本金
- 定款認証のための費用
- 登記費用
- 印鑑作成費用
資本金は1円でも会社設立が可能ですが、融資の際など信用度を得るためにはある程度の資本金があった方が良いでしょう。
また、法人化のための費用は会社の形態によっても異なりますが、株式会社の場合は20万円前後、合同会社の場合、6万円程度の費用が最低でも発生します。
そのため、節税効果を期待して法人化しても、損失の方が多くなり、後悔するケースも多いです。
事務負担が増える
法人化するにあたって、法人税申告書や決算書の提出が必要となり、年間の利益や費用を正確に記載するため、日々の事務作業が増加し、多くの時間や労力を必要とします。
飲食店としての仕事を行いながら、これらの作業も全て自分で行うとなれば、非常に大きな負担となってしまいます。その結果、業務が疎かになり、飲食店の経営自体が上手く行かなくなってしまう恐れも考えられます。
そのため、マイクロ法人の飲食店は会計業務や税務処理などを専門家に委託するなどの適切な対応を取るのが望ましいです。
飲食店が法人化するベストなタイミングは?
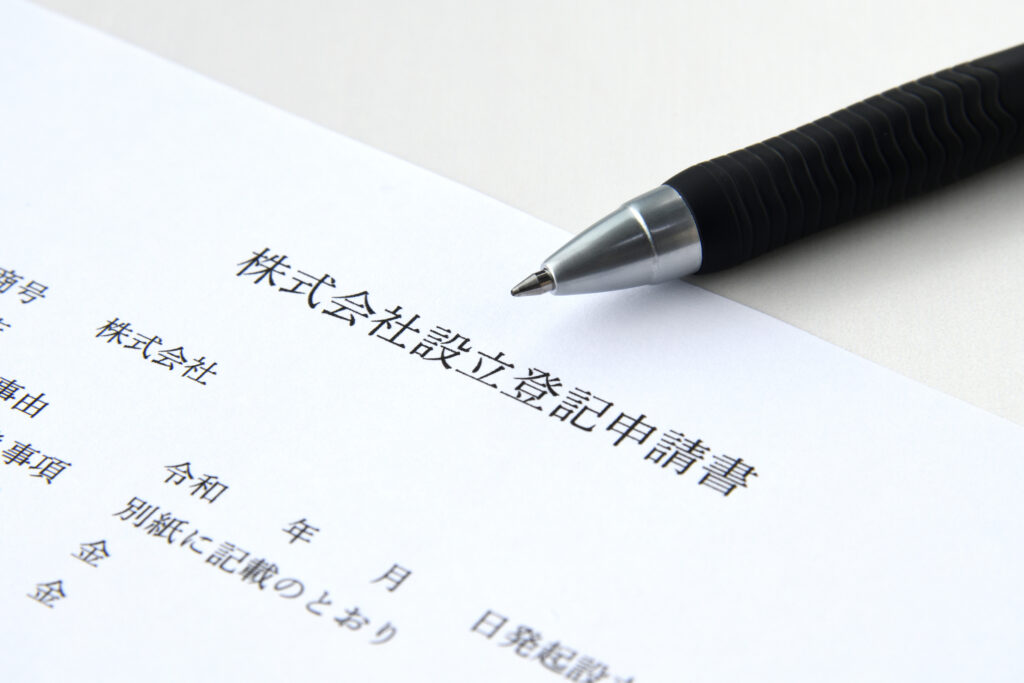
法人化には手間やコストがかかりますが、メリットも多いことから会社の設立を検討する飲食店事業主もいるでしょう。
しかし、事業規模などさまざまな事情によってデメリットが多くなることもあります。
個人事業主の飲食店が法人化する場合、以下のタイミングを検討するのが望ましいです。
- 年間売上が1,000万円を超えた場合
- 課税所得が800万円を超えた場合
- 従業員を雇用する場合
それぞれ説明していきますので、法人化の適切なタイミングを見極めましょう。
年間売上が1,000万円を超えた場合
前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者に該当するため、売上にかかる税金の他に消費税の支払いも発生します。
そのタイミングで法人化すると、最大2年間消費税の納税が免除されるので、年間売上が1,000万円を超える場合に法人化を検討するのが一つの目安になるでしょう。
仮に、売上が1,000万円を超えた翌年に法人化すると、そこから2年後に課税事業者になれば良いということになります。
ただし、インボイス制度により、売上1,000万円以下で課税事業者になっている場合はその限りではありません。
課税所得が800万円を超えた場合
年間売上が1,000万円を超えていなくても、課税所得が800万円を超えたタイミングで法人化を検討するのも良いでしょう。
課税所得が800万円を超えてくると、法人税率よりも個人事業主に適用される所得税率の方が高くなるため、法人化によって税負担の軽減が期待できます。
所得控除や役員報酬の額によっても変わってくるため、必ずしも法人化した方が得だとは言えませんが、法人化を検討する目安になるでしょう。
参考:国税庁|法人税の税率
従業員を雇用する場合
飲食店で働く人材を確保しようと考えているならば、法人化を検討するタイミングとも言えます。
法人化すると社会的信用度が上がるため、優秀な人材を雇用しやすくなり、飲食店としての信用度の向上や集客アップにも繋がるでしょう。
また、法人化によって給与所得控除も活用できるので、合理的な給与設定によりさらなる税負担軽減も期待できます。
飲食店の法人化は慎重に考えよう

飲食店で売上が上がってきても、個人事業主として経営していくのも一つの方法ですが、ある程度の安定した利益を挙げられるのであれば、税制面などを考慮して法人化を検討しても良いでしょう。
飲食店の法人化にはメリットやデメリット両方があるため、それぞれを比較して慎重に考えるのがおすすめです。
法人化すれば良いか迷っている方や、法人化といっても何から始めたらいいのか分からないという方は、税理士などの専門家に相談してみましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。










