メニュー
会社設立
建設会社の設立に必要な費用や許可とは?法人化するメリットも解説

読了目安時間:約 6分
建設業は、スキルや実績を積み重ねることで収入アップが見込める業界の一つです。そのため、将来独立して建設会社を設立しようと考える方もいるでしょう。
しかし、会社設立にあたっては必要な許可の取得や手続きを行ったり、設立費用や運転資金を用意したりと、やるべきことが多くあります。
そもそも、建設会社を開業するにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
本記事では、建設会社を設立するのに必要な費用や会社の種類、必要な許可について解説します。
また、建設業を営む個人事業主が法人化するメリットについてもご紹介しますので、ぜひこの記事を参考に、建設業の独立に必要な知識を身につけていただけたら幸いです。
目次
建設業で開業する方法は3つ!

建設業は一般的な企業と異なり技術力を活用した独立が可能であるため、自分が専門とするスキルや経験を身につけたあと、独立するケースが多いです。
建設業で独立し、開業する方法としては以下の3つがあります。
- 個人事業主として開業する
- 法人化する
- フランチャイズに加盟する
それぞれの方法を詳しくご紹介しますので、建設業の開業を検討している方は参考にしてください。
個人事業主として開業する
まず、法人を設立せず、個人事業主(一人親方)として事業を行う方法があります。
主に大工や型枠、塗装、左官、クロス貼りなど、一人で作業ができる業種やリフォーム関連の仕事で独立するケースが多いです。
個人事業主として事業を行う場合、税務署への開業届の提出や税金が優遇される青色申告の申請も行いましょう。
法人化する
建設業を法人として開業する場合は、株式会社や合同会社などの法人を設立して建設事業を行います。
法人化する場合は開業資金や法的な手続きが必要となりますが、個人事業主として事業を行うよりも、会社としての信用度を得られ、事業拡大も見込めるでしょう。
はじめは個人事業主で実績を積み、売上が上がってきたら法人化するケースが多いです。
フランチャイズに加盟する
フランチャイズとは、本部の有する商標や販売権、経営サポートなどを加盟店に与えるかわりに、対価として、加盟店が加盟金やロイヤルティを本部に支払うシステムを指します。
フランチャイズの場合、ノウハウだけでなく店舗や備品などを本部が用意してくれるケースも多く、自社で設備や体制を整えるためのコストや手間を省けます。
独立後は資金繰りに課題を感じるケースもありますが、フランチャイズでは本部のサポートを受けることで資金計画や経営ノウハウを学ぶ機会が得られることもあります。
ただし、比較的自由度が低く、本部への支払いが多く発生するといった部分には注意が必要です。
建設業の個人事業主・一人親方が法人化するメリット

建設業を営む個人事業主として売上や利益が伸びてきたら、法人化を検討する方も多くいるでしょう。
建設業の個人事業主が法人化すると、以下のメリットがあります。
- 事業を継続できる
- 信用されやすくなる
- 繁忙期を避けて決算期を決められる
- 節税効果が期待できる
- 有限責任になる
- 人材を確保しやすくなる
それぞれ詳しく説明していきます。
事業を継続できる
個人事業主として取得した建設業許可は取得した「人」に与えられるものであり、事業を個人間で受け渡す場合、この建設業許可は引き継げません。
その場合、引き継いだ人が建設業許可を新たに取得しなければならず、手数料が発生してしまうのです。
しかし、法人として許可を取得した場合には、その許可のまま事業を継続することができます。
ただし、専任技術者などの建設業許可要件を満たしている必要があるので注意しましょう。
信用されやすくなる
個人事業主としての事業を法人化すると、会社としての信用度が高くなり、具体的には以下のメリットがあります。
- 銀行からの融資を受けやすくなる
- 仕事を受けやすくなる
- 大手企業からの仕事を受注できる可能性がある
- 求人で目に留まりやすくなる など
建設業で仕事を受注するためには、信用してもらうことが特に重要です。
法人化すると、登録情報が法務局を通じて公開されるため、企業としての透明性が高まり、信頼性をアピールしやすくなる可能性があります。
繁忙期を避けて決算期を決められる
個人事業主の場合、2月中旬から3月中旬に確定申告をしなければならず、個人の都合で申告時期を変えることはできません。
しかし、法人化すると決算期を自由に決められるので、建設業の繁忙期を避けて決算期を設定できるのです。
企業の決算月で最も多いのは3月、9月、12月であり、建設業界ではこの前に工事を終わらせようと仕事が集中するケースが多く、現場に入りながら確定申告の作業も行う事業者の場合、この繁忙期を避けた決算月にした方が、落ち着いて作業できるでしょう。
節税効果が期待できる

個人事業主は所得が増えれば増えるほど税率が高くなる累進税率が適用されますが、法人化すると所得額が高くなったとしても、法人税は一定税率となるため節税効果が期待できます。
事業の利益が大きい場合には法人の方が支払う税金が安くなるのでメリットが大きいです。
また、法人化することで経費と認められる費用も多くなるため、会社を設立した方が税金面で優遇されます。
有限責任になる
個人事業主の場合は、賠償責任が無限であるのに対し、法人化すると有限責任となるため、賠償責任の金額に対して制限が発生します。
つまり、個人事業主が経営破綻すると事業主が多額の負債を背負ってしまったり、損害賠償を請求された際に全額支払わなければならなかったりと、個人の負担がかなり大きくなります。法人では原則として出資額の範囲で責任を負う「有限責任」となります。
建設業は高額な案件を取り扱うものなので、万が一のリスクを考えた場合に法人化した方がメリットが大きいといえます。
人材を確保しやすくなる
個人事業主でも人材の確保は可能ですが、法人の方が集まりやすいとされています。
法人化すると社会的信用が高くなるほか、厚生年金保険や健康保険などの社会保険に加入するため、それが社員の安心材料になるのです。
しかし、法人化で必ずしも優秀な人材が確保できるとは限らず、事業の規模や安定性も重要なポイントとなります。
建設会社を設立するために必要な基礎知識
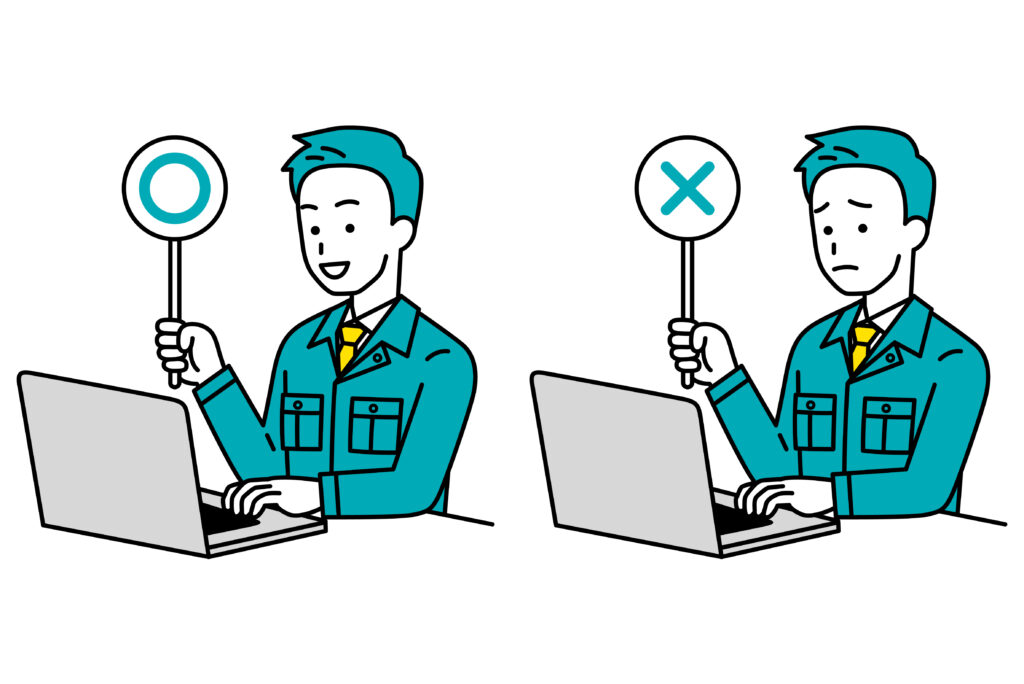
建設業界で独立・開業するにあたっては個人事業主として開業届を出し、事業を立ち上げることもできますが、先程ご紹介したように、法人化した方が有利な場合もあります。
ここでは、建設業の会社設立で必要な基礎知識をご紹介しますので、法人化を検討している方は参考にしてください。
建設業の開業には建設業許可が必要?
建設業許可は、建設業を営む場合に取得する必要がある許可のことを指し、軽微な建設工事の場合には必要ありませんが、以下の建設工事に該当する場合には建設業許可が必要となります。
- 請負代金が500万円以上の工事を請け負う場合
- 建築一式工事について、木造住宅以外の工事で1,500万円以上、または木造住宅で延べ床面積が150平方メートル以上の工事
このように、許可が必要ないケースは小規模な工事に限られるため、建設業で会社を設立するのであれば、基本的に建設業許可は必要と考えた方が良いでしょう。
なお、建設業許可の取得にあたっては以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 財産的基礎や金銭的信用があること
- 欠格要件に該当していないこと
参考:国土交通省|建設産業・不動産業:建設業の許可とは
建設会社を設立するなら合同会社と株式会社どちらにすべき?
建設業を法人化する場合、多くは株式会社もしくは合同会社で行われます。
株式会社は出資者である株主と法人の経営者の役割が切り離されている会社を指し、一方で合同会社は出資者が会社の経営者と同一である会社をいいますが、株式会社と合同会社では以下の違いがあるのです。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 会社の所有者 | 株主 | 出資者 |
| 経営を行う人 | 所有者と異なる | 所有者と同一 |
| 意思決定の要件 | 株主総会 | 全社員の同意 |
| 設立費用 | 約22万円 | 約10万円 |
| 決算公告の有無 | あり | なし |
| 役員の任期更新 | 通常2年・最長10年ごとに必要 | なし |
費用を抑えたいのであれば合同会社が適していますが、一般的には株式会社の方が対外的な信用度が高いとされる傾向にあります。
それぞれの違いを比較し、自社に合った会社形態を選択しましょう。
建設会社の設立にはいくらかかる?主な費用を解説

建設会社の設立を検討している方の多くが気になるのは、費用面ではないでしょうか。
法的な手続きや建設業許可申請など、他業種に比べると開業時にはある程度の資金力が必要になります。
ここでは、建設会社の設立に必要な費用をご紹介しますので、開業にどれだけの資金を用意すれば良いのか悩んでいる方は参考にしてください。
会社設立に必要な費用
会社を設立する際にかかる費用は、株式会社か合同会社、どちらの形態で開業するかによって異なります。
先述しましたが、株式会社では最低でも20万円前後、合同会社では10万円程度の費用がかかり、内訳は以下の通りです。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 定款用収入印紙代 | 40,000円(電子定款の場合は不要) | 40,000円(電子定款の場合は不要) |
| 定款の謄本手数料 | 約2,000円(250円/1ページ) | 0円 |
| 定款の認証手数料(公証人に支払う手数料) | 資本金100万円未満:30,000円 資本金100万円以上300万円未満:40,000円 資本金300万円以上:50,000円 | 0円 |
| 資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
| 印鑑作成費用 | 1万円程度 | 1万円程度 |
| 登録免許税 | 150,000円または資本金額 × 0.7%どちらか高いほう | 60,000円または資本金額 × 0.7%どちらか高いほう |
建設業許可申請に必要な費用
建設業許可は国が定めた一定の要件をクリアしていることの証明となるため、建設業を営む多くの人が許可を取得していますが、申請するにあたって政府に手数料を支払う必要があります。
政府に納付する手数料は、建設業許可の種類や営業所の所在地によって以下の違いがあります。
- 知事許可で建設業許可を取得する場合:9万円
- 大臣許可で建設業許可を取得する場合:15万円
なお、建設業許可の更新は5年に一度行う必要があり、更新費用は一律5万円です。
詳しくは、管轄の許可行政庁などにお問い合わせください。
参考:国土交通省|建設産業・不動産業:許可申請の手続き
専門家に依頼する場合は別途報酬が必要
会社設立の手続きを税理士や司法書士、公認会計士、社会保険労務士などに代行依頼する場合には、上記でご紹介した費用のほかに、別途で報酬を支払う必要があります。
会社設立にあたっては、やらなければならないことが多岐に渡りますが、専門家に依頼すればスムーズに開業することができるでしょう。
それぞれの士業では以下のように専門分野が異なるため、サポートを受けたい専門家に依頼するのが望ましいです。
- 行政書士:基本事項決定の相談、定款の作成・認証、許認可の代行など
- 司法書士:資本金の払い込み以外の手続きなど
- 税理士:法人化に向けた相談、税務関係の届出書の作成・提出の代行など
- 社会保険労務士:社員を雇用する場合の社会保険の手続きなど
会社設立の代行費用は依頼先や事業規模などによっても異なりますが、前述した費用のほかに報酬として別途10〜20万円程度支払う必要があると覚えておきましょう。
初期投資や運転資金として数百万円が必要
建設会社を開業するにあたっては、事務所の備品や機械設備など初期投資としての資金と、事業が軌道に乗るまで安定的かつ継続的に運営するために最低3ヶ月程度の運転資金が必要となります。
業種や事業規模によっても異なりますが、500~1,000万円程度用意しておくと安心といえるでしょう。
資金が不足するようであれば、日本政策金融公庫の融資制度や自治体の制度融資、補助金や助成金の活用などの資金調達も検討しましょう。
建設会社設立にはメリットも多いが資金も必要!

建設業界で起業する際、個人事業主としてではなく会社を設立する場合には、信用度や税金面などで多くのメリットがあります。
しかし、建設業の開業には基本的に建設業許可の取得が求められ、一般的な業種よりも手続きが難しくなるほか、費用も多くかかります。
スムーズに事業を行うためにも、開業に必要な費用や許可について把握し、必要があれば税理士や行政書士などの専門家に会社設立に必要な手続きの代行を依頼したり、資金調達方法について考えたりしましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。










